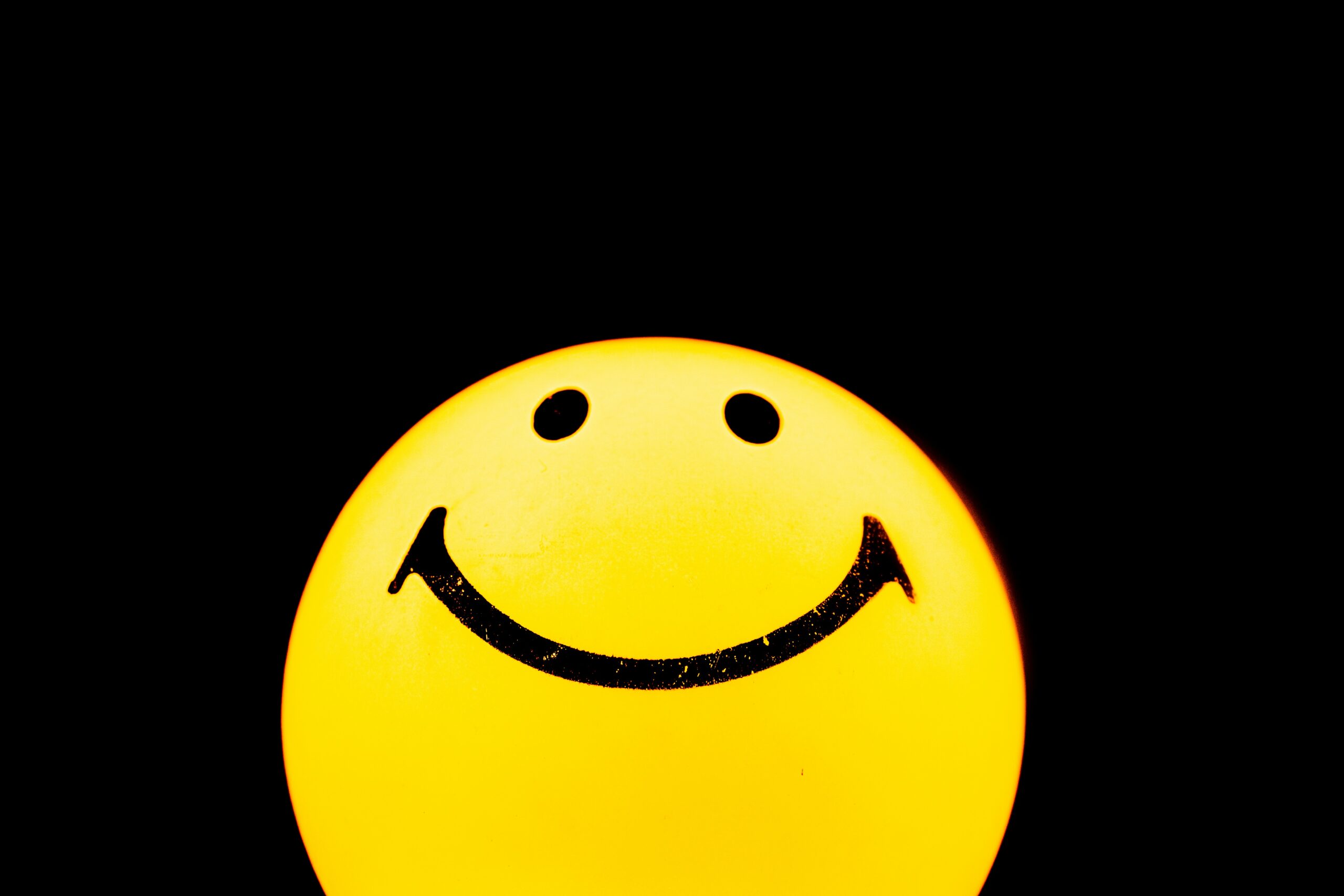
〝愛着(アタッチメント)″とは、〝特定の養育者との情緒的な絆″のことを指します。
子どもは養育者との愛着関係を基盤として、その後の対人関係を発展させていきます。
一方で、幼少期の愛着形成がうまくいかないことで、〝愛着障害″に繋がる危険性があります。
〝愛着障害″のある子どもへの対応には、様々な方法があります。
それでは、全ての愛着障害の子どもに対して万能な対応方法はあるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害のある子どもへの対応について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、子どもに合った関わり方について解説していきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.」です。
【愛着障害のある子どもへの対応】子どもに合った関わり方について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
どの子にも共通した〝こうすればいい″というかかわり方があるのではなく、その子の特徴に合ったかかわりを見つけることが大切なのです。
その子に合ったかかわりとは、愛着という絆を結んでいける<安心基地><安全基地><探索基地>の働きを意識しながら、こどもにとって〝その基地機能を意識できるかかわり″と言えます。
著書の内容から、愛着障害のある子どもへの関わり方として、全ての子どもに共通した万能な対応方法があるのではなく、子どもたち一人ひとりの特徴に合った関わり方を探していくことが大切だと記載されています。
そして、一人ひとりの子どもに合った関わり方を探していく上でのキーポイントとして、子どもが〝安心基地″〝安全基地″〝探索基地″を意識できる関わりをしていくことが必要だと考えられています。
そのためには、まず、ポジティブな感情を生み出す〝安心基地″、ネガティブな感情を減らす〝安全基地″、そして、基地を基盤として旅にでる機能となる〝探索基地″が持つ言葉の意味とその内容を深く理解していくことが重要だと言えます。
また、自閉スペクトラム症(ASD)などにおいては、関係作りの際に、発達特性を踏まえた関わり方も考慮していく必要があります。
関連記事:「【愛着で大切な3つの基地機能】安心基地→安全基地→探索基地のメカニズム」
ここから先は、著者の療育経験の中で、うまく著者との間で愛着が形成(信頼関係の構築が)できるようになった過程について見ていきます。
著者の経験談
著者は活動において、子どもの興味関心の世界に寄り添い、一緒のその世界を模索していきながら、その世界の楽しさ・面白さを共有・共感することを大切にしています。
興味関心の世界を分かち合う経験は、子どもが、著者に対して多くのポジティブな感情を抱くことに繋がっていきます。
子どもにとって〝この大人がいることで楽しい気持ちになれる!″〝もっと一緒にいたい・遊びたい!″といった気持ちを抱くのだと思います。
こうした経験を豊富に持つことで、子どもは、様々な感情をうまく表出できるようになっていくだと思います。
それは、怒り・悲しみ・不安などネガティブな感情も含まれています。
ポジティブな感情を基礎として、著者との間に少しずつ信頼関係ができてくると、今度はネガティブな感情についても伝えてくることが増えていきます。
最初は、パニック・癇癪などの表出方法だったものが、言葉の発達も含めて、徐々に言葉で困り事を相談しにくる様子が増えていきます。
そこで、著者がその思いを受け止め、一緒の解決方法を探していく姿勢を見せることが、次の段階ではとても大切だと実感しています。
ここまでが、安心基地と安全基地の形成のプロセスだと言えます。
そして、次に、著者が見ていない出来事(休日の過ごし、学校での出来事など)について、報告する様子が見られる場合が出てきます。
また、何かに挑戦しようとする際に、著者が少し背中を押すことで〝やってみよう!″といった気持ちが湧いてくることもよくあります。
こうした様子が、探索基地の形成のプロセスだと言えます。
愛着に問題のあるケース、ないケースも含めて、こうした信頼関係の構築のプロセスは多くの子どもたちに見られるように思います。
以上、【愛着障害のある子どもへの対応】子どもに合った関わり方について療育経験を通して考えるについて見てきました。
子どもたちに合った関わり方は、愛着形成を意識した関わり方から多くのヒントを得ることができます。
そして、愛着障害のある子どもには、さらに、安心基地→安全基地→探索基地を意識した関わり方が必須だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も愛着障害のある子どもも含めて、多様な子どもたちへの関わり方についてさらに学びを深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【発達障害児と信頼関係をつくるために大切な2つのこと】自閉症を例に考える」
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.









