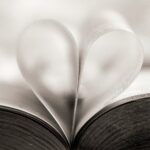〝愛着(アタッチメント)″とは、〝特定の養育者との情緒的な絆″のことを指します。
子どもは養育者との愛着関係を基盤として、その後の対人関係を発展させていきます。
一方で、幼少期の愛着形成がうまくいかないことで、〝愛着障害″に繋がる危険性があります。
〝愛着障害″のある子どもへの対応は、障害の程度にもよりますが非常に大変となる場合が多くあります。
それでは、愛着障害のある子どもへの対応として、どのような関わり方が必要となるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害のある子どもへの対応について、愛情が伝わる5つの関わり方について解説していきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.」です。
【愛着障害のある子どもへの対応】愛情が伝わる5つの関わり方について
著書には、愛情が伝わる5つの接し方についての記載があります(以下、著書引用)。
「1対1」で同じことを一緒にする
情報収集して「こんなことがあったのね」と先取りする
「これ、してもいいよね?」を見逃さない
報告には「わかるよ、その気持ち!」と共感する
「今、こう思っているよね?」と気持ちを言い当てる
それでは、次に、以上に5つの関わり方について具体的に見ていきます。
1.「1対1」で同じことを一緒にする
以下、著書を引用しながら見ていきます。
こどもの感受性をいちばん察知しやすいのは、実は「同じことを一緒にやっているとき」です。
必ずポジティブな気持ちになれることに誘うのがポイントです。
結果的にこどもが、「この人は自分がいい気持ちになれることに誘ってくれる」という感覚を得られることが大切です。
著書には、〝「1対1」で同じことを一緒にする″相手として、キーパーソン(子どものことを一番よく知っている人)の存在が必要だと記載されています。
そして、キーパーソンが感受性を働かせるためには、同じ活動を子どもと一緒に行うことが必要です。
活動内容は子どもがポジティブな感情を生起できるものが重要です。
そして、キーパーソン自らが先行して活動へと誘うことが大切です。
活動を通して、楽しい気持ちを言葉にしていくことが必要ではありますが、ネガティブな感情は取り上げないことがポイントです。
ポジティブな感情を伴う活動をキーパーソンと1対1で行うことで、キーパーソンと関わることで、よい気持ちが得られるといった実感が持てることが重要だと言えます。
2.情報収集して「こんなことがあったのね」と先取りする
以下、著書を引用しながら見ていきます。
キーパーソンへの情報集約ができていれば(中略)こちらが先手を打って「こんなことがあったんだって?すごかったね。うれしかったね」と伝えてポジティブな感情に誘うことができるのです。
こどもが困ったことや失敗したことを伝えてくれたときは必ず、「大丈夫だよ」とフォローしてください。
著書には、〝情報収集して「こんなことがあったのね」と先取りする″こともキーパーソンの重要な関わりだと記載されています。
先に見たように、キーパーソンとは子どものことを一番よく知っている人であるため、子どもに関わる人たちが連携していきながら、キーパーソンに子どもに関する多くの情報を与えていくことが、先取り行動へと繋がっていきます。
先取り行動、つまり、先手を打つことで、子どもをポジティブな感情に誘う経験が増えていきます。
そして、次に、子どもが困ったこと、失敗したことなど、ネガティブな感情へのフォローを行うことです。
これは、先に見たポジティブな感情の積み上げ、つまり、安心基地ができてくるに伴い、今度は、ネガティブな感情へのフォロー、つまり、安全基地の形成の段階に入っていく状態だと言えます。
この際に、ネガティブ感情への共感や問いかけではなく、あくまでも、〝大丈夫″だといったフォローに徹することが大切になっていきます。
3.「これ、してもいいよね?」を見逃さない
以下、著書を引用しながら見ていきます。
気持ち的に99%は「やろう」と自分ですでに決めているけれど、最後の1%でキーパーソンに確認して背中を押してもらおうとしています。
この参照視は、ふたりのあいだの絆を確認する大切な行為です。
著書には、子どもの〝「これ、してもいいよね?」を見逃さない″といった参照視に対して、最後に〝いいよ!″と背中を押してあげることが大切な関わりだと記載されています。
参照視とは、子どもが自分の行動の判断を他者(子どもにとって重要な人)に委ねる行為だと言えます。
子どもが参照視できるためには、安心基地・安全基地が形成されている必要があります。
そして、参照視を後押しすることが子どもとの絆の確認に繋がり、自立行動の育ちに貢献していくと考えられています。
4.報告には「わかるよ、その気持ち!」と共感する
以下、著書を引用しながら見ていきます。
一緒に何かすることが習慣化してくると、こどもはやがて、キーパーソンと離れているあいだに起きた出来事やひとりでやったことを、帰ってきて報告してくれるようになります。
著書には、子どもがキーパーソンへの〝報告には「わかるよ、その気持ち!」と共感する″ことが非常に重要であると記載されています。
子どもは、最初はキーパーソンと1対1の活動に始まり、その過程において、安心基地・安全基地が形成されてくると、今度は、探索基地が機能し始めるようになっていきます。
探索基地とは、重要な人(キーパーソン)から一度離れて探索・冒険をして通して、再度、重要な人のもとに戻ってくる基地だと言えます。
ここで、重要となるのが探索・冒険内容の〝報告″です。
つまり、自分が重要な人が見ていないところで自分がやってきたこと・見てきたことを伝えることです。
子どもの〝報告″に対しては、強制はせず、子どものタイミングの発信を待ち(時にはきっかけを作ることも必要)、発信に対して、共感を示すことがとても大切だと考えられています。
5.「今、こう思っているよね?」と気持ちを言い当てる
以下、著書を引用しながら見ていきます。
あなた自身がかかわっていないことについても、「こんなふうに思ってやったんだよね?」と、こどもの気持ちを言い当てることができるようになったとき、愛着の絆はしっかり結ばれていきます。
著書には、〝「今、こう思っているよね?」と気持ちを言い当てる″ことを大人ができたとき、愛着の絆は形成されてきていると記載されています。
つまり、キーパーソンとなる重要な人が、子どもと関わっていない状況においても、その状況に関する気持ちを言い当てることができるようになったとき、子どもの心の中に、重要な他者の存在をしっかりと感じることができる状態になってきたと言えます。
これは、子どもが心の中に重要な他者の存在を思い浮かべることで安心感を得られる状態であり、専門用語で〝内的作業モデル″とも言われています。
〝今、ここ″を離れても、重要な人との繋がりを感じることができている状態が愛着形成においてとても大切だと言えます。
以上、【愛着障害のある子どもへの対応】愛情が伝わる5つの関わり方について見てきました。
愛着障害のある子どもへの対応はとても困難だと言えます。
そのため、今回見てきた対応方法も含めて、愛着障害への理解と対応を学んでいくことが重要だと感じます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育実践を踏まえて、愛着障害に関する様々な知識を吸収していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「愛着障害への対応[してはいけない対応5選]」
関連記事:「愛着に問題のある子の支援-「叱る」対応の問題点について-」
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.