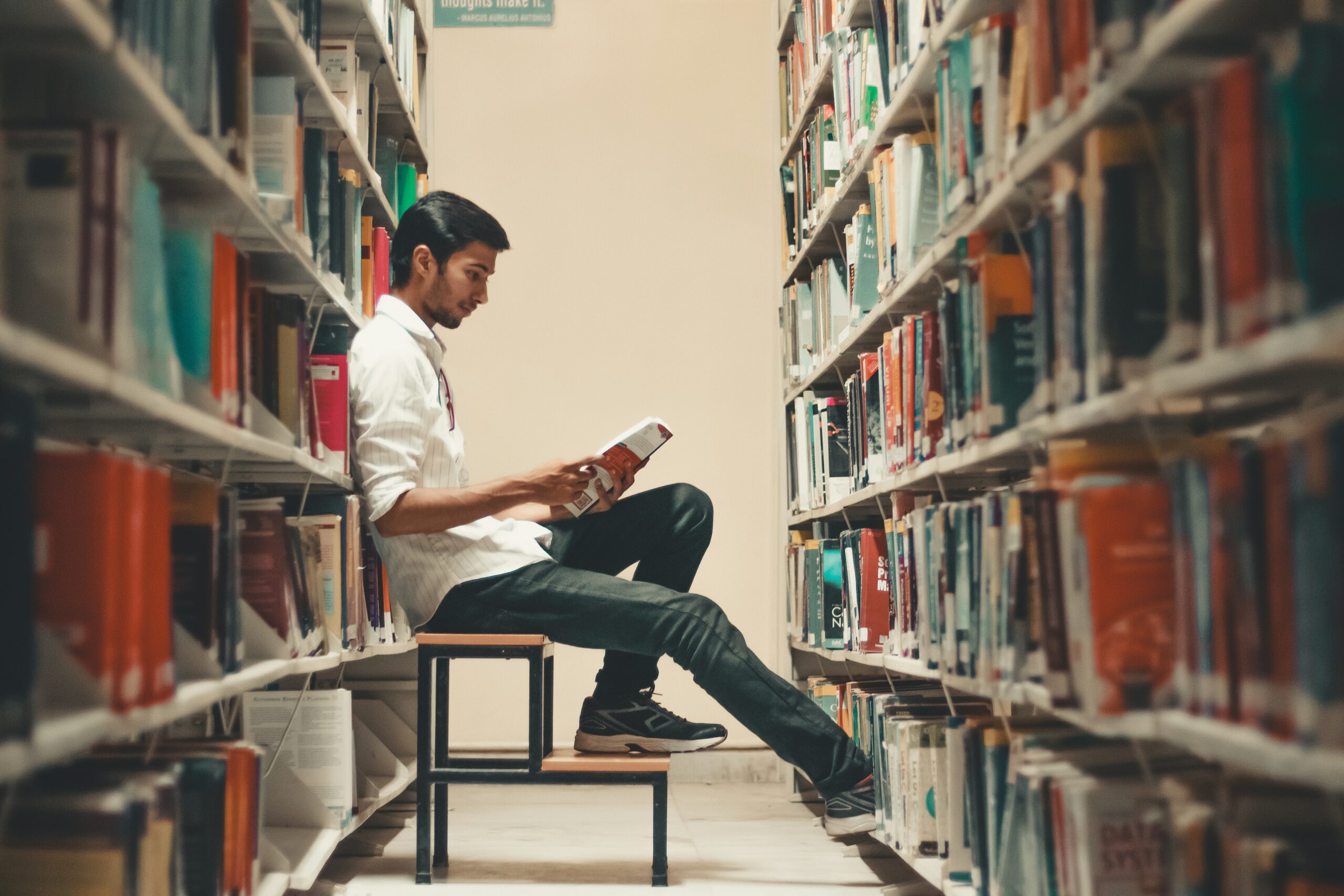
この記事では、著者が療育実践で非常に役に立った視点についてお伝えします。
今回取り上げる理論・視点は、①太田ステージ、②感覚と運動の高次化になります。
これらの理論・視点を知ることで、著者は障害のある子どもたちの発達段階についての理解が加速度的に進んだと実感しています。興味のある方は参考までに調べてみて下さい。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
①太田ステージ
認知発達に関して、ピアジェの理論をベースに感覚運動期~概念形成期までの発達をわかりやすく述べられているのが特徴です。簡単に取れるアセスメント方法についても解説があります。発達段階ごとに遊びについての紹介もあります。
言葉の前の段階から、ある程度言葉をはなしはじめ様々な概念理解まで進んだ子どもたちまでを対象としています。
関連しておすすめなのは、立松英子さんの「発達支援と教材教具」シリーズです。太田ステージについて非常にわかりやすく解説されており、障害児に合わせた教材教具の説明も豊富に記載されています。
私自身、太田ステージの認知の発達段階や、立松英子さんの教材教具の紹介など、以前の療育施設で発達を理解する視点と子どもに合わせた教材を考えるときに非常に参考になりました。
太田ステージ関するお勧め書籍紹介
②感覚と運動の高次化理論
「感覚と運動の高次化理論」は宇佐川浩さんという方が考え出した理論です。
太田ステージでは認知の発達が中軸となっていましたが、この理論は認知だけはなく、感覚や運動、言語や情動など認知以外の様々な要因との関連付けなども記載されています。
また、太田ステージと同様に、感覚と運動という原初的な発達から概念形成段階までいくつかの段階に分けて解説されており、それぞれの段階ごとの遊びの紹介もあります。また、アセスメント方法も紹介されています。
私は初めて「感覚と運動の高次化理論」に出会ったのは、療育施設での勤務三年目でした。初めてこの理論を学んだ時には衝撃を受けました!あまりの衝撃に仕事後に毎日読み込んだほどです。一言でいいますと、現場の子どもたちをより深く理解できているという納得感が得られました。
ただ難解であるため、初心者にはお勧めできない部分もありますが、探求心の強い方には非常に参考になるかと思います。私は障害児の発達を理解する究極の理論だと今でも思っています!
感覚と運動の高次化に関するお勧め書籍紹介
以上が、著者が療育実践で子どもたちを理解するために非常に参考になった視点です。
障害のある子どもたちの発達を理解することは簡単ではありません。それは定型発達児とは異なる発達を辿るからです。
今後も他の視点や今回取り上げた内容についてさらに深堀していきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
関連記事:「【発達支援(理論編):療育実践で役立つ視点】感覚統合理論・関係論的アプローチ」
関連記事:「【発達支援(理論編):発達支援の現場で役立つ視点】発達特性・愛着」









