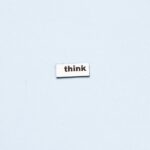「 年別アーカイブ:2022年 」 一覧
-

-
2022/07/03 -ニューロダイバーシティ
ニューロダイバーシティという言葉を聞いたことがあるでしょうか? 著者は発達障害領域で療育をしています。 そのため、少し前から、書籍やメディアなどでこの言葉を聞くことが増えてきた印象があり …
-

-
【発達障害とは何か?】「発達」の意味を踏まえて「発達障害」について考える
「発達障害」への理解が、ここ近年急速に進んできています。 発達障害と言えば、自閉症スペクトラム障害(ASD)やADHD、学習障害など様々なものがあります。 一方で、「発達」 …
-

-
2022/07/01 -生活療法的視点
発達支援(療育)では、日々の子どもたちの困り感・生きづらさを支えることがとても大切です。 関連記事:「発達障害の「生きづらさ」について-療育経験を通して考える-」 それは、発達障害を生活 …
-

-
発達の多様性を理解することの大切さについて-発達障害児・者との関わりを通して考える-
2022/06/29 -ニューロダイバーシティ, 発達
発達障害のある人たちと、療育(発達支援)の現場で関わっていると非常に個々によって育ちや成長が多様であると実感します。 日本の学校教育ではとかく、協調性など周囲に合わせることや、一般的な基 …
-

-
療育現場での体験を客観化する方法-間主観性・相互主体性・エピソード記述から-
療育現場では日々子どもたちとの関わりから、様々な体験を得ることができます。 様々な体験の中には、子どもたちの言動や行動の意図や意味がなかなか見いだせないといった問いも出てきます。 一方で …
-

-
療育現場で子どもを観察する視点-行動科学と間主観性による客観性の違い-
療育現場で発達に躓きのある子どもたちと接していて難しいのは、子どもたちの行動の背景要因や行動動機などです。 例えば、もの投げや癇癪など療育者がその対応に困る行動など、「なぜこうした行動を …
-

-
【発達障害の強弱・重複(併存)について】療育経験を通して考える
日本では発達障害といえば、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、学習症(LD)などが主な症状としてあります。 また、DSM-5(アメリカ精神医学界の診断と統計マニュア …
-

-
学童期の療育で得意なこと・好きなことを見つける重要性について
療育で大切なこととして、学童期の課題では、学習や仲間関係が主なものとしてあります。 中でも、仲間関係から得られる自己有能感はともて大切な発達課題です。 関連記事:「療育で大 …