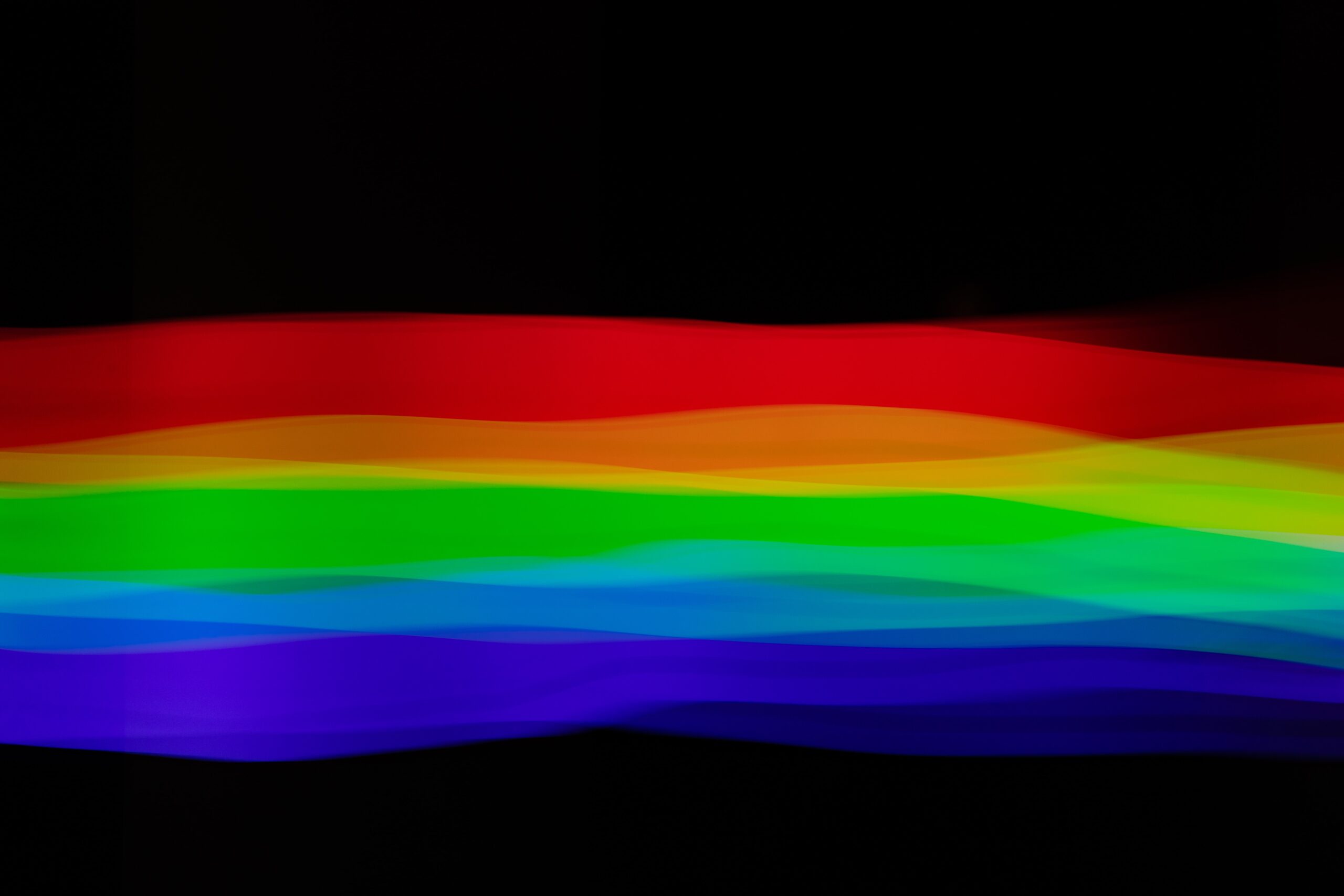
‟行動障害(Challenging Behaviour)”とは、自傷や他害、パニックや癇癪、器物破損など、その行動が自他に悪い影響を及ぼすものだとされています。
行動障害と強度行動障害とを定義上分類している方もおりますが、今回は、以下の参照資料に基づいて‟行動障害”に統一して話を進めていきます。
関連記事:「行動障害と強度行動障害の違いについて-行動障害の背景にあるものとは?-」
行動障害は非常にトラブルに発展しやすく対応が難しい行動だと考えられていますが、未然に行動のシグナルなどをキャッチする方法はあるのでしょうか?
そこで、今回は、行動障害の特徴について、臨床発達心理士である著者の経験談の交えながら、発展段階から行動に至るまでのプロセスについて理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「英国行動障害支援協会(編)清水直治(監訳)ゲラ弘美(編訳)(2015)行動障害の理解と適切行動支援 英国における行動問題への対処アプローチ.ジアース教育新社.」です。
行動障害の特徴について【発展段階をキーワードに考える】
以下、著書を引用しながら見ていきます。
行動障害が “突然に” 勃発したり、前ぶれもなく起こることはほとんどありません。
行動障害は、(中略) “勃発曲線” をたどって、4つの段階を経て発展していきます。
著書の中では、行動障害の問題行動に至るまでの発展段階を“勃発曲線”として4つの段階があると想定しています。
その4つとは、1.緑信号帯、2.黄信号帯、3.赤信号帯、4.青信号帯です。
それでは、以下、それぞれについて説明していきます。
1.緑信号帯
以下、著書を引用します。
気分が安定
当人の精神状態は落ち着いていて、積極的に活動に参加することができます。
著書の内容から、緑信号帯は、気分が安定した状態であり、様々な活動に参加することが可能な状態になります。
著者も行動障害のある人(その傾向がある人)の気分が安定している場合には、活動への意欲が高く、少しのことでは情緒が崩れな心穏やかな状態にあると感じています。
一方で、情緒が安定しているからある程度のことは大丈夫だと考えるのではなく、引き続き安心して過ごせるための工夫を心掛けるようにしています。
2.黄信号帯
以下、著書を引用します。
不安、興奮、イライラの開始
初期の徴候として、当人の不安やイライラが始まる段階です。
著書の内容では、黄信号帯は、行動障害の問題行動が発生する一歩手前の段階に位置付けています。
そのため、次の段階に入らないための予防・対応が重要になります。
著者の経験からも、この段階に入ると、明らかに不満・不安の表情に変わり、声のトーンや話の内容なども鬼気迫る感じが伝わってきます。
そのため、ゆっくり気持ちが落ち着くのを待つというよりも早期の対応を心掛けるようにしています。
3.赤信号帯
以下、著書を引用します。
事態の勃発
暴れたり極度に興奮したりという行動障害が、実際に勃発してしまった段階です。
著著の内容から、赤信号帯は、行動障害の問題行動が発生した段階になります。
そのため、早急に事態を落ち着かせる対応が重要になります。
著者の経験からも、この段階に入ると、沈静化まで非常に時間がかかるといった印象があります。
中には、長時間にわたり、イライラが収まらないこともあったり、長い時間をかけての個別対応の末にようやく落ち着いたケースはこれまで多くありました。
そのため、この段階では周囲の力も借りながら、冷静に気持ちを落ち着けることにフォーカスした対応を心掛けるようにしています。
4.青信号帯
著書を引用します。
落ち着きを取り戻すが、まだ注意が必要
事態が収まり、当人が前の状態に回復し始め、再び落ち着きを取り戻す段階です。
著書の内容から、青信号帯は、一度は赤信号帯を通過し、回復した(落ち着いてきた)が、まだ油断はできない段階になります。
著者の経験から、この段階に些細な刺激によって再び赤信号帯に戻ってしまった経験は少なからずあります。
そのため、できるだけ本人にとって刺激となるものを周囲から取り除く、安心できる刺激や環境調整などを心掛けるようにしています。
以上、行動障害の特徴について【発展段階をキーワードに考える】について見てきました。
このように、行動障害の特徴について、発展段階を信号に置き換えると状態の変化を捉えやすいように思います。
著者の経験からも、以上の4つの段階は間違いなく存在するものであり、非常に理解しやすいものであると感じます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も行動障害について様々な方面から理解を深め、実践に繋げていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「行動障害のアセスメントで必要な視点について【状況要因と契機要因を通して考える】」
行動障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「行動障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
英国行動障害支援協会(編)清水直治(監訳)ゲラ弘美(編訳)(2015)行動障害の理解と適切行動支援 英国における行動問題への対処アプローチ.ジアース教育新社.









