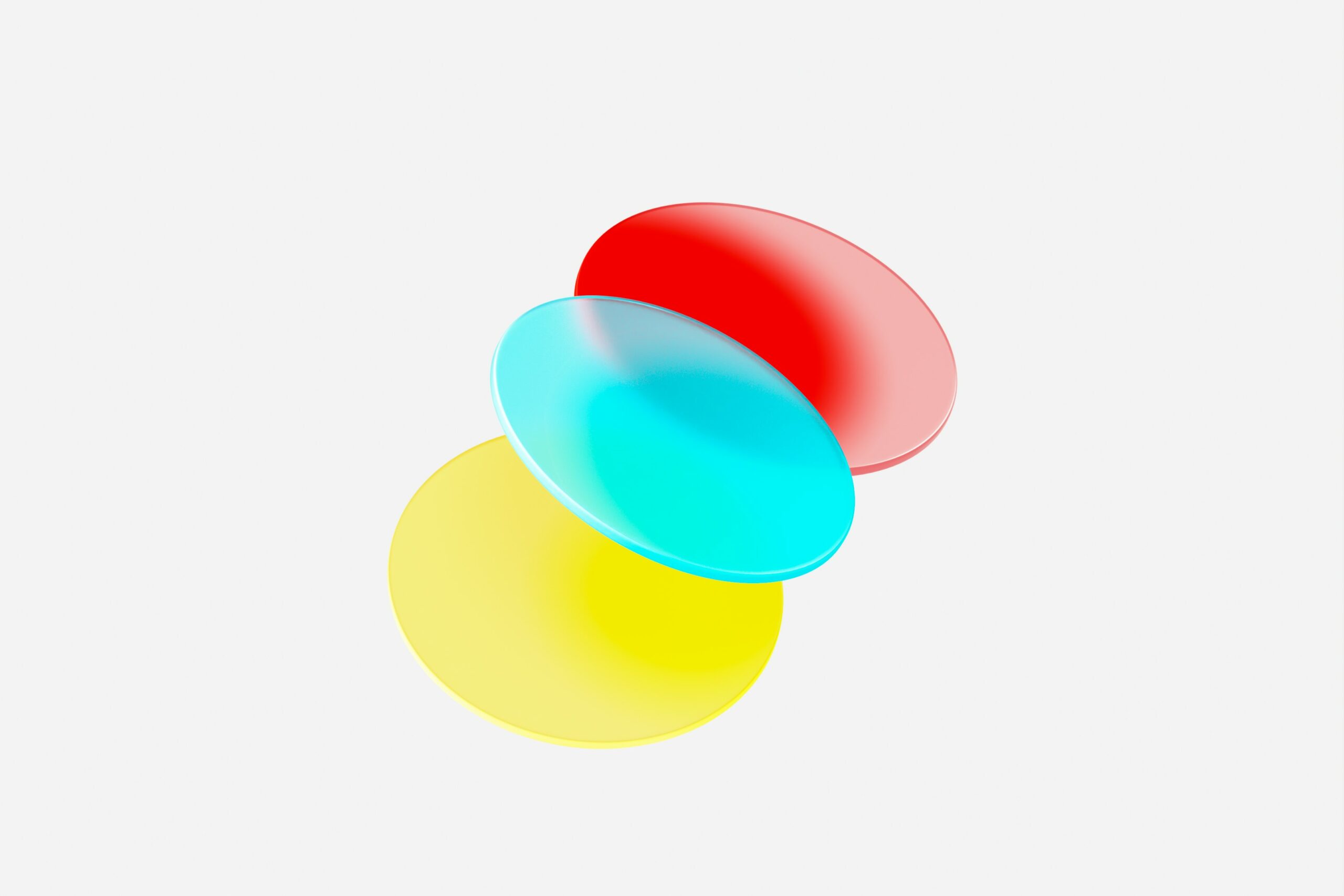
発達障害(神経発達障害)には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、発達性協調運動障害(DCD)、知的障害(ID)など様々な症状が含まれています。
発達障害と言えば、自閉症の○○の特性がある、ADHDの○○の特性があるため、○○さんには自閉症の理解と支援が必要、○○さんにはADHDの理解と支援が必要といったように、各診断(特性)に応じた理解と対応がとても重要になります。
一方で、様々な特性は互いに重なり合っているケースもあります。
重なり合うことで、状態像の理解は複雑化していくと言えます。
それでは、様々な発達障害の発症頻度はどの程度なのでしょうか?
そして、様々な発達障害の重複(併存)についてはどのように考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害の発症の頻度と重複(併存)について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参考にする資料は、「杉山登志郎(2018)子育てで一番大切なこと.講談社現代新書.」、「本田秀夫(2018)発達障害:生きづらさを抱える少数派の「種族」たち.SB新書.」、「アメリカ精神医学会 高橋三郎・大野裕(監訳)(2014)DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院.」です。
発達障害の発症の頻度について
以下、著書を引用しながら見ていきます(杉山,2018)。
知的障害:1%弱
自閉症スペクトラム障害:2%強
注意欠陥/多動性障害:3~5%
学習障害:5%
発達障害の発症の頻度を見ると、日本で早くから社会的認識が広まった知的障害(ID)や自閉症スペクトラム障害(ASD)よりも、注意欠如多動性障害(ADHD)や学習障害(LD)の頻度が高いことがわかります。
最近のADHDの当事者に関する情報が多く広がっている様子を見ても、こうした頻度は納得できると言えます。
また、上記の発達障害に加えて、最近では不器用さなど協調運動に関する発達障害として、発達性協調運動障害(DCD)が注目されるようになってきました。
発達性協調運動障害(DCD)の有病率は以下です(DSM-5より)。
発達性協調運動障害:5~6%
以上の発達障害(発達特性)は、大人になっても残存すると言われています。
発達障害の重複(併存)について
発達障害はDSM-5以降(2014年以降)に重複診断が可能になったこともあり、一人の人に複数の診断がついている状態も珍しくなくなってきました。
例えば、ASD+ADHD+SLDなどの3つの診断を持っている人もいます。
そして、一人の人が複数の特性を持っているケースが高いと述べている人もいます。
この点について、以下、著書を引用しながら見ていきます(本田,2018)。
私は、発達障害関連の問題で専門外来を訪れる人の多くは、重複例だと感じています。重複の程度は人によって異なりますが、ひとつの障害の特性だけが存在し、そのための診療だけで対応できるという例は、比較的少ない印象です。
著書にあるように、様々な障害が重複しているケースにおいて(重複の強弱は多様です)、特定の特性への理解と対応で支援が可能なケースは少ないと言えます。
それだけ、重複例において、様々な発達障害への理解と対応方法への知識が必要だと言えます。
それでは、次に、著者の療育経験から発達障害の重複(併存)についての体験談をお伝えします。
著者の体験談
放課後等デイサービスに通所している当時小学5年生のA君は、ASDの特性があると保護者の方から伺っていました。
A君は、一方的に自分の意見を話す、他者の意図の汲み取りが苦手、場面の空気などの理解が苦手なため、確かに自閉症的な特徴が見られていました。
一方で、A君にはこうした特性以上に、片付けができない、計画立てができない、衝動的に行動してしまうなど、どちらかと言えばADHDの特性の方が強く見られていました。
もちろん、場面や状況によって特性による困り感の出方は異なると思います。
ここでは、あくまでも著者が勤める放課後等デイサービスに限定して、ADHDと思われる特性が困り感として強く出ていたのだと言えます。
そのため、我々スタッフは、こうしたASDとADHDの両方の理解と支援を大切に関わっていきました。
重複(併存)に関する状態像を意識したことで、A君への理解は深まり、支援もうまく進んでいったように感じています。
A君のような事例は他にも複数存在していると思います。
一方で、療育現場に携わるスタッフにおいても、発達障害の重複(併存)の理解は少し乏しいように感じています。
そのため、今後はさらに発達障害の重複(併存)の理解が必須だと言えます。
以上、【発達障害の発症の頻度と重複(併存)について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
私自身もまだまだ未熟ですが、今後も発達障害への理解を深めていけるように学びと実践を継続していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
杉山登志郎(2018)子育てで一番大切なこと.講談社現代新書.
本田秀夫(2018)発達障害:生きづらさを抱える少数派の「種族」たち.SB新書.
アメリカ精神医学会 高橋三郎・大野裕(監訳)(2014)DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院.









