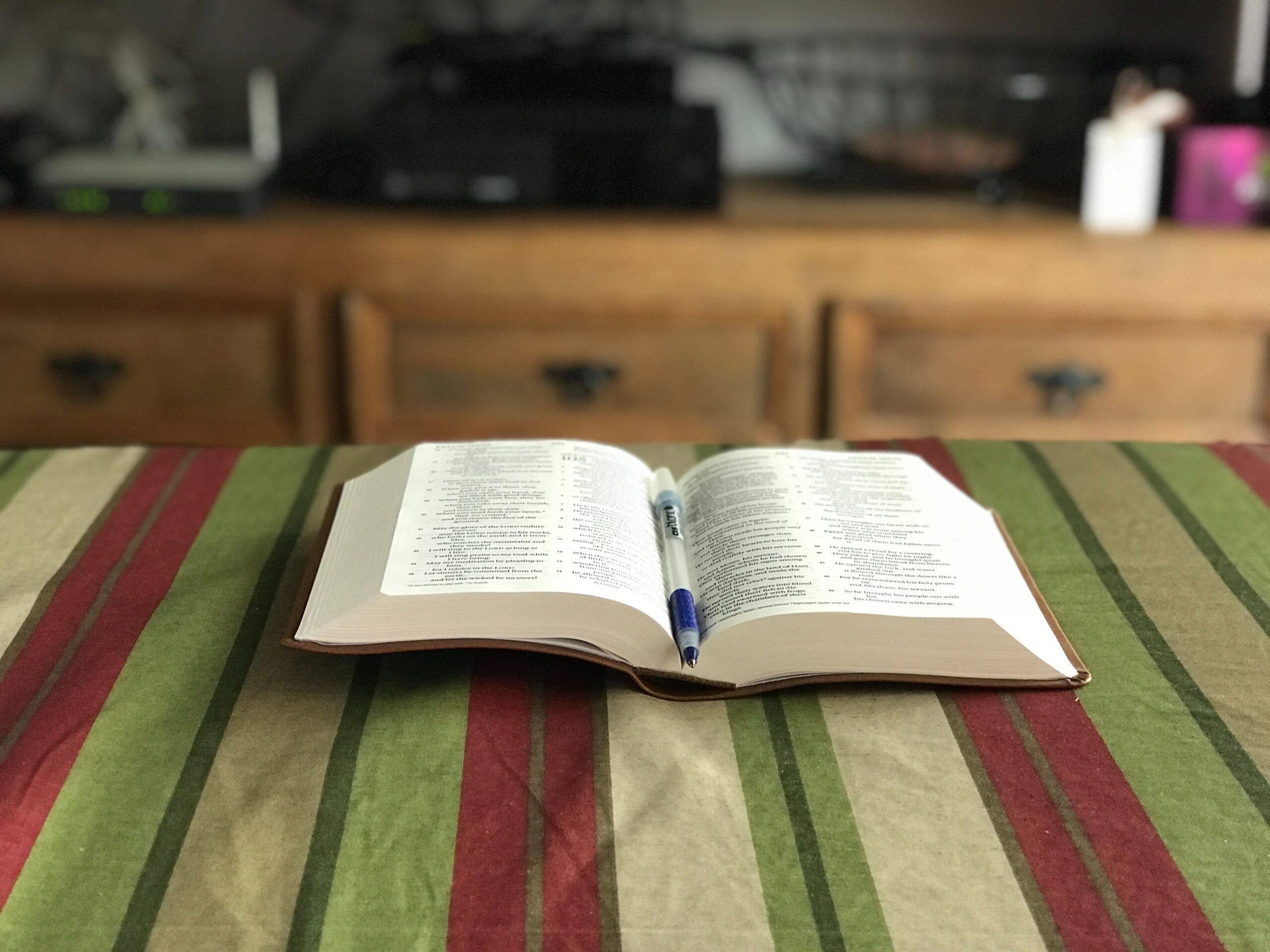
著者は現在に至るまで発達障害関連の仕事を多くしてきました。
その中で、発達障害の診断名が変わる人がいるということを時々耳にします。
しかし、発達障害とは、先天性の脳の機能障害であるため、生育歴を含め、現在の状態を的確にアセスメントしていくことで、概ね診断名はどの医師が行っても変わらないものだという認識があったため、診断名が変わるということに違和感がありました。
仮に、診断名が変わることがあるとして、それは、診断名を適切にくだすために必要な情報が取れなかったことが考えられます。
また、発達障害の診断基準などは時代に応じて変わり続ける所もあるため、時代の流れが影響している面も考えられます。
このように、診断名が変わる理由には様々な要因があるのかもしれませんが、何か納得のいく理由はあるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害の診断名がなぜ変わることがあるのかについて考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史・松久眞実・竹田契一(2022)特別支援教育 通常の学級で行う「愛着障害」サポート 発達や愛着の問題を抱えたこどもたちへの理解と支援.明治図書.」です。
発達障害の診断名はなぜ変わることがあるのか
著書の中では成長に伴い変化する診断についての例の記載があります(以下、著書引用)。
幼児期
多動、不注意
ADHD?
小学校低学年
読み書き苦手 LD?
小学校高学年・思春期
対人関係
ASD?
上記の引用が示すことは、ある一人の人物を例に、発達時期によってこれまでと違う診断名が浮上してきた例です。
幼児期に多動、不注意などが目立つとADHDの診断がつきやすいということです。
実際にこの時期に、ADHDの診断がつきやすいことが多いと言われています。
そして、小学校に上がると、学習面での躓きが顕著になりLDの診断がつきやすくなるということです。
学校の勉強の中心は、読み書き計算ですので、学習障害がある子どもはここで特定されやすいということです。
そして、小学校高学年以降になると、対人関係の問題が浮上し、ASDの診断がつきやすいということです。
小学校高学年頃になると、会話のレベルも高度になってくるため、自閉症の特性である相手の意図理解の苦手さなどが影響して会話がうまく成立しないということが出てくるということです。
さて、上記の人はどの診断名が妥当になるのでしょうか?
著書の中では、この人物はADHDもLDもASDも全て併存していた、ということになっています。
それでは、何故、このように時期によって診断名が変わるのでしょうか?
著書の中では、以下の回答をしてます(以下、著書引用)。
実はこどもの診断名が変わるのではないのです。成長の時期によって目立つものが違うのです。
つまり、本来3つの特性(ADHD、LD、ASD)を持っていても、それらの特性が問題として顕著になるのは、時期や環境からの影響を強く受けるからだということです。
それによって、障害の出方、つまり、診断名も変わってくるということになります。
逆に、もともと様々な発達特性を持っていても、その子がうまく環境に適応できていれば障害とはならないということです。
著者は今回参照した資料を見て、改めて、環境の大切さを実感しました。
つまり、障害は環境や社会が生み出している所も多くあるということです。
以上、発達障害の診断名はなぜ変わることがあるのかについて見てきました。
診断を受けることは、診断を受けた人が周囲から理解が得られ、必要な支援を受けることができるために行うものです。
そのために、大切なことは、問題となっていることをできるだけ正確に把握することと、その問題への予防と対応だと感じています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も一人ひとりの発達理解と発達支援に少しでも貢献していきたい思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「発達障害の強弱・重複(併存)について考える」
関連記事:「発達障害の重複(併存)について-療育経験から理解と支援について考える-」
米澤好史・松久眞実・竹田契一(2022)特別支援教育 通常の学級で行う「愛着障害」サポート 発達や愛着の問題を抱えたこどもたちへの理解と支援.明治図書.









