
発達障害には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動障害(ADHD)、学習障害(LD)、知的障害(ID)、発達性協調運動障害(DCD)などがあります。
発達障害への支援を考えた場合には、上記に見られる個々の発達特性への理解を踏まえた支援が非常に大切になります。
もちろん、こうした発達特性は、単独で発症している場合もあれば重複しているケースもあります。
それでは、発達障害の支援を考えた場合には、どのような対応策が知識として必要になるのでしょうか?
療育現場や特別支援教育の現場などで本当に役立つ知識にはどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、療育現場で発達障害の人たちとも関わりのある臨床発達心理士である著者が発達障害の支援に関するおすすめ本10選【初級~中級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、発達障害の支援に関する理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~10の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル
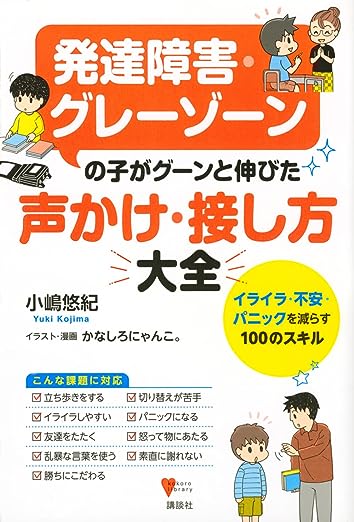
小学校教諭の〝小嶋悠紀さん″が書いた本になります。
そのため、学校現場での実践による知見が豊富に載っているため教育や福祉をはじめ、家庭で発達障害やグレーゾーンの子どもとの関わりにおいても役立つ本になっています。
内容としては、100のスキルの声かけ・接し方(支援)について、イラスト・漫画を加えながらとても分かりやすく解説されています。
教育・福祉・家庭などの環境において発達障害・グレーゾーンの子どもが見せる行動について困り感を抱えている教師・保育士・指導員、そして保護者の方にお勧めです。
2.小嶋悠紀の特別支援教育 究極の指導システム①
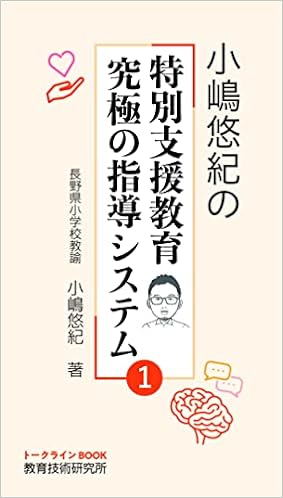
1で紹介した著者と同じく〝小嶋悠紀さん″が書いた特別支援教育の指導システムの前編となります。
内容としては、教師の心得、基本のスキル、指導のポイントから構成されており、教育を行う上で何を大切にしていけば良いのかを考えながら、実践方法について学ぶことのできる本となっています。
また、ASDやADHDなどの特性を踏まえた関わり方について、事例を交えての考察が様々な状況を通して説明されています。
特別支援教育を目指している方(特別支援教育の教員の方)をはじめ、発達障害児支援に関わる方にとってはとても参考になる本です。
3.小嶋悠紀の特別支援教育 究極の指導システム②
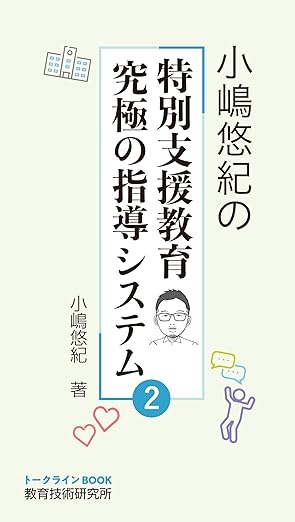
2で紹介した本の後編になります。
内容としては、子どもが荒れないためのスキル、学習困難場面での合理的配慮①②から構成されています。
そのため、学級内で問題となる(荒れる・学習困難)ことへの対応方法が主な内容となっています。
1と併せて読んで頂けると理解が深まる本であり、特別支援教育に携わっている方や発達障害児支援に関わっている方にお勧めです。
4.発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプローチ―叱らないけど譲らない支援
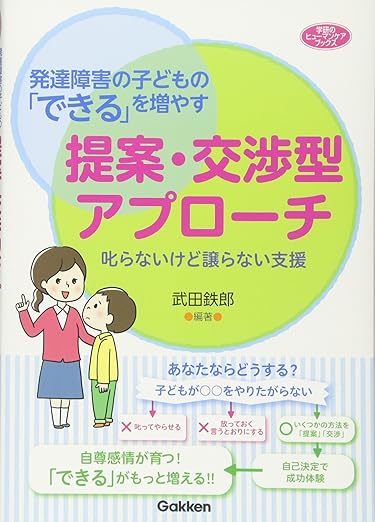
子どもの思いと大人の思いは食い違うことがよくあります。
〝子どもは○○したい″という思いがある中で、〝大人は○○して欲しい、○○がよい″といった食い違いは家庭や教育現場でよく見られます。
こうしたやり取りの中で行き詰まりを感じてしまうことは双方においてとても良くない状態になってしまうことがあります。
本書では、このような状態において大人(支援者・保護者)がどのように関われば良いのかを〝提案・交渉型アプローチ″とった〝叱らないが、譲らない″方法を通じて解説しています。
教育・福祉、家庭の中で、発達障害児との関わり方、特に折り合いの取りにくさに難しさを抱えている人たちにとってとても参考になる本です。
5.「うまくいかない」ことが「うまくいく」に変わる! 発達障害のある子どもがいきいきと輝く「かかわり方」と「工夫」
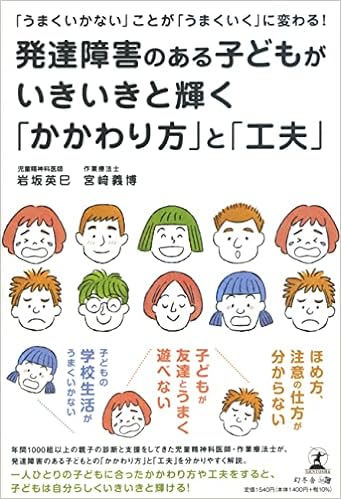
発達障害児の中には、様々な困り事が見られることがあります。
本書では、発達障害児が見せる様々な困り事について、どのようにすれば困り事を軽減し、結果、うまくいくに転換していけるのかが、特性理解の把握を踏まえて、関わり方の工夫・支援方法が豊富に載っています。
教育・福祉・家庭で発達障害児との関わりにうまくいかなさを感じている方にとって参考になる本です。
6.発達症のある子どもの支援入門 行動や対人関係が気になる幼児の保育・教育・療育
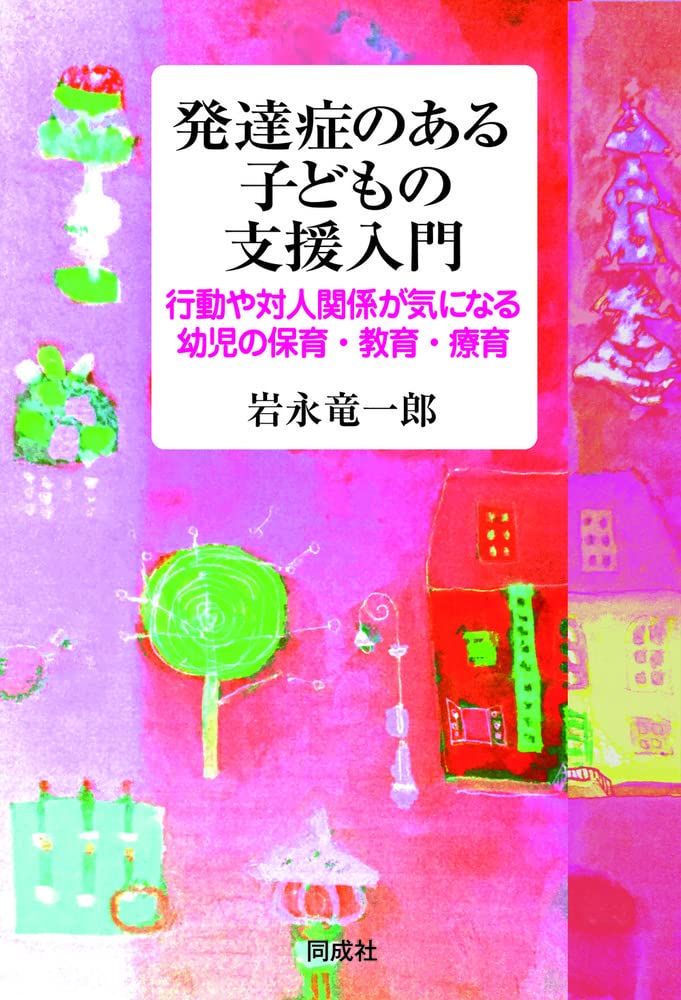
この本では、発達症の子どもへの様々な対応方法について、分かりやすく、かつ、豊富に記載されています。
年齢層としては、未就学児頃向けに書かれた内容ではありますが、学童期といったライフステージにも大変参考になる内容だと言えます。
特性が影響して生じる様々な困りごとに対して、その理解と対応で悩まれている保育者・療育者にとってとても参考になる本です。
7.がんばりすぎない!発達障害の子ども支援
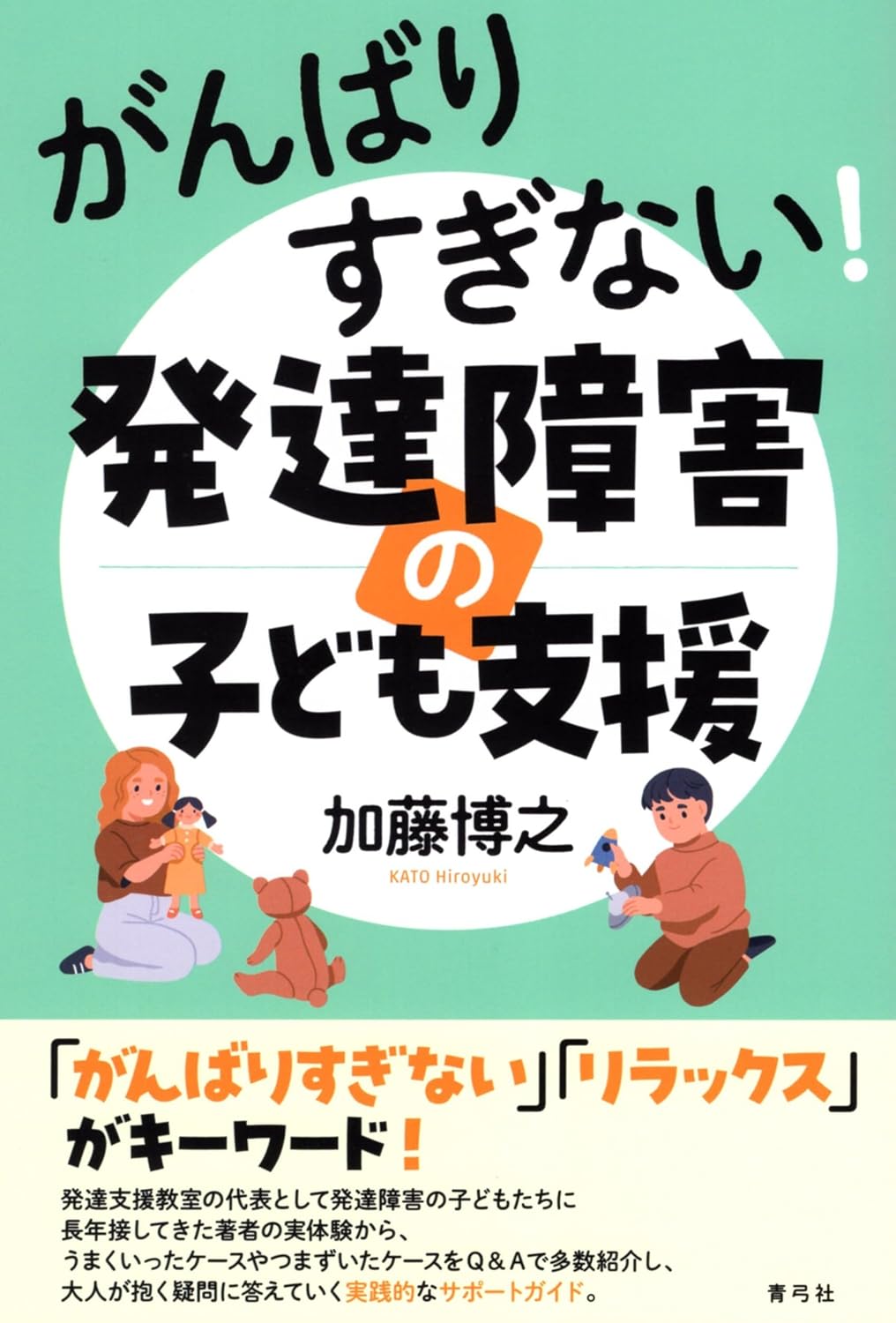
タイトルある通り、〝がんばりすぎない“〝リラックス“がキーワードとして書かれた実践書です。
発達障害に関する概要の説明に加えて、無理せずできる様々な支援方法が豊富に記載されています。
支援内容も非常に様々なケースにおいて対応できる情報が載っており、かつ、非常に実践的な内容になっています。
そのため、日々、発達障害児と向き合っている教育者・療育者にとって大変お勧めできる本です。
8.「できる」が増えて「自立心」がどんどんアップ! 発達障害&グレーゾーンの子への接し方・育て方
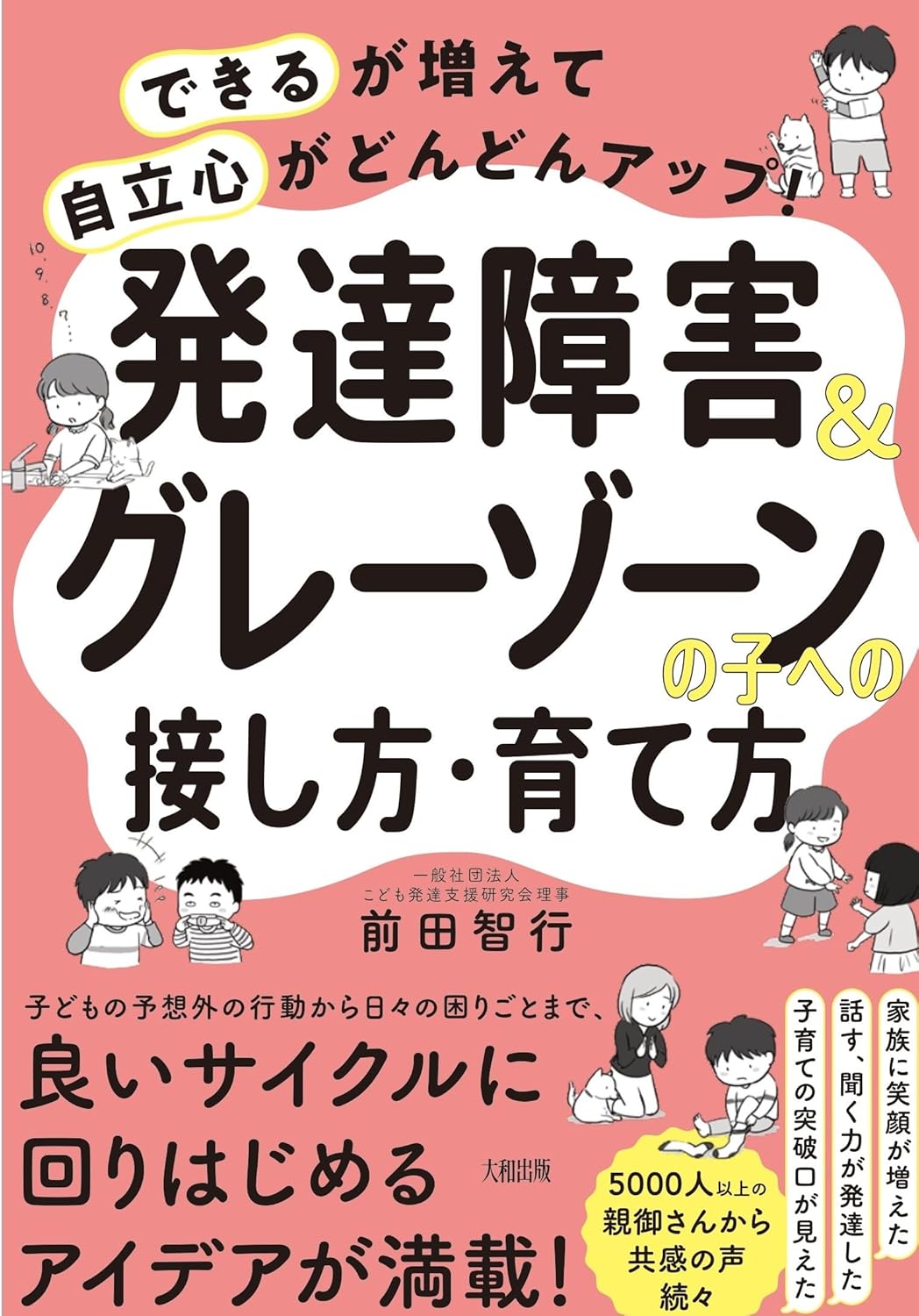
発達障害及びグレーゾーンの子どもへの様々な接し方が分かりやすく解説されています。
コミュニケーション・学習・感覚・運動・社会性など、対応に困りうる様々なテーマに対して、イラストなども交えながら説明されています。
発達障害及びグレーゾーンの子どもに関わる教育者・療育者・保護者の人たちにお勧めです。
9.発達が気になる子の教え方 THE BEST
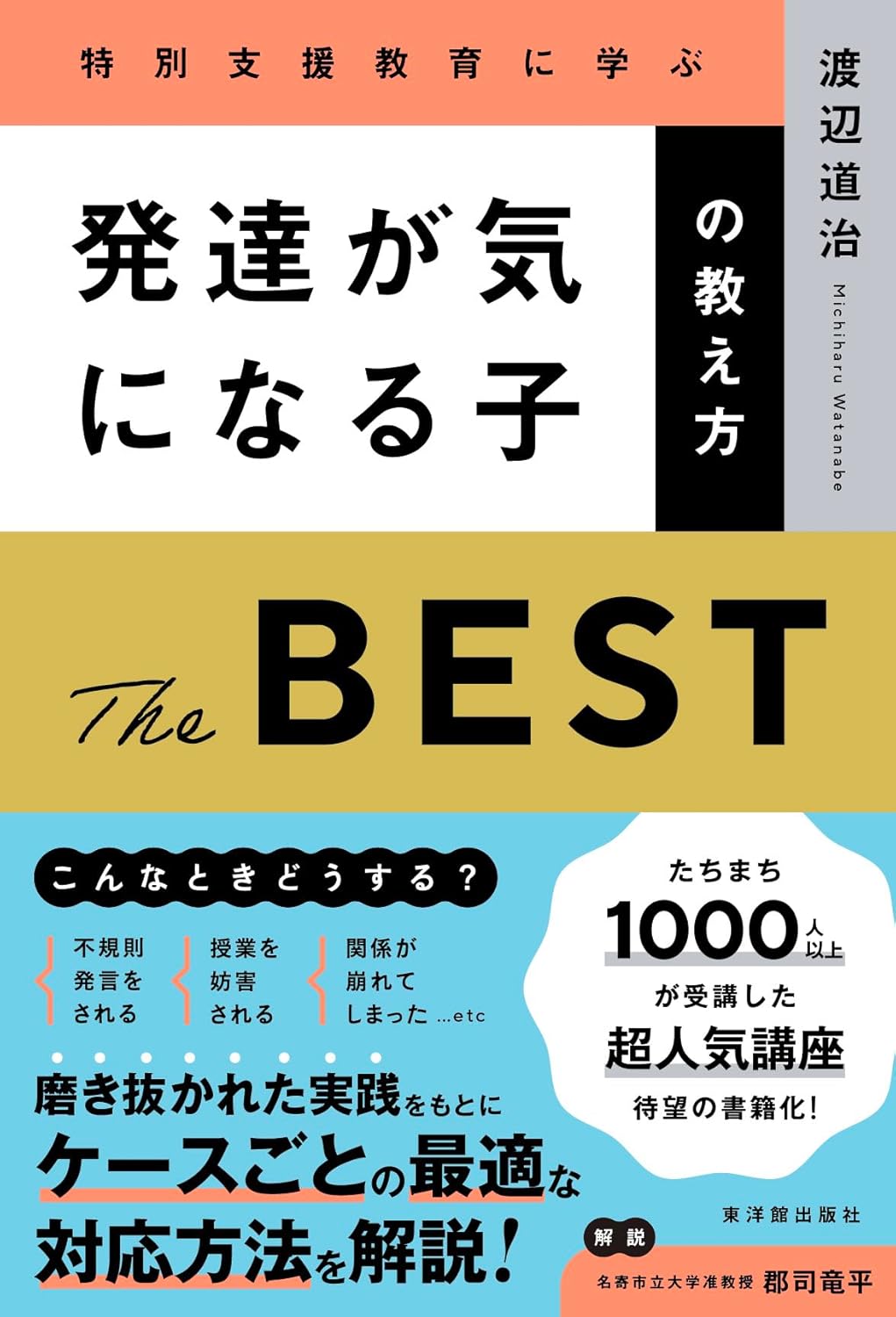
生徒との関係がうまくいかない、暴力・暴言が絶えない、癇癪が多いなど、子どもが見せる様々な〝問題行動“に対する対応のヒントが豊富に記載されています。
〝問題行動“には、行動の背景となる理由があること、そして、それに応じた対応方法について分かりやすく説明されています。
発達が気になる子どもとの関わりで困っている教師をはじめ、療育関係者などにもぜひお勧めできる本です。
10.学校が楽しくなる!発達が気になる子へのソ-シャルスキルの教え方
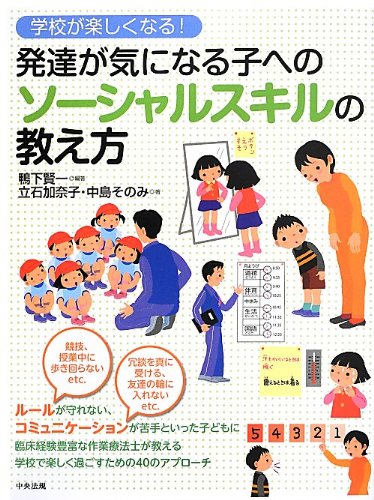
発達が気になる子どもに対して、生活上の様々な困り事についての対応方法が具体的に説明されている本です。
様々な困り事で躓いている事に関して、4つの原因とそれに対する対応方法(1.自分をコントロールする力が弱い、2.自尊心が育っていない、3.感覚面の偏り、4.相手の気持ちを読み取りにくい)から解説されています。
教育現場や療育現場に携わっている教員・支援者をはじめ、発達に躓きを抱えている子どもを持つ保護者の人たちにもお勧めできる本だと言えます。
発達障害の概要について理解を深めたい人にお勧め記事は以下です。
関連記事:「発達障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「発達障害に関するおすすめ本【中級~上級編】」










