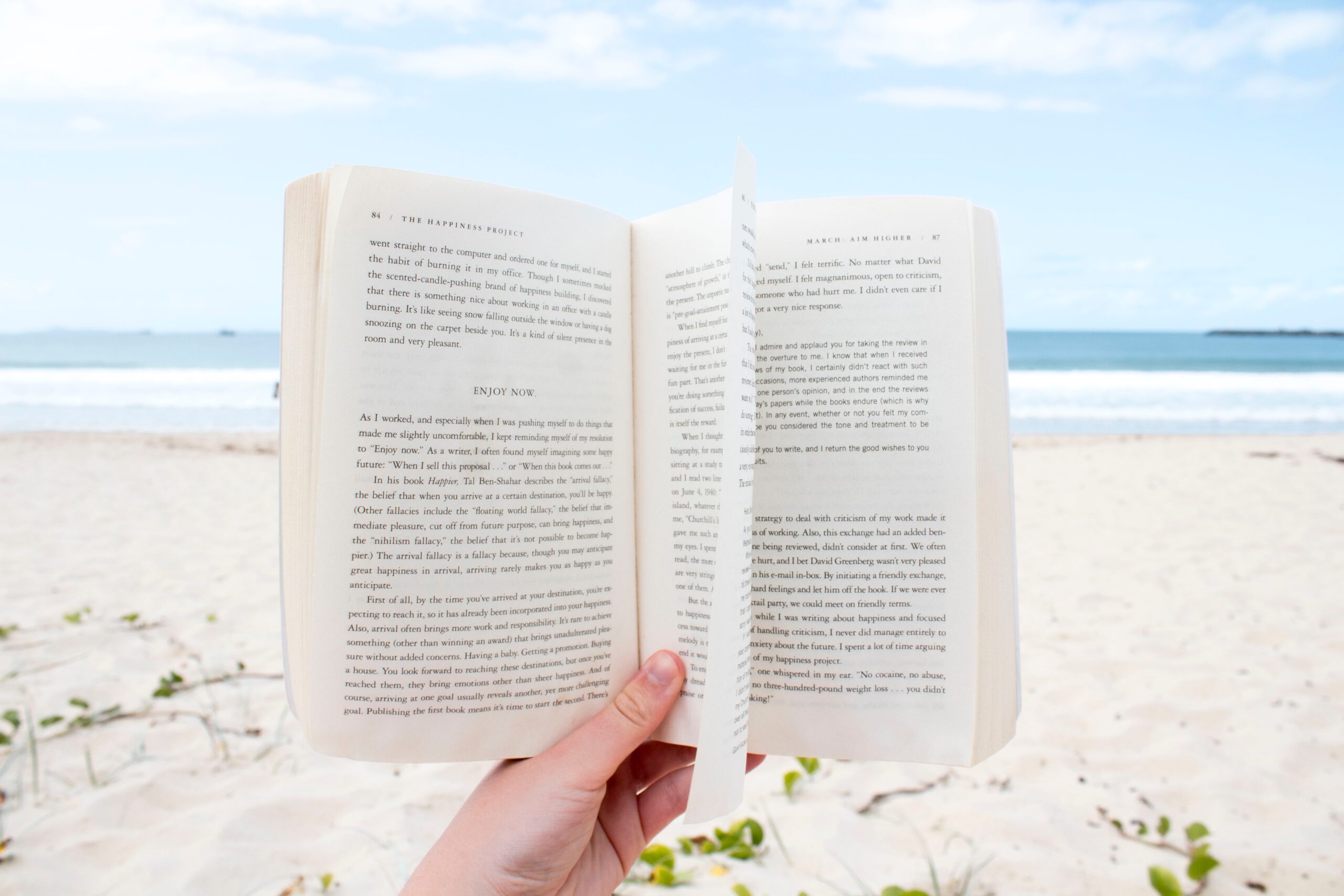
療育(発達支援)において〝遊び″のもつ重要性はとても大きいです。
子どもたちは〝遊び″によって身体機能、社会性、創造性などを高めていくことができます。
それでは、遊びをより深く理解する上でどのような知識が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、療育(発達支援)に役立つ遊びを理解する上で非常に参考になるおすすめ本6選【初級~中級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、療育(発達支援)に役立つ遊びに関する理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~6の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.遊びが学びに欠かせないわけ―自立した学び手を育てる
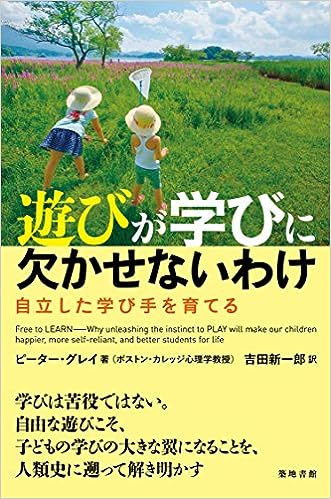
子どもの遊びの進化学で世界的に権威のある〝ピーター・グレイ″著の訳本になります。
この本を通して、人が学び自立していくためには〝遊び″が非常に重要な意味を持っているということが理解できます。
自由遊びの意味とは?異年齢集団で人は何を学ぶのか?遊び心は人のどうような育ちに貢献するのか?遊びの種類や内容にはどのようなものがあるのか?子どもが危ない遊びをすることの意味とは?など、様々な問いへのヒントを与えてくれます。
閉塞感のある日本の教育を見直す上でもとても参考になる本です。
療育現場に関わる人だけでなく、教育や保育、保護者の方々など人を育てるといった立場にある人たちすべてにお勧めできる本です。
2.集団遊びの発達心理学
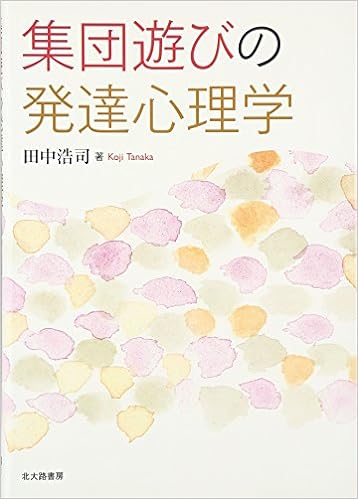
子どもたちは〝集合遊び″を通して成長・発達すると言われています。
この本では、集団遊びの現状や集団遊びに関する様々な実践例、集団遊びの文献研究などを通して、集団遊びの意味について理解を深めていくことができます。
集団遊びにも様々なタイプや発達段階があるということを考えていくことで、療育や保育現場で子どもたちと関わるスタッフにとって子どもたちの成長・発達を捉える目が養われていきます。
〝集団遊び″に関する理論と実践の両方をバランスよく学びたい方にとってお勧めできる本です。
3.障がいのある子との遊びサポートブック―達人の技から学ぶ楽しいコミュニケーション
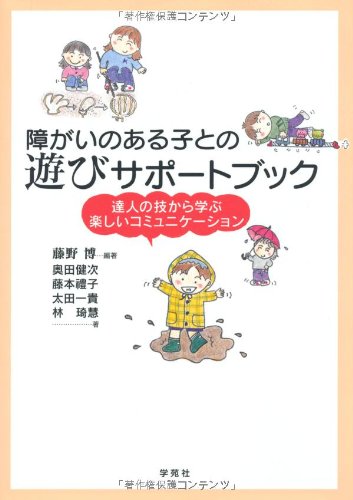
障がいのある子どもの遊びを考え発展させることは難しい場合が多くあります。
この本では、発達に遅れのある子どもたちへのコミュニケーションや言葉の力を育てていくための具体的な方法が記載されています。
子どもとうまく遊べないと悩まれている保護者の方、療育や保育に携わる方にとって関わり方のヒント、楽しく遊ぶためのヒントが豊富に載っています。
そのため、障がいのある子どもたちと実際の現場で関わっている方すべてにお勧めできる本です。
4.ひとりで、できた!
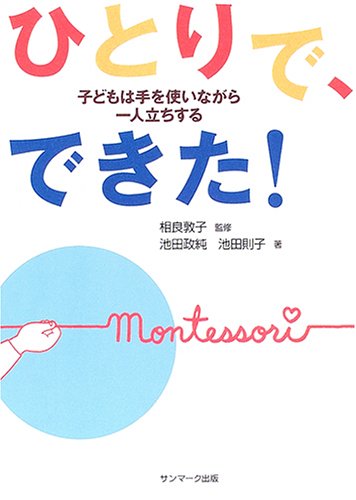
モンテッソーリ教育の理論と実践が詰まった本になります。
子どもたちは、自分の手を使い・特定の動作を繰り返すことで、一人立ちしていくと言われています。
幼い頃に自分の身体(五感)を通して様々な学習をしていくことが後の成長・発達においてとても大切です。
この本では、様々な動作に対応した保育教材のヒントが写真やイラストも豊富に交えながら解説されています。
そのため、療育や保育で子どもたちと関わるスタッフにはとてもお勧めできる本です。
5.子どもの心の世界がみえる 太田ステージを通した発達支援の展開
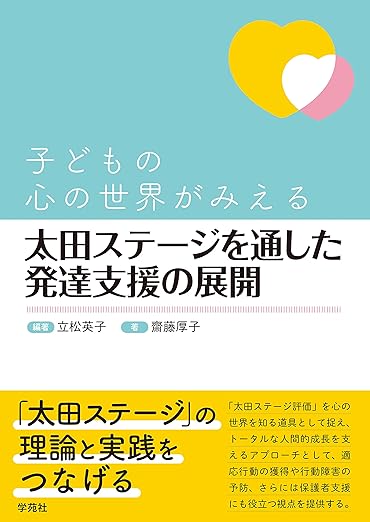
療育現場などで障害の程度の重たい方と接していると、その人たちの内面世界をどのように理解し支援していけば良いのか迷う方も多くいると思います。
この本では、〝太田ステージ″による発達支援の理論と実践が豊富に載っています。
太田ステージを通して、障害のある方の発達段階(認知的側面)を理解し、具体的な支援の方法を見つけていくヒントを得ることができます。
福祉・心理・教育の領域で障がいのある人たちと関わっている方すべてにお勧めできる本です。
6.おもちゃ教材で育む人間関係と自閉スペクトラム症の療育: 親・保育園・幼稚園・学校・児童発達支援・放課後等デイサービスのためのガイド
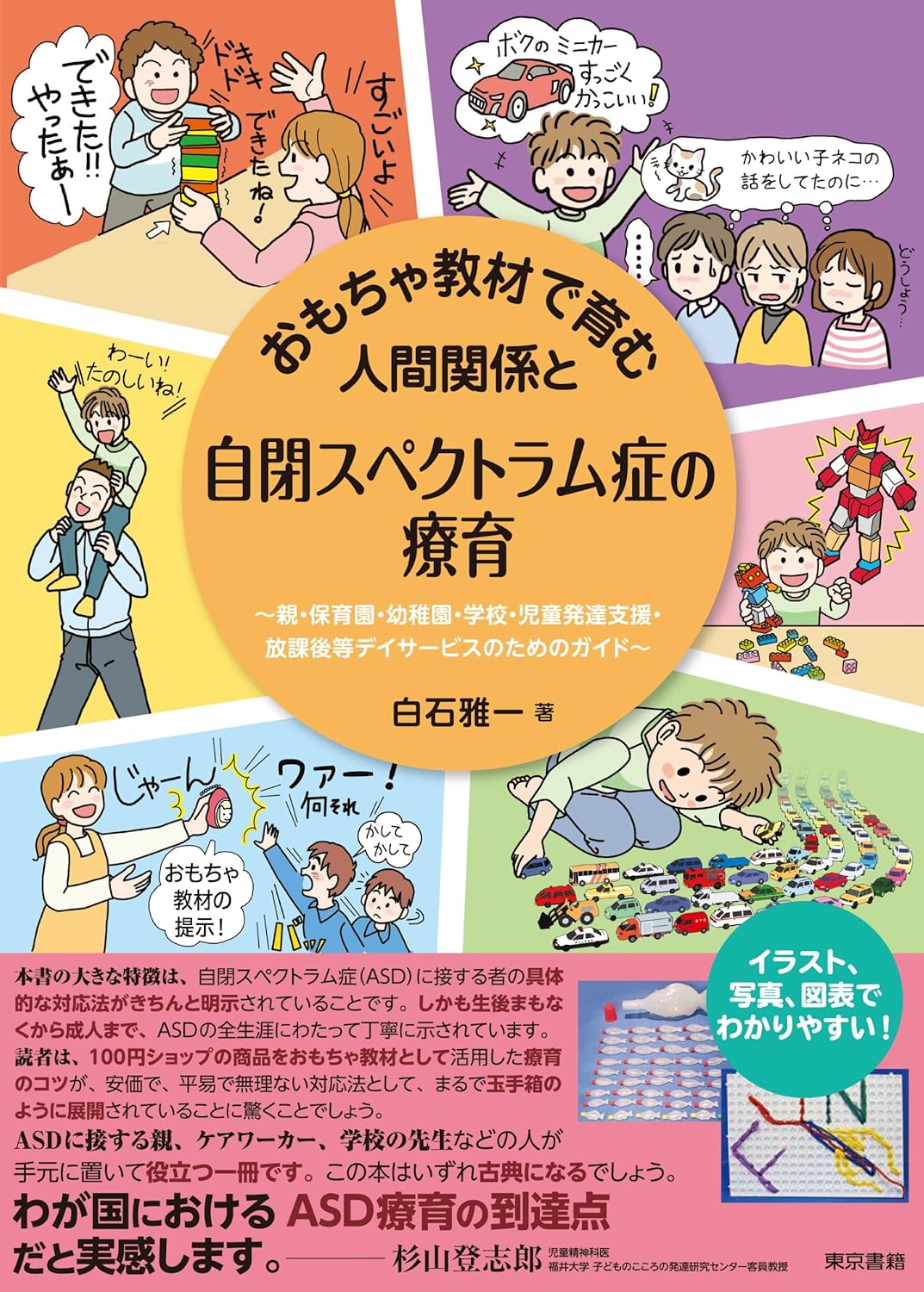
自閉症(ASD)療育に詳しい〝白石雅一″さん著の非常にオリジナリティの高い本となっています。
対人意識の弱い自閉症児に対して、〝おもちゃ教材”を活用した人間関係を育むアプローチ方法が豊富に記載されています。
様々な〝おもちゃ教材″の考案・活用方法など非常に実践向きに書かれています。
その他、自閉症児によく見られる〝こだわり行動″〝パニック”への理解・対応方法なども分かりやすく解説されています。
福祉・心理・教育の領域で自閉症児に携わる人をはじめ、当事者家族にもお勧めできる本です。
関連記事:「療育(発達支援)に関するおすすめ本【初級編~中級編】」










