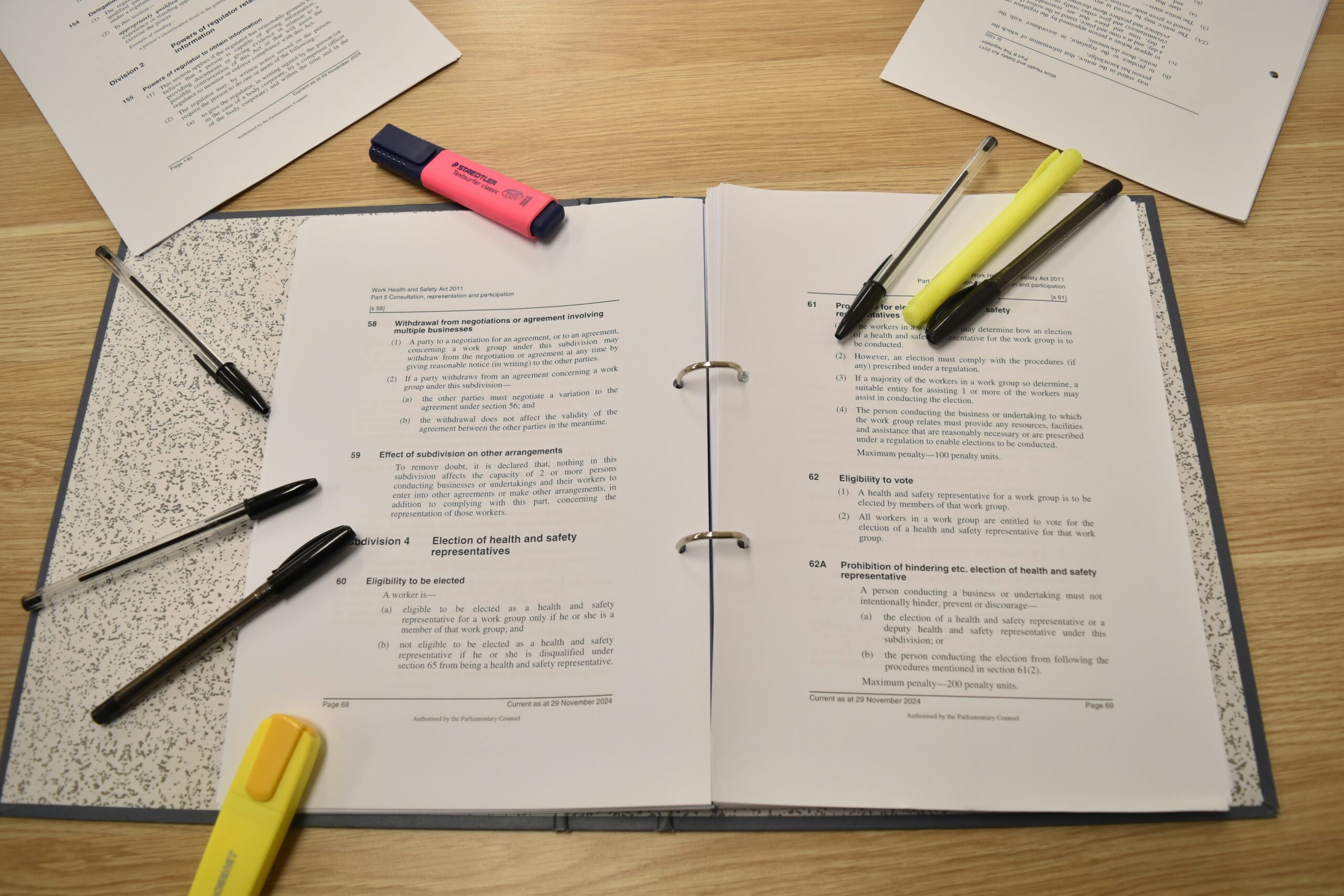
著者は長年、発達に躓きのある子どもたちに療育(発達支援)をしています。
現場経験を通して、子どもたち一人ひとりの個性や発達はとても多様であることを実感しています。
著者は療育現場での経験と並行して研究にも携わる機会がこれまでありました。
そのため現場経験と研究を通して、現場に活用できる研究方法などはないか?と考えることも多くありました。
そこで、今回は療育現場における実践研究の活用方法について、「実践的還元」をキーワードにお伝えしていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「シリーズ支援のための発達心理学:実践研究の理論と方法」です。
実践研究とは何か?
実践研究とは、例えば、Aさんの課題を、アセスメントを通して整理し、解決したい特定の行動に対して、ある一定期間介入を行い、その効果を時系列で分析(行動の変化を数値化)するものなどが例としてあります。
この場合、特定のAさんへの介入とその効果の検証ですので、一般化の問題が生じます。
つまり、他の人への活用は有効であるか?ということです。
著者は、昔、心理学統計などある集団からデータを収集し、統計的に有意であるのかを仮説検証する研究方法を学んでいたため、特定の一人(あるいは数人)を対象に研究するということが科学的に有効であることを立証することは困難であると考えていました。
もちろん科学が万能であるわけではありませんが、最近はエビデンスがとても重視されるようになっているため、支援においても根拠がより重要になってきています。
一方、著者は長年の療育現場での経験から、支援する子どもたち一人ひとりの状態像は非常に多様であるため、個別のニーズや支援方法なども多様であることは経験則から間違いないと実感するようになりました。
こうした、研究と現場での経験に対して、さらにもう一歩前進するヒントが得られた視点が「実践的還元」というものです。
それでは、次に「実践的還元」についてお伝えしていきます。
実践的還元とは何か?
以下、著書を引用します。
実践研究は、一般化と無縁なわけではない。個々の研究から得られた知見をまとめ、類型化することによって一般化可能性が高まるという。このような観点は、「実践的還元」と呼ばれる。すなわち、実践研究の結果、確かめられた仮説や理論を再び実践の場に適用し、その妥当性を検討すると同時に、実践の積み重ねから人の変化に影響を及ぼす要因の整理を行うということである。
著書の内容では、実践研究で得られた知見を他の事例に活用し、その効果を検討するというプロセスを重ねることで、一般化可能性を高めていくという視点を「実践的還元」と呼ぶとしています。
つまり、研究協力者一人の実践研究でも、同じような事例に活用・応用していくことで、その人数を増やしていくことで、一般化が高まっていくという考え方です。
著書のコメント
こうした「実践的還元」の視点は、療育現場で非常に多様な子どもたちと関わっていると納得のいくものだと思います。
多様な子どもたちではあっても、例えば、困りなど特定の内容には共通性が見られることがあります。
その際に、過去の実践を振り返り、再度、活用できないかを考えることは現場にいる方は自然と行っているものだと思います。
もちろん、こうした内容は事例検討というもので、実践研究とは異なりますので、研究として扱う場合には、データを収集し、過去の研究知見も踏まえて整理していく必要があります。
それでも、一人の事例・実践から多くを学ぶこと、その事例・実践から他の人に活用・応用するという視点には共通性があると思います。
母集団から統計的に有意であるかという統計学的な視点も大切ですが、現場経験を通して得られる一人ひとりの困り感やニーズなどを踏まえて支援し、その効果を検討すること、そして、その支援方法を再度他の事例に活用するという視点もまた人間の多様な理解と支援方法に繋がっていくものだと思います。
私自身、まだまだ未熟ですが、今後も経験と知識から多くの学びを獲得していく中で、より良い発達理解・発達支援を目指していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
本郷一夫(編)シリーズ支援のための発達心理学:実践研究の理論と方法.金子書房.




