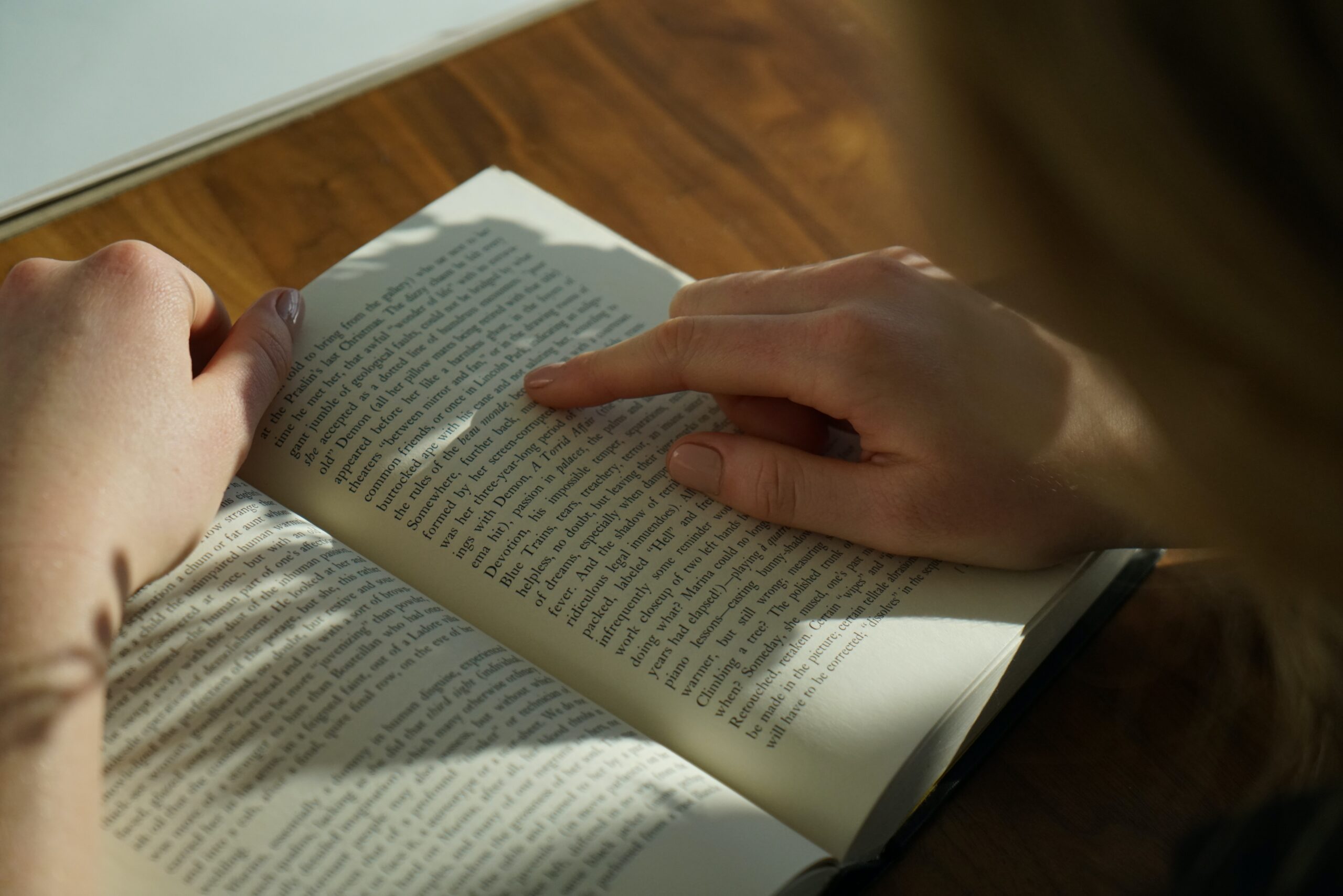
人は外の世界から感覚器官を通して様々な情報を取り込んでいますが、その中で、様々な情報をまとめ上げていきながら外の世界に適応していきます。
〝感覚統合″とは、脳に入力された様々な感覚情報(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚固有覚、平衡感覚など)を目的に応じて整理して秩序だったものへと構成することとされています。
〝感覚統合″の理論・知識は、発達障害のある人たちへの理解や支援において必要不可欠なほど大切なものです。
それでは、感覚統合をより深く理解する上でどのような知識が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、感覚統合を理解する上で非常に参考になるおすすめ本3選【中級~上級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、感覚統合の理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~3の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.感覚統合とその実践
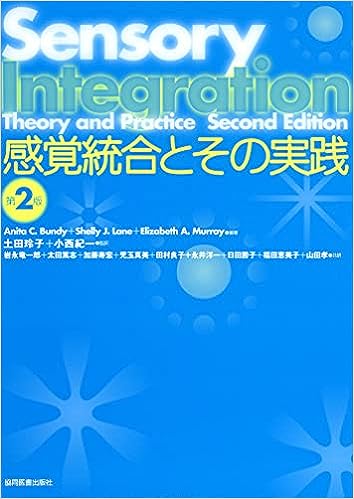
感覚統合に関する知識を網羅的に学ぶことができる書籍になっています。
内容としては、第1部:理論構成、第2部:評価と介入、第3部:研究と作業から構成されています。
中でも、評価ツールとして小学生を対象とした調査票が付録に記載されていることが他の感覚統合の本には珍しい点かと思います。
感覚に関する評価ツールになると、SP感覚プロファイルシリーズが有名ですが、本書にある評価ツールもまた感覚統合に関する知識と発達に関する知識を有することで非常に実用可能なものとなっています。
海外の方が書いた翻訳本となりますが、訳としては分かりやすく抵抗なく読めるものかと思います。
分量が500ページを超えるものであるため、感覚統合に関する専門的な知識を学びたい方、作業療法士など感覚統合の知識が必須の専門家などにお勧めです。
2.アスペルガー症候群と感覚敏感性への対処法
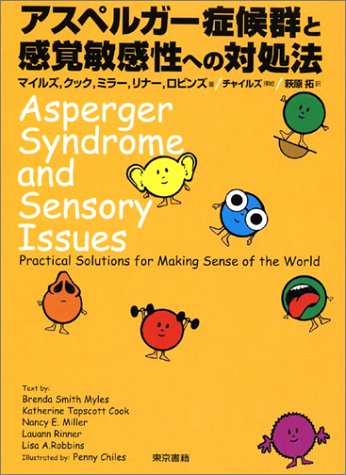
海外の方が書いた翻訳本になります。
この本では、アスペルガー症候群や高機能自閉症(現在は自閉スペクトラム症に統一された)の人たちの感覚に関する問題を取り上げ、その評価と指導方法が多くの事例を対象に分かりやすく記載されています。
感覚に関する評価ツールも著書の中で取り上げられているため(1で紹介した書籍同様に珍しいです)、どのような視点に評価の軸を持っていけば良いかのかが理解できるかと思います。
分量としては、150ページ程度のものであり、内容に関しても分かりやすい説明となっています。
そのため、自閉症の感覚の問題について理解したいと考えている方(もちろん、感覚統合に関する基本的な説明もあります)にはお勧めです。
3.子どもの発達と感覚統合
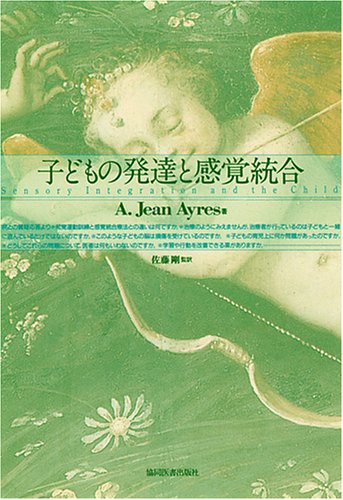
この書籍は、感覚統合理論を構築した〝A.ジーン エアーズ″によって書かれたものです。
彼女が生み出した感覚統合理論は障害児教育の世界において実践(感覚統合療法として)されるようになりました。
そんな彼女が書いた本は、感覚統合理論を学ぶ上での必読書だといっても過言ではありません。
今回紹介する書籍は、1982年出版(日本において)の本ですが、エアーズ博士の感覚統合理論の概要と実践(対処方法)を学ぶことができます。
感覚統合について深く理解したいと考えている方、大学で感覚統合に関する研究をしている方などにお勧めです。
関連記事:「感覚統合に関するおすすめ本【初級~中級編】」









