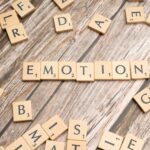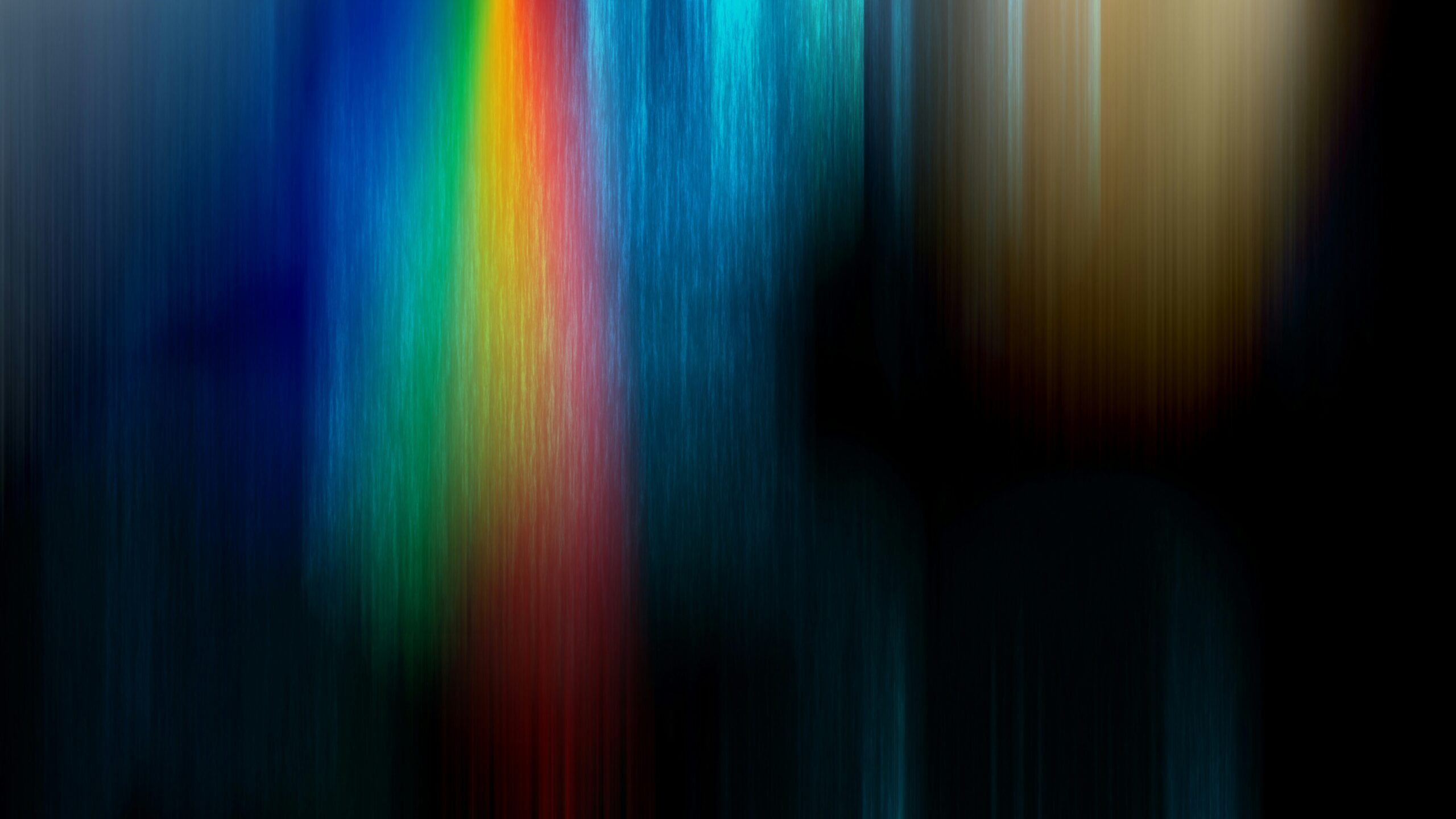
愛着障害には様々なタイプあると言われています。
DSM-5など医学的な診断定義では、「脱抑制タイプ」(脱抑制対人交流障害)、「抑制タイプ」(反応性愛着障害)の2つが記載されています。
一方、臨床発達心理士の米澤好史さんは、この2つに「ASDと愛着障害併存タイプ」を加え、3つのタイプがあるとしています。
関連記事:「【愛着障害の3つのタイプ】脱抑制タイプ・抑制タイプ・ASDと愛着障害併存タイプ」
3つ目のタイプにある、「ASDと愛着障害併存タイプ」ですが、著者もこのタイプは長年の療育経験から存在すると実感しています。
ASDは、自閉症スペクトラム障害のことですが、スペクトラムとは連続体のことです。
つまり、自閉的な特徴はどこかで区切るものではなく、濃淡(グラデーション)があり、その特徴は誰にでも存在するという考え方です。
それでは、愛着障害については、スペクトラム障害という見方はできるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害をスペクトラム障害とする見方に加えて、愛着障害への支援を重視することの意義について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら考えていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「米澤好史(2019)愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか?アセスメントと具体的支援のポイント51.福村出版.」です。
愛着障害をスペクトラム障害とする見方と愛着障害への支援を重視することの意義
以下、著書を引用しながら見ていきます。
愛着障害については、残念ながら、1か0かではなく、程度の差であるスペクトラム障害であるとは、まだ認定されていません。(中略)愛着障害をスペクトラム障害と捉えると(中略)それぞれの特性の程度の強さのかけ算の答え([自閉の強さの程度]×[愛着の問題の強さの程度])と等しいという法則を見つけることができます。
著書の内容では、現段階において、愛着障害をスペクトラム障害とする見方は認定されてはいませんが、臨床経験から第三の「ASDと愛着障害併存タイプ」には、それぞれの特性のスペクトラムの掛け算により状態像が変化するという法則があるとしています。
著書の米澤好史さんは、多くの臨床研究から、愛着障害をスペクトラム障害とする見方が妥当であると考えています。
そして、第3のタイプへの支援において、以下のように述べています(以下、著書引用)。
自閉と愛着の問題を併せ持つタイプとして意識し、まず、愛着の問題からアプローチすれば、必ず、劇的に愛着修復ができ、行動の問題が減少・改善することを、たくさんの実践例から確かめてきた。
著書の内容から、自閉と愛着の問題が併存しているタイプについては、介入すべき優先順位はまずは愛着の方にあるとしています。愛着からのアプローチをとることで劇的に問題行動が減少すると述べています。
こうした点から、自閉的な特徴に加えて、愛着の問題もあるケースにおいて、愛着からのアプローチを重視することに大きな意義があるのだと言えます。
それでは、次に以上を踏まえて著者の意見も述べていきたいと思います。
著者のコメント
著者がこれまで見てきた子どもたち中には、ASD(自閉症スペクトラム障害)の子も多くおります。
その中で、特に関係構築が難しいタイプに、ASD+愛着障害(愛着に問題を抱える)のタイプがあります。
こうした重複したタイプの子に対して、仮に、愛着障害の理解がなければ、ASDからの理解と支援に重きを置くことになります。
しかし、前述した米澤好史さんも述べていたように、介入の優先順位は愛着障害→ASDの順であるので、ASDのみの理解と支援での効果はそれほど期待できません。
著者も非常に関係構築が難しい子どものケースには、その背景に愛着の問題の理解を想定した介入が重要だと考えています。
まずは、特定のキーパーソンを決め、その人物との情緒的交流が進むことで、ASDの特徴も問題行動としてではなく、特性としてむしろその子の個性として、関わりの中で残っていくという印象があります。
そのため、関わりにくさの背景要因をしっかりと把握していく必要があります。
それが、ASD単独のものか、ASD+愛着障害(愛着に問題を抱える)かで理解と支援方法も変わってくるからです。
さらに、愛情障害の程度もスペクトラムであるといった視点についても著者も同意します。
愛着障害の程度も濃淡があり、フラッシュバック的に爆発したり、解離が見られるなどの重いケースから、大人への信頼が薄いといったケースまで多様であると感じます。
様々な発達障害をスペクトラムだとする見方が強まっている中で、愛着障害についても同じくスペクトラム(スペクトラム障害)とする見方をとる方が、現場の感覚からすると子どもたちの状態像の正確な理解に繋がるのではないかと思います。
以上、愛着障害をスペクトラム障害とする見方と愛着障害への支援を重視することの意義について述べてきました。
私自身、愛着障害に対する理解はまだまだ不足していると感じる中で、これからも日々の現場経験から子どもたちの実態に可能な限り迫る理解と支援を実施していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2019)愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか?アセスメントと具体的支援のポイント51.福村出版.