
療育現場には、自傷や他害、パニックや激しいこだわりなどが見られる子どもたちがいます。
こうした行動特徴は、‟(強度)行動障害”とも言われています。
‟(強度)行動障害”についての理解が不足してしまうと、問題となる行動の背景を分析して対応することよりも、目の前の行動を止めることに終始してしまう状態が発生する場合があります。
そのため、‟(強度)行動障害”について、正しい知識を獲得していく中で、できる対応を考えていくことが大切です。
関連記事:「行動障害と強度行動障害の違いについて-行動障害の背景にあるものとは?-」
それでは、そもそも強度行動障害とは一体どのように定義されているのでしょうか?
そこで、今回は、強度行動障害とは何かについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、関わり方で大切な視点について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「小林隆児(2001)自閉症と行動障害:関係障害臨床からの接近.岩崎学術出版社.」です。
強度行動障害とは何か?:強度行動障害の定義について
以下、著書を引用します。
行動障害児(者)研究会は、「強度行動障害」を以下のように定義している。
「強度行動障害児(者)とは、直接的他害(噛みつき、頭つき等)や、間接的他害(睡眠の乱れ、同一性の保持、場所・プログラム・人への拘り、多動、うなり、飛び出し、器物破損等)や自傷行為などが、通常考えられない頻度の形式で出現し、その養育環境では著しく処遇の困難な者をいい、行動的に定義される群である。その中には医学的には、自閉症児(者)、精神薄弱児(者)、精神病児(者)等が含まれるものの、必ずしも医学により定義される群ではない。主として、本人に対する総合的な療育の必要性を背景として成立した概念である」。
行動障害児(者)研究会の定義から、‟強度行動障害”について見てみると、直接的・間接的他害や自傷など様々なものがあり、その頻度が非常に高いこと、養育環境での対応が難しく、療育の必要性を背景として成立した概念とされています。
それでは、次に‟(強度)行動障害”の観点から、著者の療育経験を通して関わり方で大切な視点についてお伝えします。
著者の経験談:関わり方で大切な視点
著者はこれまで行動障害とまではいかなくとも、その手前にいると想定される子どもたちと関わってきました。
その中で、大切な視点は予防だと感じています。
以下、いくつか事例を見ていきましょう。
①Aさんの事例:うまくいかないことがあると他害や自傷を見せる子ども
Aさんは、自分が使いたい物を他児が使っていたり、他児が急に寄ってくると他児に物を投げたり叩くなどの他害、思い通りにいかないとドアに頭をぶつけたりするといった自傷が見られる子どもでした。。
当時の著者はこうしたAさんの行動に対して止める働きが多くを占めていました。
しかし、関わりを継続していく中で、Aさんが他害や自傷を見せる場面が、ある程度特定できるようになってきました。
そのため、最初に取り組んだ内容として、他害や自傷を起こさないような環境設定を考えるといったものでした。
例えば、他児との間には必ず大人が入る、Aさんが好む活動をしっかりと把握し、まずはその活動ができる状況を作るなど、一見簡単そうには見えますが、その他の子どもも見ながら対応することは容易ではありませんでした。
しかし、関わるスタッフがこうした予防的な視点で環境調整することにより、他害や自傷は非常に減り、逆にスタッフに他害や自傷以外の方法、例えば、言葉を通してお願いしてくる姿が増えていきました。
Aさんの事例を振り返って見ても、他害や自傷といった行動がどのような場面や文脈で生じるのかを把握し、それを防止するといった未然の策を講じていくことはとても大切だと思います。
②Bさんの事例:感覚遊びに没頭しすぎてしまい生活に支障が出ている子ども
Bさんは、水遊びに没頭する特徴のある子どもでした。
そのため、来所して直ぐに台所の水道に直行し、水をたくさん出してその感覚に浸ることが多く見られていました。
非常に水といった特定の感覚に没頭しているので、途中で中断したり、事前に終わりを伝えても、癇癪やパニックを起こします。そのため、当初は大泣きする毎日だったように思います。
Bさんに対して取り組んだ内容として、水遊び以外にも楽しめる活動を探し取り入れていくというものでした。
例えば、ペットボトルに水を入れその中に光る紙を入れたおもちゃの作成、トランポリンや毛布ブランコなどの感覚遊びを少しずつ実践していきました。
継続した取り組みにより、Bさんは、水遊びをある程度行うと次の活動に注意を向けるなど、特定の感覚刺激以外にも興味を持つようになりました。
また、関わる大人にスキンシップを求めてくるなど、人に対しても関心を向ける様子が増えていきました。
Bさんの事例を振り返って見ても、特定の感覚刺激に没頭するといった強いこだわりに対して、他に楽しめる活動を作っていくこと、また、その中で大人との関係性を作っていくことは、長い取り組みにはなりますが、予防の視点からは大切なことだと思います。
以上、強度行動障害とは何か?療育経験を通して関わり方で大切な視点について考えるについて見てきました。
(強度)行動障害への理解と対応はとても根気のいる取り組みであり、また、多くのスタッフとの連携も必要不可欠だと思います。
そして、(強度)行動障害もその背景となる発達段階や発達特性など個々の状態像に応じて、理解や取り組み内容も変わってくると言えます。
大切なことは予防の視点です。
つまり、行動の背景をつかむこと、その行動を起こさないように未然に環境調整をすることが大事になってきます。
私自身、まだまだ未熟ですが、今後も行動障害について理解を深め、二次障害を予防していけるように、日々の療育での実践を大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
行動障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「行動障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
小林隆児(2001)自閉症と行動障害:関係障害臨床からの接近.岩崎学術出版社.

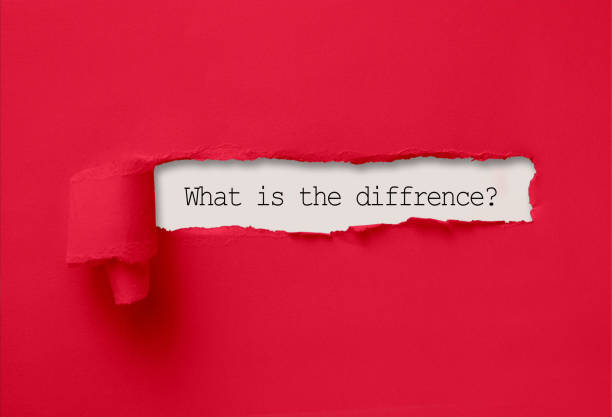
コメント