知的障害や発達障害とよく似た言葉として〝境界知能″があります。
〝境界知能“は、知的障害や発達障害と比べると、まだまだ社会的な理解が乏しい現状があります。
それでは、境界知能とは一体どのような人たちのことを指すのでしょうか?
そこで、今回は、境界知能とは何かについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、知的障害との違いも踏まえて理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「宮口幸治(著)佐々木昭后(作画)(2020)マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち.扶桑社.」です。
知的障害について
〝知的障害(ID)″とは、知的水準が全体的な発達よりも低く、かつ、社会適応上問題がある状態のことを言います。
IQ(知能指数)の数値で言えば、69以下のゾーンを指します。
最近では、IQ(知能指数)だけではなく、社会適応能力の面が重視されるようになってきています。
知的障害は、全人口の約2%(クラスに約1人)だとされています。
関連記事:「【知的障害児の〝知的機能″の遅れとは何か?】療育経験を通して考える」
関連記事:「【知的障害児の〝適応機能″とは何か?】療育経験を通して考える」
境界知能について
「境界知能」とは、IQが70~84のゾーンを指し、これは人口全体の14%(クラスに約5人)いる計算になります(71~85と記載されている文献もあります)。
IQで見ると、平均値よりも下回るも、知的障害の知能指数の数値よりは上のゾーンにいる人たちになります。
そのため、行動特徴として、学習面や運動面、社会性の面など、多くの面で遅れが見られることがあります。
一方で、「境界知能」は、知的障害や発達障害と比べてなかなか気づかれることは少なく、支援の対象になりにくい傾向にあります。
さらに、発達上の遅れが顕著でないため、本人の努力不足などとして捉えられてしまうこともあります。
著者の体験談
境界知能:Aさんの事例
Aさんは、子どもの頃にはかった知能指数が境界知能のゾーンでした。
全体的に発達が遅れている印象がありましたが、時間をかければ学習に追いつく、少しのサポートがあれば集団行動についていけるといった印象がありました。
一方で、周囲の理解(推測)と本人の状態像は、実際のところ大きく解離していました。
Aさん本人は「なぜ、自分は他人とは違うのか?」「なぜ、自分は勉強や運動がうまくできないのか?」「なぜ、周りの人が話していることがよく理解できていないにもかかわらず、理解できているように受け取られてしまうのか?」など、これらはAさんの後々の語りをもとに、困り感の一部を取り上げたものになります。
当時は、自分の思いや遅れなどを言語化することが難しかったため、漠然とした不安の中にいたのだと言えます。
そのため、Aさんの上記の困り感は、年齢が進むにつれて、自己理解が進み、後々になってから、自分の状態像を言葉によって客観視できるうようになってから聞き取ったものになります。
著者がこうした境界知能の大人の方(子どもも含め)と関わることが、これまで少なからずありましたが(そうだと想定されるケースを含めて)、一言でいうと、わかりにくさが特徴としてあったように思います。
そして、本人にとって何が一番大変なのかというと、周囲から理解されず、ただ漠然とした努力を求められていることだと思います。
それは、一見すると周囲とうまくやれているように見えてしまうことで、周囲からの理解が得ずらいのではないかと考えられます。
もう少し頑張れば学習についていける、運動についていけるなど、周囲から見て少しの差といった印象もあるかもしれませんが、長期的にみると周囲に追いつくように過度な努力を強いられることは、本人の自尊心の低下や、二次障害にも繋がりかねないと言えます。
今後は、境界知能についてさらに理解が進むことで、発達障害との関連性なども踏まえて、より総合的に人を理解していくことが求められていく必要があると思います。
私自身、療育現場を通して、子どもから大人を見据えて、境界知能や発達障害など様々な人への理解を深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
知的障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「知的障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
宮口幸治(著)佐々木昭后(作画)(2020)マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち.扶桑社.
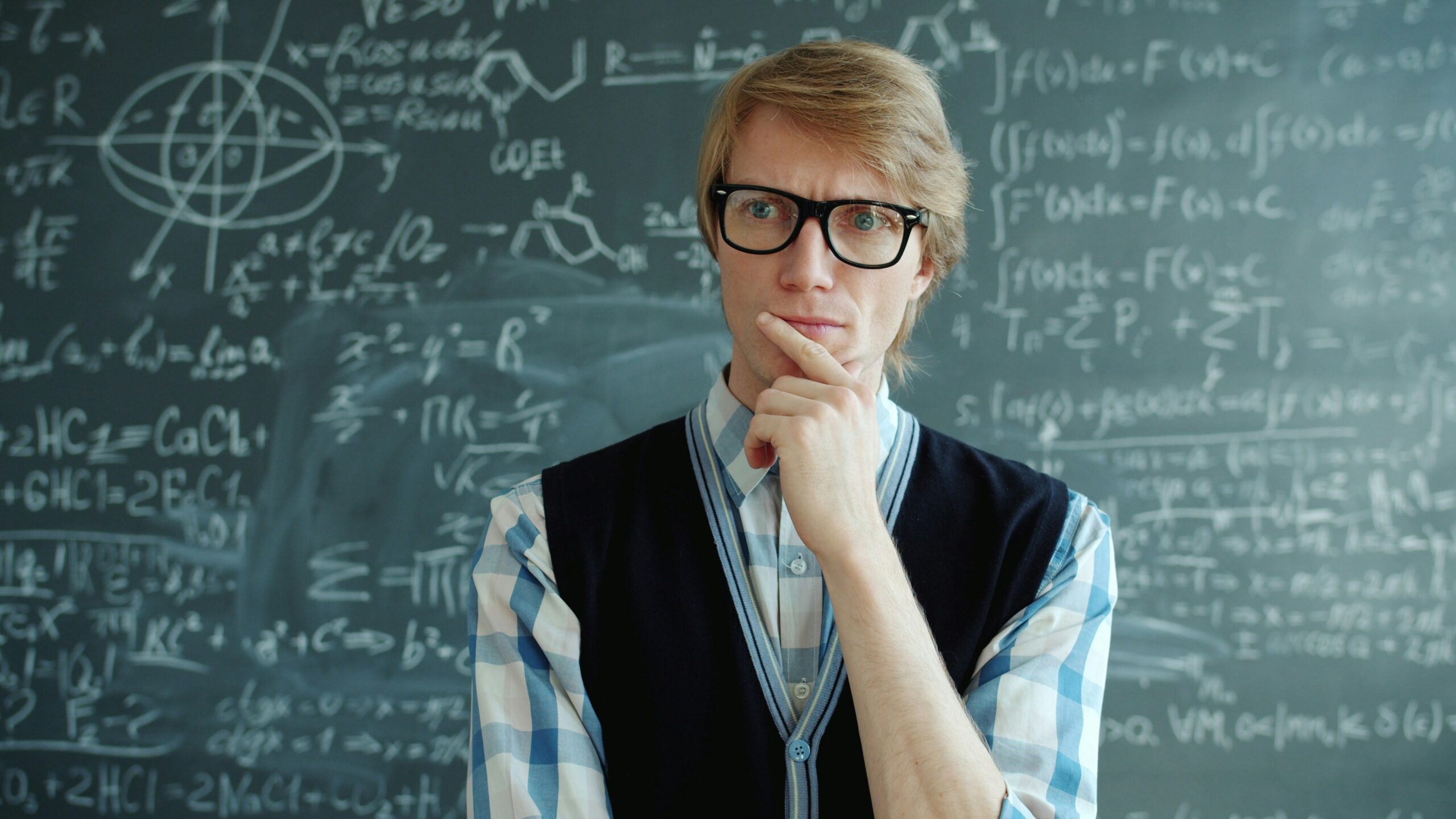


コメント