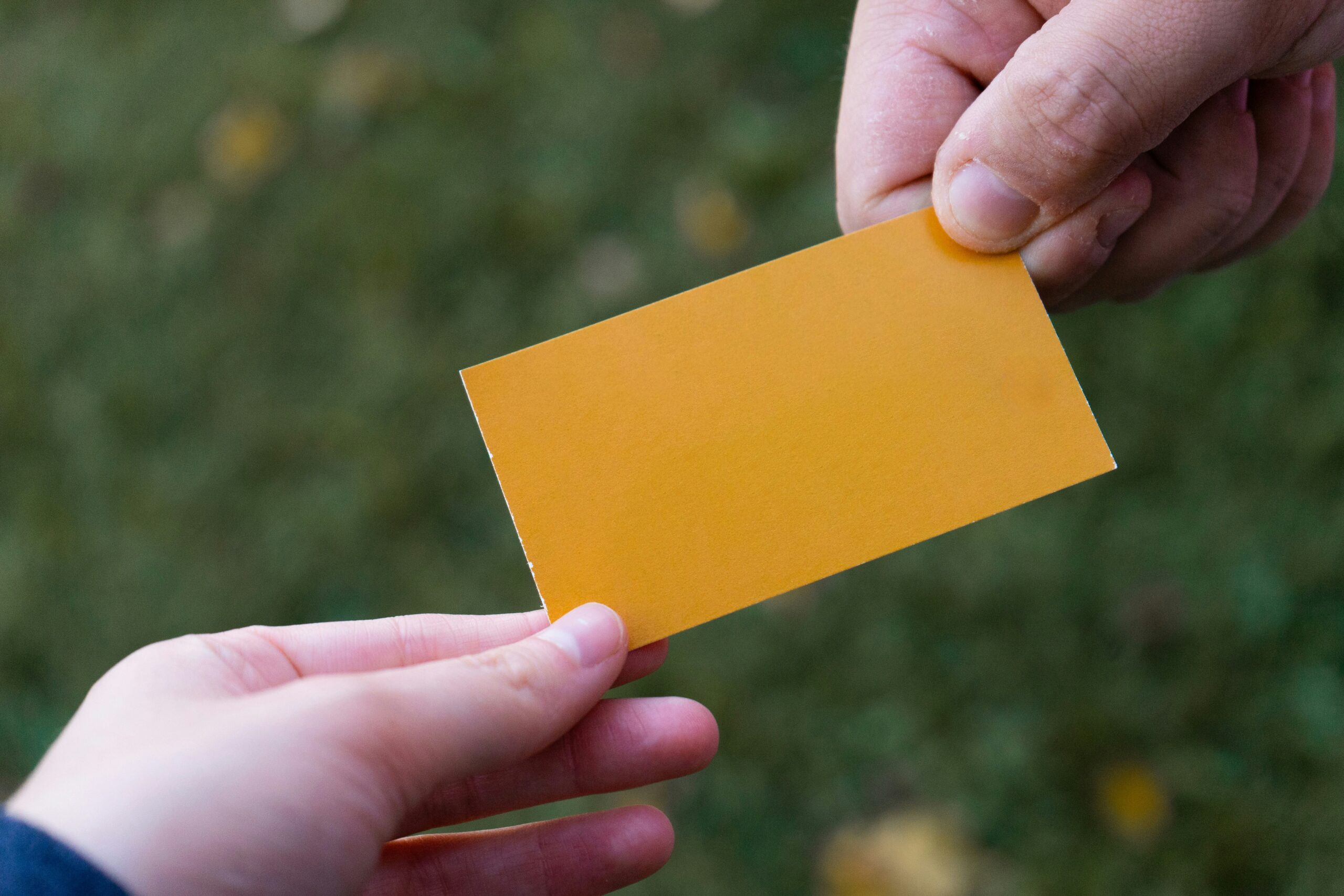
療育現場では様々な子どもたちと心の交流があります。
例えば、遊びを通して楽しかったという経験やうまくできなかったという経験などを共有することです。
こうした心の交流とはある意味、ことば文化を共有することでもあります。
それでは、こうしたことば文化を共有するとは一体どのようなことなのでしょうか?
今回は、著者の療育経験を通して、分かち合いコミュニケーションをキーワードに考えていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「小林隆児(2001)自閉症と行動障害:関係障害臨床からの接近.岩崎学術出版社.」です。
分かち合いコミュニケーション(ことば文化の共有)について
以下、著書を引用します。
養育者は子どもの心の動き(内的世界)に参入して(合わせて)、その世界を共有するようにまずは努めることである。このような関わりは子どもに合わせていくという受動性を要求されるが、それとともに子どもの世界に主体的に合わせて積極的にそれを分かち合うという能動的な営みでもある。
著書の内容から、分かち合いコミュニケーションとは、一方の気持ちを受容しながらも、また一方が能動的に主体的に気持ちを出すというように、相互の気持ちの能動と受動が交差する状態ということが言えるかと思います。
これは例えば、養育者が子どもの気持ちを受動的態度で受け止めながら、養育者もまた自分の能動性を出しながら、ことば文化を伝え共有していくことでもあります。
もう少し、かみ砕いて言うと、大人は子どもの気持ちを感じ取りながら、大人の文化・言葉を子どもに伝えていきながら、お互いの気持ちやことば(文化)を共有していくということです。
それでは次に、著者の療育経験から、分かち合いコミュニケーションについて考えていきたいと思います。
著者の経験談
著者は療育現場で様々な子どもたちと長い期間の関わりの中でことば文化を共有してきたという実感があります。
当時、小学生のAさんの事例をここでは取り上げたいと思います。
当時のAさんは自分の気持ちをうまく伝えることができずによくイライラすることがありました。
その頃の私はAさんのイライラした感情を受動的態度で受け止めてきました。まずは、イライラしている気持ちを一緒に感じるということです。
そして、Aさんがイライラした理由を言葉で伝えて(推測ですが)いきました。
もちろん、Aさんのイライラの意味は状況によって理由が異なるので常にその状況を把握しながら推測することが大切になります。
また、その時、「○○すればいいよ」、「○○してほしかったのかな?」など、私は気持ちを落ち着ける言葉がけをしたり、どうして欲しかったのかも聞きながら、少しずつ私(大人)も能動的に関わることが増えていきました。
こうしたやり取りを日々繰り返すことで、Aさんは私のことばを理解する様子が増えたり、自分の気持ちをことばに置き換えてうまく伝える様子が増えていきました。
こうしたやり取りは、成長に伴い、関係性の発達に伴い、少しずつ変化していったと思いますが、重要なことは、お互いの気持ちを受け止める働きと、お互いの気持ちを出す働きが常に交差しながら、ことば文化が深まっていくということです。
特に、発達初期の子どもは大人と様々な体験を共有しながら、その体験にことばがかぶさることで大人文化を理解していきます。
現にAさんも、私がAさんの気持ちを言い当てたり、イライラした時の気持ちの対処方法などを提案していく中で、それらを自分の中に取り込む様子が増えていきました。
逆に、私もAさんとの関わりを通して、Aさんが様々なことで悩んでいること、喜んでいることなどを一緒に分かち合う体験を通して、Aさんの気持ちを少しずつ理解できるようになったと思います。
このように、分かち合いコミュニケーション(ことば文化の共有)は、大人と子どもが分かち合えたという体験を通して、様々な気持ちや思いを理解していくことであるかと思います。
Aさんのような事例は療育現場で多くの子どもたちを関わっていると、様々な場面で出会うことができます。
こうした貴重な経験を時間軸で見ると、子どもの成長には大人との様々な体験を共有することがとても大切なのだと思います。
私自身、まだまだ未熟ですが、こらからも子どもたちとの関わりを通して、喜怒哀楽様々な感情を分かち合えたという体験を重ねていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
小林隆児(2001)自閉症と行動障害:関係障害臨床からの接近.岩崎学術出版社.




