ワーキングメモリとは、作動記憶とも呼ばれ、聞いた情報を一時的に記憶に保持し、その情報を操作する力なります。
著者は、療育現場で発達に躓きのある子どもたちと関わっていますが、その中には、ワーキングメモリに苦手さがある子どもたちが多くいます。
ワーキングメモリに苦手さがあると、ついさっき言った内容を直ぐに忘れてしまう、ルールや約束事を忘れてしまう、学校の勉強での躓きが多く見られるなどの支障が出てきます。
ワーキングメモリと関連性が深いものに学習障害があります。
学習障害の多くはワーキングメモリに苦手さがあると言われています。
関連記事:「知能検査から見たワーキングメモリについて【学習障害との関連性】」
それではワーキングメモリを鍛えることはできないのでしょうか?
また、鍛えられるとすれば、どのような方法があるのでしょうか?
そこで、今回は、ワーキングメモリを鍛え方について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「岡田尊司(2022)発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法.SB新書.」です。
ワーキングメモリを鍛えるためには?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
一つは暗唱訓練だ。文章を読んで、それをそのまま覚えて暗唱する。その場合、一語一句正確に言うことにこだわる必要はない。内容がきちんと把握され、すべての項目が表現できていたらよしとする。
むしろ、要約するといったことのほうが有用だ。ワーキングメモリは、覚えたものを操作し活用するときに活発に使われるからだ。
さらに難易度が上がるが、より効果的なのがシャドーイングと呼ばれるもので、聞きとりながら、同時に声を出して繰り返す方法だ。
著書の内容から、ワーキングメモリを鍛える方法には様々ありますが、例えば、1.暗唱訓練や2.シャドーイングなどがあります。
以下それぞれについて見ていきます。
暗唱訓練について
暗唱訓練で大切なことは、一つひとつを正確に復唱するというよりも、おおよその内容を把握することです。
例えば、文章を読んで概要としてまとめる、要約するなどがあります。
要約するためには、ある程度、頭の中に話の内容を記憶として保持し操作する力を必要とします。
要約する内容は、できるだけ本人が興味関心のあるものの方が、効果があると思います。
理解したい・知りたいという動機のもと、自分から自発的に話をまとめようとする力が徐々に育まれることが期待できるからです。
そして、要約する動機には、その対象への興味関心以外にも、話の内容を伝えたい相手がいることも大切です。
伝えたい思いがあることで(人がいることで)、話の内容をまとめ・保持(圧縮して)しようと思うからです。
著者は興味のある本を自分なりにまとめることがありますが、興味関心が強いと自発的にまとめようとする動機が高まり、そして、その内容を伝えたい相手がいるとさらに覚えよう(まとめよう)とする動機が高まります。
また、療育現場においても、子どもたちは自分が興味のあるものを必死に自分なりに頭の中で整理しようとする場面があります。
例えば、学校で借りてきた興味のある本の内容を必死に自分なりに著者に伝えようと要約しようとする姿からそのように感じます。
こうした行為は、目で見た情報(読んだ内容)→まとめながら声に出して伝える(あるいは文章で表現)という意味で、ワーキングメモリ(視覚による)を鍛えるトレーニングに繋がっているように思います。
シャドーイングについて
その他、ワーキングメモリを鍛える方法には、シャドーイングがあります。
シャドーイングは、英語学習などでよく活用されるものです。
例えば、アップル(リンゴ)という音声を聞き、聞いた直後に音声で真似るという練習方法があります。
そして、練習では、単語→短い文章→少し長めの文章→・・・、といったように徐々に難易度を上げていきます。
そうすることにより、頭の中での記憶として保持・操作する力が鍛えられます。
療育現場では、子どもたちは自分が好きなアニメのシーンなどをすかさず真似ようとする行為があります。
こうした行為も、音で聞き取る→声に出す、という意味でワーキングメモリ(音声による)を鍛えるトレーニングに繋がっているように思います。
また、会話の中でも、シャドーイングに通じるものがあります。
例えば、相手の話を聞きながら、その内容を記憶に保持し、自分なりに整理して相手に伝えるという意味で、音声による記憶の保持と操作が入るからです。
以上、ワーキングメモリを鍛えるためには【発達障害児支援の現場から考える】について見てきました。
ワーキングメモリは学習を中心に、社会生活全般に影響する重要な能力です。
ワーキングメモリを鍛えるためには、先に見た、暗唱訓練やシャドーイングなどが有効だとされていますが、練習の際には、その人が興味関心を持って取り組むことが何よりも大切だと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後もワーキングメモリを鍛えるための動機を高める対象を療育現場で子どもたちと一緒に探していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「ワーキングメモリの概要:活用されているモデル・学習や発達障害との関連性について」
ワーキングメモリに関するお勧め書籍紹介
関連記事:「ワーキングメモリに関するおすすめ本【中級編】」
岡田尊司(2022)発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法.SB新書.

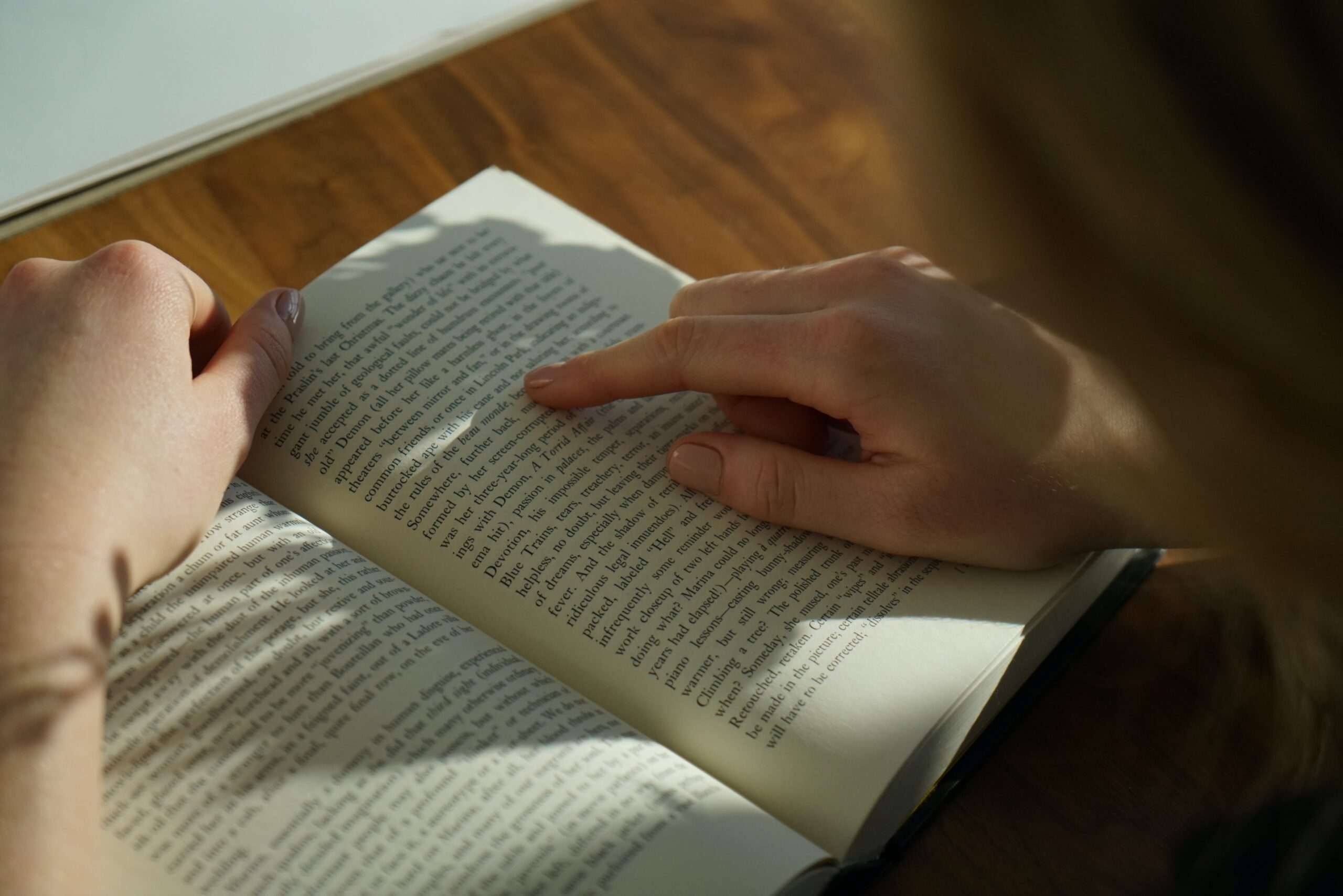
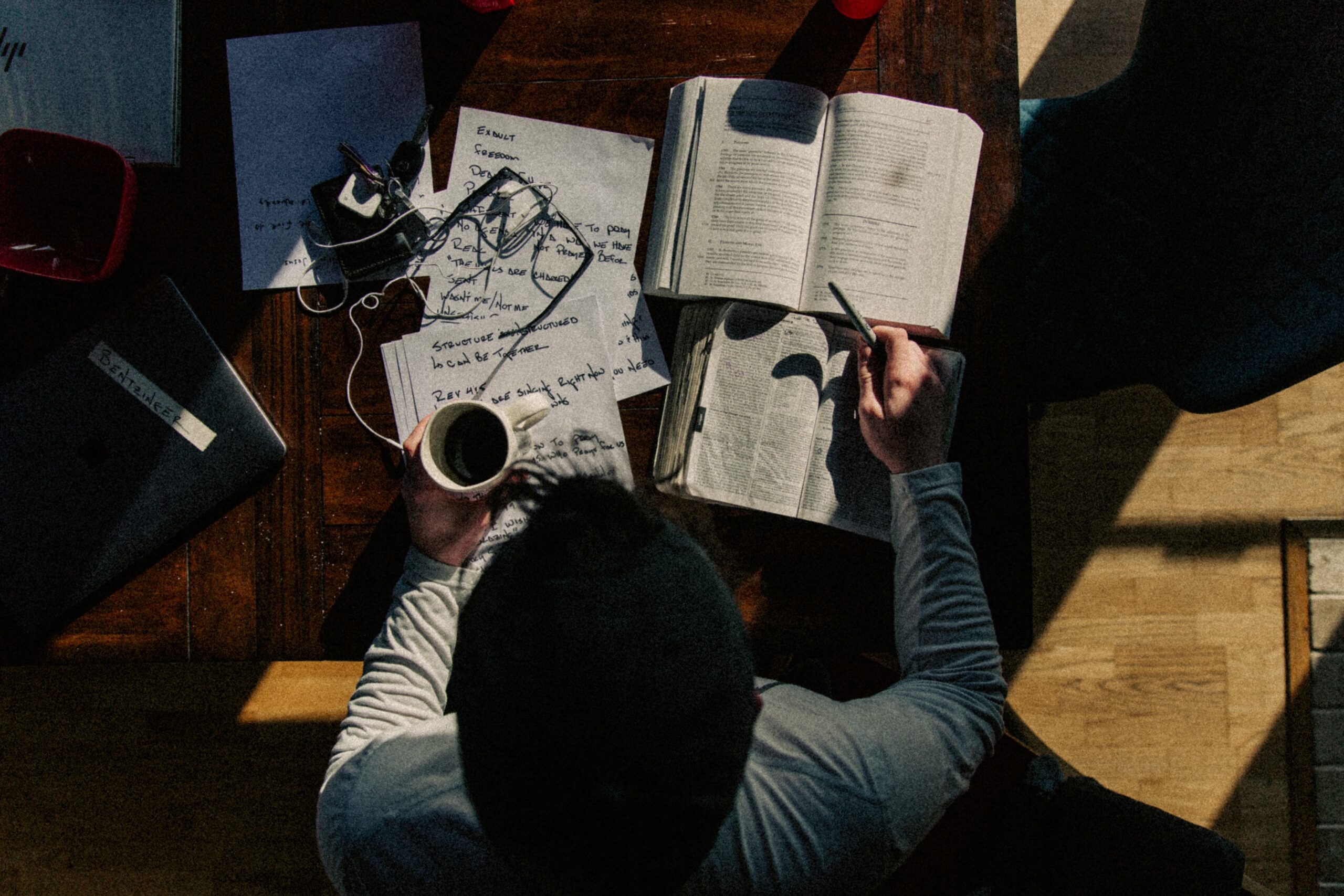
コメント