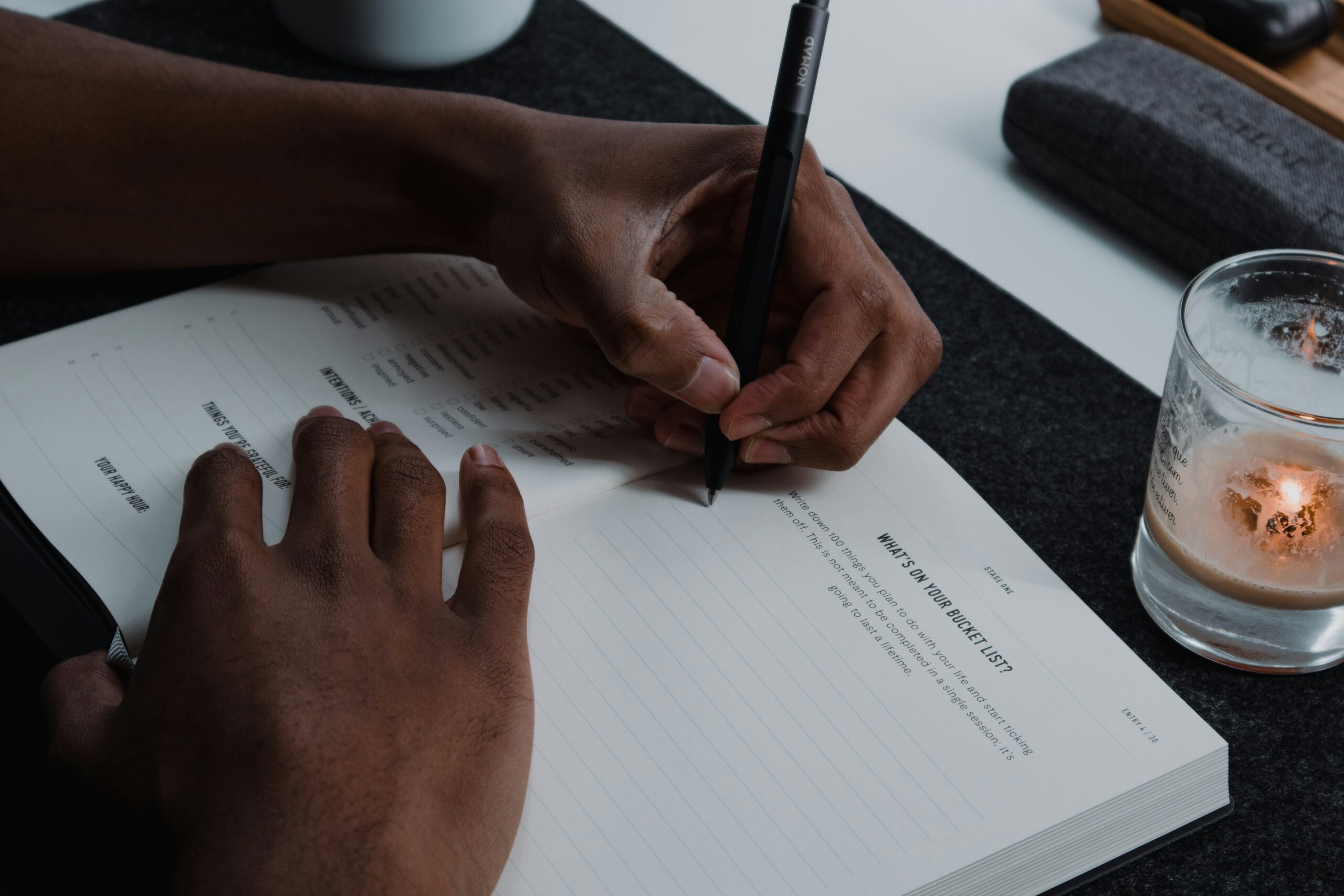
知能は正常でありながらも読み書きに苦手さがある人たちがいます。
こうした人たちの中には〝ディスレクシア(読み書き障害)“の人たちもいます。
ディスレクシアというと、読み書きの苦手さなどから、学校の勉強をはじめ、日常生活や社会生活に至るまで、様々な困難なことが語られることが多くあります。
一方で、ディスレクシアには強みもありますが、あまり語られることはありません。
それでは、ディスレクシアにはどのような強みがあると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、ディスレクシアの強みについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参考にする資料は「ブロック・L・アイディ/ファーネット・F・アイディ(著)藤堂英子(監訳)辻佑子・成田あゆみ(訳)(2021)ディスレクシアだから大丈夫!視点を変えると見えてくる特異性と才能.金子書房.」です。
ディスレクシアの4つの強みについて
著者は、この本を読んだときに、正直、自分の中で革命が起こったような感覚でした!
興味のある方はぜひ読んでみて下さい。
重要な点は、ディスレクシアだから、というところです。
以下、著書を引用しながらディスレクシアの4つの強みについて見ていきます。
①空間把握能力(Material reasoning)
物理的あるいは物質的な世界について把握する能力。つまり、空間内における物、サイズ、動き、位置関係、向き、物体が互いにどう連携するかを把握する能力。
②相互関係性把握能力(Interconnected reasoning)
複数のモノや概念、視点などの関係性を見つけることのできる並外れた能力。
③物語理解能力(Narrative reasoning)
過去の個人的経験の断片(エピソード記憶)を繋ぎ合わせ「脳内シーン」を構築する能力。
④シミュレーション能力(Dynamic reasoning)
エピソードのシミュレーションをもとに、過去や未来を正確に予測する力。
以上がディスレクシアの4つの強みになります。
詳細は、参考書の中に、それぞれの能力の詳細な内容や事例などが豊富に記載されています。
こうした強みは、ディスレクシアの人の中で、強弱が見られること、そして、一つが有意である(人によって複数あるなど)など、個人差があると言われています。
また、ディスレクシアが苦手とするものがあるからこそ、それとトレードオフで上記のような強みがあるといった視点が非常に興味深いところだと言えます。
関連記事:「【ディスレクシアに向いている仕事とは何か?】4つの強みに適した仕事について見る」
著者の経験談
著者は、診断は受けていませんが、ディスレクシア傾向があると感じています。
そのため、学校の勉強など学習において、これまで非常に苦労してきました。
それでは、ディスレクシア傾向のある著者がどの強みを持っていると感じているのかについて見ていきます。
それはずばり、②相互関係性把握能力(Interconnected reasoning)です。
これは何か能力を測定したというものではなく、あくまでも著者の主観的な感覚です。
それでも、この「相互関係性把握能力」が、なぜ著者の強みと言えるのかには、ある程度の根拠があります。
それは、著者が苦手とする読み書きと記憶力の弱さが背景にあると考えます。
つまり、こうした弱さを補うために、「相互関係性把握能力」が高まったと思います。
著者には、読み書きの苦手さに加えて、記憶力がとても弱いと感じています。
そのため、記憶力重視の学校教育にうまく適応することが困難でした。勉強で挫折した経験や、無力感に襲われた経験は、これまで非常に多くあったと思います。
なぜ自分は読みが苦手なのか?なぜ自分は記憶力がこんなに悪いのか?といった不安感や疑問は常にもっていました。
一度、自分の脳のどこかがおかしいのではないかと思い、MRIを撮りにいったほどです(笑)。もちろん、脳は正常でしたが・・・。
このような苦手さのある著者ですが、独学で勉強を進める中で、得意になってきた能力があります。
それは、物事の繋がりや関連性を考える力(「相互関係把握能力」)です。
記憶力が悪い著者は、とても大量の情報を覚えておくことができません。
そのため、もう覚える学びは止めにして、物事の関連や意味を掘り下げるといった学びにシフトしていきました。
シフトしたというよりも、シフトせざるを得なかったという感じです。
こうして、著者ならではの学びを進めていく中で、記憶力が仮に悪くても、物事を理解できないわけではない、一つひとつをしっかり覚えておかなくても大丈夫だということを学んでいくことができました。
そして、こうした学び方は、必然的に、物事の繋がりといった関連性を理解していくことに繋がり、細部ではなく全体的情報を理解することに通じていくのだと感じています。
もちろん、こうした力は徐々に身に付いてきたもので、最初から計画立てていたものではありません。
こうした学びを長く続けていくことで、人の脳はそれぞれ個性があること、そして、自分に合った多様な学び方があるのだと実感できるようになっていきました。
以上、【ディスレクシアの4つの強みについて】著者の経験談も踏まえて考えるについて見てきました。
今回取り上げた書籍は、ディスレクシアの強みに焦点を当てています。
こうした文献は非常に少ないため、著者のようなディスレクシアの特徴がある人たちにとっては、とても勇気づけられるものだと思います。
今後も多様な人間の発達を理解できるように、学ぶことを継続していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「ディスレクシアとは何か?:読み書きに困難のある人たちについて考える」
学習障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「学習障害(ディスレクシア)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
ブロック・L・アイディ/ファーネット・F・アイディ(著)藤堂英子(監訳)辻佑子・成田あゆみ(訳)(2021)ディスレクシアだから大丈夫!視点を変えると見えてくる特異性と才能.金子書房.









