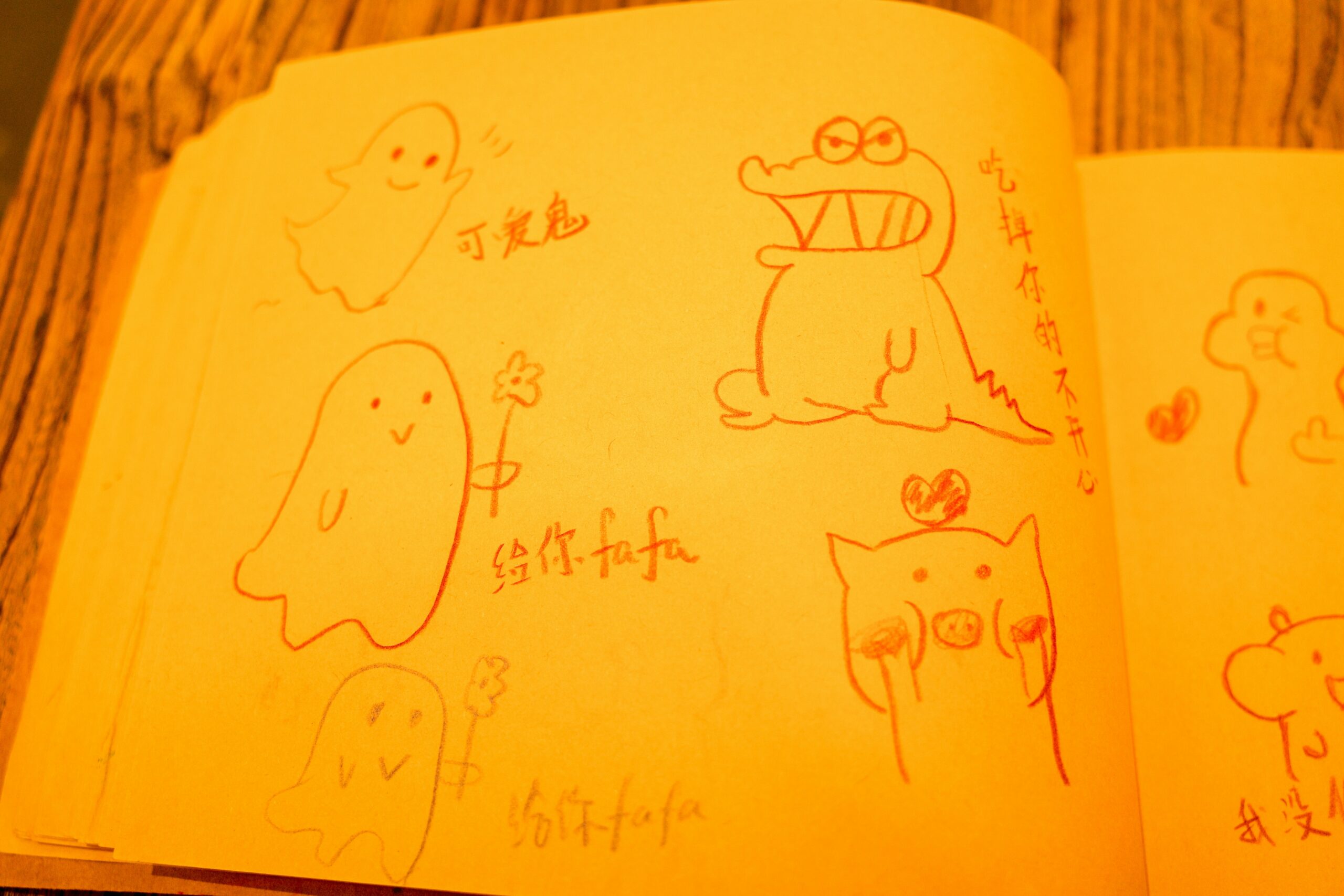
子どもたちは日々の〝遊び″の中で多くのことを学んでいきます。
著者の療育現場でも、日々行われている様々な〝遊び″を通して、子どもたちの成長・発達が短期・長期のスパンで見られています。
それでは、〝遊び心″を持って様々な事に取り組む姿勢は具体的にどのようなポジティブな影響があると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、遊び心は〝問題解決力″を高めるのか?といったテーマについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、遊び心を促進することによる利点から理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「ピーター・グレイ(著)吉田新一朗(訳)(2018)遊びが学びに欠かせないわけ 自立した学び手を育てる.築地書館.」です。
遊び心は〝問題解決力″を高めるのか?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
実験が示しているのは、「前向きな気分」が創造的かつ洞察力のある論理的思考を高めることだと述べています。私は、より具体的に、どのような「前向きな気分」がもっとも効果的なのかを提案したいと思います。それは、「遊びの気分」です。
小さな子どもたちは真面目な状況では解けなかったのに、遊びの状況だと論理的な問題を解くことができることを発見しました。
以上の著書の内容は、様々な実験を通した研究結果です。
つまり、〝遊び心″は、創造的かつ洞察力のある〝問題解決力″を高めたり、論理的な問題を解くことに貢献するといった内容です。
多くの人は、これまでやってきた前例(過去の知識や経験)をもとに問題を解く傾向があるかと思います。
その際に、〝遊び心″を取り入れることで、より創造的かつ洞察力といった、新たな発想やひらめきによって問題が解ける場面が増えるということです。
また、すべての人間は必ず死ぬ、Aさんは人間である、ゆえにAさんは必ず死ぬ、といった三段論法などに代表される論理的思考もまた、〝遊び心″を取り入れることでより論理的に問題を解く力が増すということです。
以上より、〝遊び心″を持って取り組むことは、〝問題解決力″を高めることに貢献することがこれまでの研究知見から分かってきています。
それでは、次に、〝遊び心″を持つことで〝問題解決力″が高まったと感じた著者の経験について見ていきたいと思います。
著者の経験談
著者は療育現場で生じる課題解決が求められる状況において、様々な発想やアイディアが必要になることが多くあります。
その時に、大真面目に取り組むことよりも、〝遊び心″をもって楽しんで取り組んだ方が良い発想やアイディアが浮かぶと感じています。
例えば、A君がうまく事業所で過ごすことができない、遊びの幅が広がらない、A君への関わり方がよくわからない、などの対応で困る場面(行き詰まりの状況)において、これまでの既存の枠組みを一度取り除いて新たな発想を構築していく姿勢の方がうまく行くケースが多いと感じています。
事業所ではなく外出活動を中心にしていく、これまでやったことのない遊びを大人がまずは楽しんでやっている様子を見せてからA君に働きかける、関わり方を柔軟にしていく(例:既存のルールを止めにするなど)、などの取り組みは子どもにもよりますがうまくいった対応の一部です。
人はこれまでやってきた前例を崩すことへの抵抗感を強く持つ生き物です。
一方で、問題を解決するためには時に前例を崩していくなど新しい発想やアイディアが必要であり、こうした既存の枠組みを崩す時には、〝遊び心″を持って取り組んだほうが前向きな思考が出やすいと感じています。
今思い返すと、直感的に良いと感じる問題解決法は、意外にも自分が楽しんで取り組んでいる状態のときの方が多かったように思います。
以上、【遊び心は〝問題解決力″を高めるのか?】遊び心を促進することによる利点から考えるについて見てきました。
人は日々様々な問題と向き合う場面があります。
それは、療育で関わる子どもたちだけではなく、関わる大人たちすべての人に共通することです。
子どもにしても大人にしても、〝遊び心″を持って楽しんで取り組んだ方が問題の解決力は高まるのだと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も関わる子どもたちに〝遊び心″をもって取り組むことの大切さを伝えていくと同時に、自分自身もまた〝遊び心″をもって様々なことに取り組んでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【遊び心は〝学び″や〝創造性″を高めるのか?】遊び心を妨げることによる障害の視点から考える」
ピーター・グレイ(著)吉田新一朗(訳)(2018)遊びが学びに欠かせないわけ 自立した学び手を育てる.築地書館.









