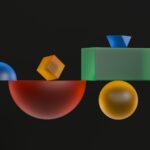自閉症(自閉スペクトラム症:ASD)とは、〝社会性の障害″〝コミュニケーションの障害″〝こだわり行動″を特徴とする発達障害です。
自閉症児への理解と支援を考えた場合、上記の三つの特徴(〝三つ組″)を理解して、それに対して対応策を考えることが大切です。
それでは、自閉症児の〝三つ組″への支援にはどのような視点が大切になるのでしょうか?
そこで、今回は、自閉症の療育で大切なことについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、〝三つ組″への支援で大切な〝人間関係″の力を育てる視点について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「白石雅一(2024)おもちゃ教材で育む人間関係と自閉スペクトラム症の療育~親・保育園・幼稚園・学校・児童発達支援・放課後等デイサービスのためのガイド~.東京書籍.」です。
自閉症児の〝三つ組″への支援で大切な〝人間関係″の力を育むこと
以下、著書を引用しながら見ていきます。
実は、ASDの人たちがもつ「社会性の障害」も「コミュニケーションの障害」も「こだわり行動」も「対人関係の障害の仲間である」というように〝大きく括ってしまう″ことで、アプローチがしやすくなります。
具体的には、「対人関係の改善や形成、維持、発展」を期して行う取り組みがASDの「社会性の障害」や「コミュニケーションの障害」「こだわり行動」のそれぞれに効くとともに、ASDの人々を成長・発達へと導くことになるのです。
著書の内容から、自閉症の〝三つ組″への支援で大切なことは、〝三つ組″すべてを〝対人関係の障害″として一括りにして対応することでより支援がしやすくなると考えられています。
つまり、〝対人関係の障害″への支援として、〝人間関係″の力を育てることが重要であると言えます。
もちろん、〝こだわり行動″に対しては、〝こだわり″の特徴を理解してそれに伴う対応をすることも重要です。
一方で、〝人間関係″の力を育てることは、〝こだわり″も含めて、自閉症の〝三つ組″すべてに効果的な方法であると言えます。
それでは、次に、著者が〝こだわり行動″をよく見せていた自閉症児に対して〝人間関係″の力を育てるアプローチを取ることで〝こだわり行動″が低減した経験談について見ていきます。
著者の経験談
当時、小学校高学年であった自閉症児Aさんを例に見ていきます。
Aさんとは長年にわたり、関わることのある児童でしたが、特にAさんが高学年になってから著者との関係がより深まっていきました。
それ以前のAさんは、一人遊びが多く、周囲からもあまり干渉されたくないタイプのお子さんで、〝時間通りに行動したい″といった〝時間へのこだわり″が強く見られていたケースです。
著者はAさんの興味関心を把握していきながら、少しずつAさんにとって何が好きで、どのような関わり方を好むのかを試行錯誤していきました。
すると、Aさんは自身が持つ興味関心を著者と共有する頻度が高まっていきました。
Aさんは興味関心が共有できた喜びと、自身の発信に対してどのような反応を著者が見せるのかを期待する眼差しで著者の表情を見つめるようになりました。
この頃から、Aさんと非常に〝視線が合う″ことを実感するようになりました。
著者は、Aさんからの発信を待つだけでなく、著者からもAさんが楽しめそうな話題や遊びを提案していきました。
すると、さらに、Aさんとの関わりの量・質が増えていきました。
Aさんが高学年になる頃には、〝時間へのこだわり″が非常に弱くなっていきました。
また、著者の提案や事前の見通しへの合意が以前よりもスムーズに取れるようになっていきました。
こうした変化の背景には、Aさん自身の〝人間関係″の育ちがあったのだと思います。
もちろん、〝こだわり行動″への理解と配慮も行っていましたが、大きな変化は〝人間関係″の育ちであったことは周囲の目から見ても明確であったと思います。
このように、〝三つ組〝へのアプローチには、〝人間関係″の力を育てることが大切だと学ぶことができた重要な事例だと感じています。
以上、【自閉症の療育で大切なこと】〝三つ組″への支援で大切な〝人間関係″の力を育てる視点について見てきました。
自閉症児の人間関係の力を育てることは簡単ではありません。
一方で、時間をかけて人間関係の力を育てることは、生活および人生をより豊かにしていくためにも大切な視点であると感じています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場で子どもたちの人間関係の力を育んでいけるように、実践からの学びを大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【自閉症スペクトラム障害の特徴について】三つ組とは何か?2因子モデルとは何か?」
関連記事:「【自閉症児の人間関係の育て方】乳児期~幼児期の発達段階を通して考える」
関連記事:「【自閉症児の人間関係の育て方】児童期の発達段階を通して考える」
白石雅一(2024)おもちゃ教材で育む人間関係と自閉スペクトラム症の療育~親・保育園・幼稚園・学校・児童発達支援・放課後等デイサービスのためのガイド~.東京書籍.