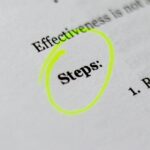自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)とは、対人・コミュニケーションの困難さとこだわりを主な特徴としています。
自閉症の人たちは、その特性が影響して、特別な配慮がないと学校や社会の中で躓きやすいとも言われています。
もちろん、こうした特性理解や配慮の点が自閉症の人たちの人生を生きやすくすることに繋がります。
一方で、その他の視点から、自閉症の人たちが自分の人生を豊かに生きるためには、どのようなことが大切となるのでしょう?
そこで、今回は、自閉症の人が将来に向けて必要なこととは何かについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、豊かな人生を歩むために大切なことについて考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「本田秀夫(2013)自閉症スペクトラム:10人に1人が抱える「生きづらさ」の正体.SB新書.」です。
自閉症の人が将来に向けて必要なこととは何か?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
思春期の自閉症スペクトラムの人たちが、後悔せずに人生を歩もうと思うためには、やはり、目標を持てているということが重要です。目標が定まっている人、自分の力で選択や判断をしていると思えている人、難関や挫折を自分の力で克服できたと思えている人。思春期以降の失敗は、失敗の後に立ち直ってうまく解決すると自信になるのです。
著書の内容から、自閉症の人が将来に向けて必要なことに、〝目標がある″ことをあげています。
目標があることで、自ら様々な選択を行い、失敗経験も糧にして前に進んでいこうという道の歩き方が大切になります。
もちろん、〝目標がある″ことは自閉症の人に限らず多くの人の人生を豊かにするものだと思います。
そして、〝目標″とは、必ずしも明確である必要はなく、そして、変わって行ってもいいと思います。
〝何となく○○になりたい″〝○○のように生きたい″といった漠然としたものでも入り口としては大切だと考えます。
そして、〝目標″があるかないかで人生の輝き度は変わってくると思います。
著者の経験談
著者の周囲にも自閉症児・者をはじめとした発達障害のある人、診断は受けていないが発達特性のある人たちがいます。
こうした人たちとの関わりを通して、〝目標″を持つことはとても大切なことだと実感しています。
著者が関わる子どもの中にも、〝目標″が何となくでも見つかったことで、自分の進むべき道が見つかり、将来に対して期待が持てるようになった子どもたちもいます。
つまり、将来の自分に期待が持てる、将来もっと楽しいことがある、将来新しい楽しい世界に出会えると思えるようになる、などです。
こうした将来に関するポジティブな会話が子どもたちの中に見られる場合には(もちろん、不安も混在していますが)、豊かな人生をその人の中で思い描くことができているのだと思います。
逆に、〝やりたいことがない″〝やる意欲がない″〝日々を生きることで精一杯で目標など考える余裕がない″といった人たちもいます。
昔の著者もどちらかというと、将来に対してネガティブ感情の方が強かったと思います。
しかし、後に〝目標″ができたことで、失敗経験も含めて前向きに進んでいけるようになりました。
〝目標″を見つけるためには、様々な経験が必要不可欠だと思います。
様々な経験の中で、自分が何が好きで得意であるのかを漠然とでも見極めることができます。
そして、思春期までには、意欲のエネルギーが衰退しないような関わり方が非常に大切だと思います。
意欲のエネルギーが保たれていないと、〝目標″を探す、〝目標″に向けて進む、ということは難しくなるように思います。
もちろん、〝目標″が見つかったことで、意欲のエネルギーが高まり始めたという場合もあるかと思いますが、大切なことは、そもそもその人の中で、自分が肯定されてきた経験、自分の取り組み過程が認められてきたという経験、日々の活動の中での成功体験の積み重ねなどがベースにあることが必要だと思います。
以上、【自閉症の人が将来に向けて必要なこととは何か?】豊かな人生を歩むために大切なことについて考えるについて見てきました。
〝目標″があることで人生の輝き度が増すということは、著者は自分の経験と周囲の人との関わりを通して実感しています。
もちろん、〝目標″は人に自慢できるような大きなものである必要はありません。
どんなに小さな〝目標″であっても、自分が進むべき道があり、進む過程の中で様々な経験を積み重ねていくことが豊かな人生に繋がっていくと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も〝目標″を持ち続けながら、日々の成長を楽しんでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「自閉症児が思春期を乗り越えるために大切なことについて考える」
本田秀夫(2013)自閉症スペクトラム:10人に1人が抱える「生きづらさ」の正体.SB新書.