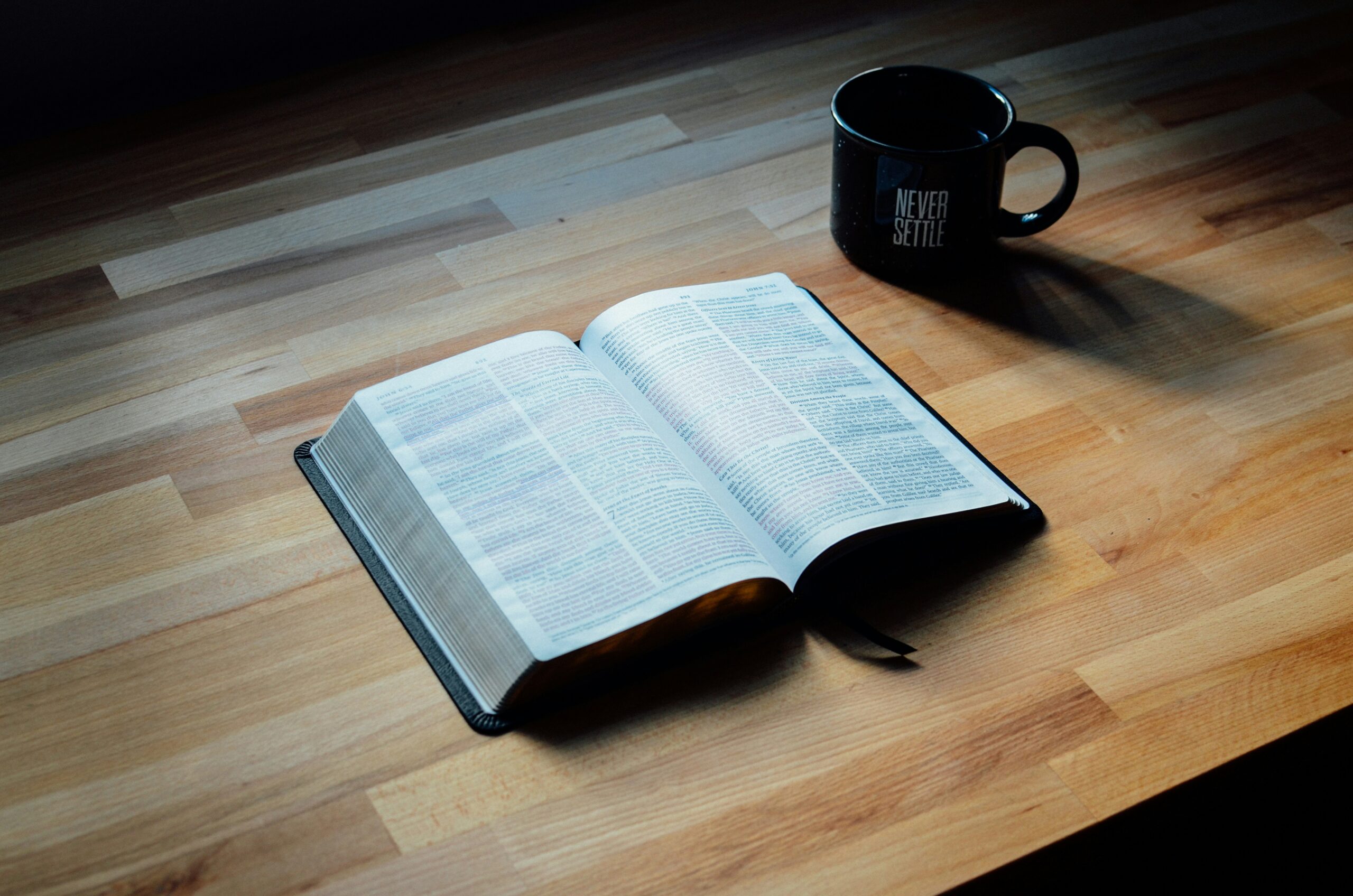
著者は年々、〝発達障害″など発達に躓きのある子どもたちを支援してきています。
年齢層は、未就学や小学生を主な対象としています。
関わるフィールドは、児童発達支援、放課後等デイサービスといった療育(発達支援)の現場です。
療育経験を通して、発達障害児支援には高い〝専門性″が必要だと感じています。
それでは、発達障害児支援の専門性にはどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害児支援の専門性について、臨床発達心理士である著者の経験談を元に理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
発達障害児支援の専門性について
著者が発達障害児支援の〝専門性″として必要だと考えるものは大きく以下の2点です。
1.発達に関するアセスメント(見立て)
2.オーダーメイドの支援(配慮)
それでは、この2点について見ていきます。
1.発達に関するアセスメント(見立て)
発達障害のアセスメントに関連する情報は非常に膨大にあります。
その中でも、子どもの発達の状態を〝見立てる″こと、つまり、〝アセスメント(査定・評価)″することは大切です。
この見立てが大きく現状とズレてしまうと、その後の支援が誤った方向に進んでしまうことがあります。
現在の状態にいかに接近していくかが大切です。
アセスメントには〝包括的アセスメント″といった様々なアセスメントツールからその子の状態像を包括的に理解していくアセスメントの方法があります。
しかし、〝包括的アセスメント″を実施している療育現場は非常に少ないと思います。
著者の療育現場も他機関で実施した検査結果などを保護者の承諾を受けてお借りすることもありますが、こうしたフォーマルアセスメンの情報は少なく、アセスメントの多くは〝インフォーマルアセスメント″から情報を収集しているのが現状です。
一方で、〝インフォーマルアセスメント″は現場で支援をしていく上でとても大切な情報収集の方法です。
その理由は、日頃の(そしてこれまでの)生活の中での情報収集であるため、実際の支援に直結しやすいといった利点があります。
もちろん、〝フォーマルアセスメント″と〝インフォーマルアセスメント″を両方組み合わせて〝見立てる″ことが理想であると思います。
関連記事:「発達障害への包括的アセスメントについて」
関連記事:「【二次障害のアセスメントで必要なインフォーマルアセスメント】発達障害児支援の現場を通して考える」
次に、〝発達に関する理解″です。
発達に関する情報は、生育歴に加え、これまでの支援経過、家庭環境、学校の情報や子どもの障害特性や二次障害の有無といった環境要因と個人要因に時間軸を加えて理解していくことです。
ここで大切になるのは、長年にわたり一人の子どもの成長を見たきた〝経験″や様々な〝ライフステージにおける子どもの発達課題″を理解する目を養っていくことだと思います。
子どもの成長は日々の積み重ねによって変化を遂げていきます。
この点に関しては、〝知識″も重要ですがそれ以上に〝経験″の中で試行錯誤して子どもの発達を考えてきたという過程が大切だと感じています。
関連記事:「臨床発達心理学とは?-療育経験からその視点の重要性を考える-」
2.オーダーメイドの支援(配慮)
現在の特別支援教育はより〝個別化″といった一人ひとりの子どものニーズに応じた教育が大切になってきています。
つまり、〝オーダーメイドの支援″の必要性が高まっているということです。
オーダーメイドの支援を行う上で著者が大切にしていることは以下3点です。
①アセスメントによる見立てと関連させて支援を実施する
②特性への配慮
③保護者支援
④コミュニティ支援
①アセスメントによる見立てと関連させて支援を実施する
療育現場では大きく活動(遊び)がメインになります。
様々な活動を通して子どもの中に愛情や意欲エネルギーを充足していくことが大切になります。
そして、先に見た〝見立て″に基づいて、つまり、子どものニーズに応じてどのような支援内容が必要なのかを検討していくことが重要です。
逆に、活動を進めていくことで子どもが何に困っているのか?何を欲しているのか?に気がつくこともあります。
このように、見立て⇔支援、といった双方向性が専門性を高めるためにとても大切です。
②特性への配慮
〝オーダーメイドの支援″で重要な点は〝特性への配慮″です。
つまり、みんなと一緒という視点ではなく(平等)、個々によって異なる対応が必要(公平)という視点を重視していくことです。
ASDやADHD、IDなどの神経発達障障害は、生まれもっての特性です。
そのため、個人の努力での改善が難しいため、周囲が特性に合わせた関わり・環境調整をすることが大切です。
配慮された環境で子どもが育つことで、〝自尊心″や〝自己効力感″、〝レジリエンス″が高まるといった心の成長に繋げていくことができると感じています。
③保護者支援
子どもの状態に直結しているのが保護的の心の状態です。
保護者がいつもイライラしている、不満感が高まっている状態だと支援が思うように進まないことがあります。
そのため、子どもを一時的にでも預かり、保護者に心の余裕を持ってもらうことがとても重要だと思います。
保護者が安心して預けることのできる場があることで、保護者にとって地域で子どもを育てていくことができるといった気持ちが出でくることが大切(ソーシャルサポートが得られる感覚)だと思います。
④コミュニティ支援
すべての人は繋がりの中で生きています。
子どもが日々を安心して生きていくためには、家庭や園・学校以外にも安心して過ごすことができる〝居場所(サードプレイス)″が必要です。
子どもは様々な他者と繋がることで、大人への信頼を獲得し、他児と繋がる喜びを感じることができるのだと思います。
子どもの〝社会性″は良いコミュニティの中で育まれていく側面も大いにあると感じています。
関連記事:「発達障害児にとって大切な〝サードプレイス″の価値について考える」
以上、【発達障害児支援の専門性について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
これまで見たきた以外にも発達障害児支援の〝専門性″は多くあると思います。
今回は、その中でも著者が必要不可欠だと感じているものをピックアップしてみました。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も発達障害児支援の専門性を高めていけるように、経験と知識からの学びを大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「療育(発達支援)の専門性5選」









