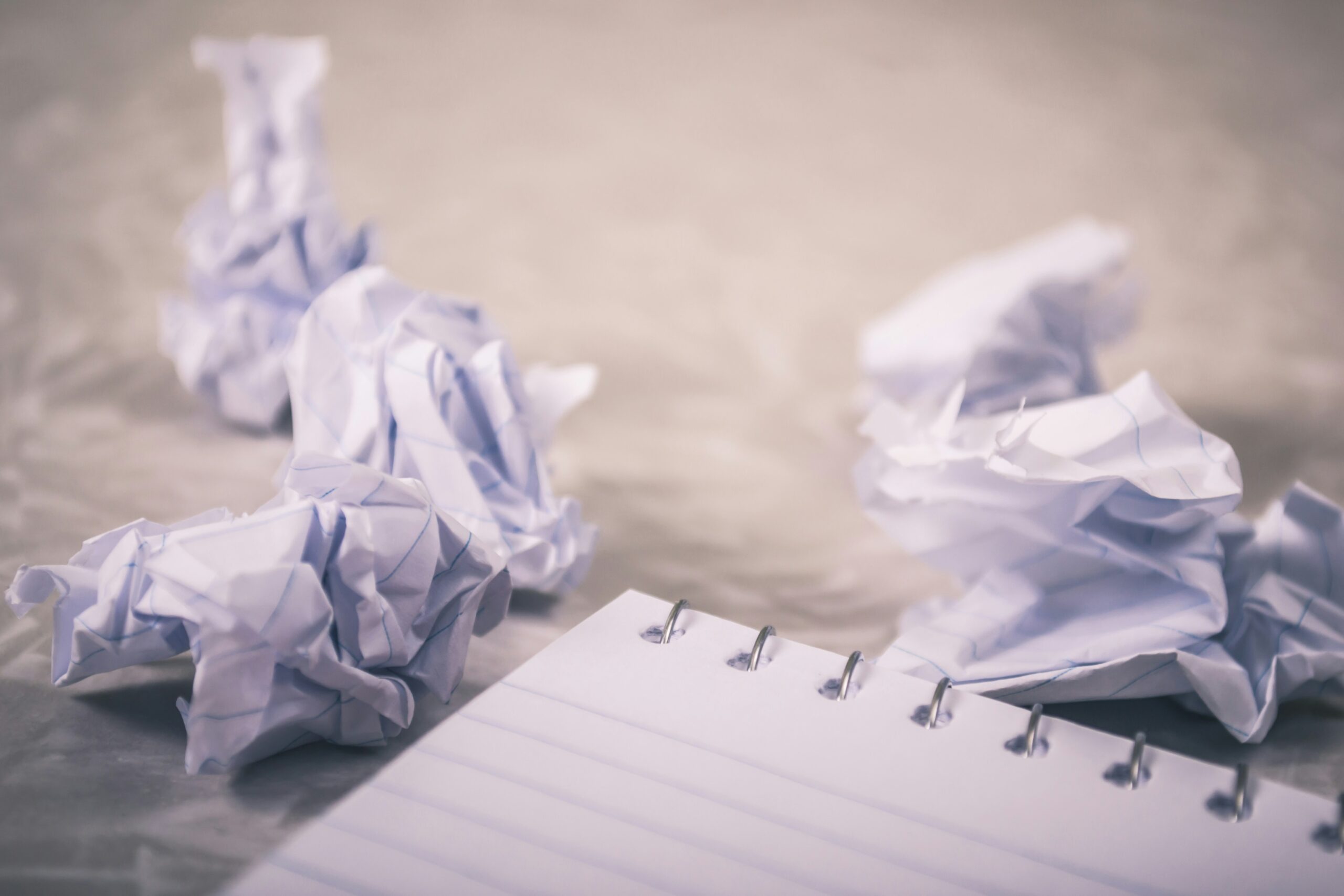
発達障害児支援には良き対応もあれば悪い対応もあります。
もちろん、両者は明確に境界線を引けるわけではない場合もあります。
一方で、決してしてはいけないNG対応があることも事実です。
それでは、発達障害児に対して、やってはいけない対応にはどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害児へのNG対応について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら、注意の繰り返しによる悪影響について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「加藤博之(2023)がんばりすぎない!発達障害の子ども支援.青弓社.」です。
発達障害児へのNG対応とそれによる悪影響
以下、著書を引用しながら見ていきます。
いつも注意ばかりしていては子どもとの関係に悪影響を及ぼしてしまいます。(中略)子どもを注意しすぎることは、以下の点で不適切と考えられます。
①余計にイライラさせて、不適切な行動を促進してしまう。
②その場の雰囲気を壊してしまう。
③誤学習につながってしまう。
著書の内容を踏まえると、発達障害児へのNG対応として、注意や叱責をすることをやり続けてしまうことは、子どもとの関係構築の上で悪影響に繋がるマイナスな対応だと言えます。
そして、注意や責を頻繁に行うことで、上記の①~③のマイナスとなる影響が生じます。
それでは、次に①~③について著者の意見も交えながら見ていきます。
著者のコメント
著者は長年、療育現場で発達障害など発達に躓きのある子どもへの支援をしてきています。
その経験を踏まえて①~③について見ていきます。
①余計にイライラさせて、不適切な行動を促進してしまう。
子どもに対して注意をする際に、落ち着いた声のトーンで、子どもの行動を適切な方向へと導くものであれば良いのですが、関わる大人が不快な感情を前面に出して対応することは行動の修正どころか、不適切な行動の増加に繋がってしまうと思います。
本来、注意や責とは、子どもの不適切な行動を適切な行動へと修正するために行うものです。
かつての著者は、イライラした態度で子どもを注意することがありました。
それは、そうした態度が子どもに怒っていることを伝えることになり、不適応な行動の改善に繋がると考えていたからです。
しかし、こうした対応でうまくいったケースはほとんどなかったように思います(長期的にみるとゼロだと思います)。
著書にあるように、逆に不適切な行動を促進してしまっていたかもしれません。
それは、大人のネガティブ感情が伝搬することで、大人がかけた声掛けの内容よりもイライラ感の伝搬が優位になってしまうからだと思います。
②その場の雰囲気を壊してしまう。
大人が大声で注意や叱責をすると、周囲の子どもたちにもマイナスな影響を及ぼしてしまうと思います。
著書にあるように、〝場の雰囲気を壊してしまう!″ということです。
もちろん、注意している当人は良かれと思っていやっているのかもしれません。
しかし、情動は伝搬します!
ネガティブ感情やイライラした態度は周囲に少なからずネガティブな影響を及ぼします。
逆に、常に一定の声のトーンで注意や責をした方が(できれば個別の環境の中で)、周囲の子どもたちは安心して過ごすことができるのだとこれまでの著者の経験からも言えることだと思います。
③誤学習につながってしまう。
子どものマイナス行動に対してだけ目を向けて関わることは〝誤学習″に繋がってしまうと思います。
大人の中には、マイナスな行動への感度が高い方が多くいます。
子どものマイナス行動を修正することが支援上とても大切だと考えている方もいると思います。
一方で、著者の経験上、マイナス行動にばかり目が向けられ、注意や叱責を受けている子どもたちは、その大人の前だけではしないようにする、逆にたまった鬱憤を他の場ではらす、大人がさらに困るような態度をとるようになる、など〝誤学習″に繋がる行動が増えてしまっていたと思います(後々回想すると)。
以上、【発達障害児へのNG対応】注意の繰り返しによる悪影響とは何か?について見てきました。
今回見てきた内容は必ずしも発達障害児限定の話ではないと思います。
すべての子どもへの対応で心がけることだと思います。
そして、NG対応を認識していく中で、良き対応・良き関わり方も見えてくるのだと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場で関わる子どもへの成長・発達に貢献していけるように、自分の対応のあり方を見直していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【間違った〝叱り方″による問題点とは?】発達障害児支援の現場を通して考える」
関連記事:「【子育てにおいて重要な3種類の〝褒め方″とは?】効果的な〝褒め方“について考える」




