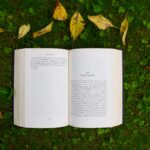教育現場では、子どもが一人一台、パソコンやタブレットなどが普及される時代になってきています。
また、家庭でもパソコンやタブレットなどを通して、子どもが様々な情報にアクセスしたり、ゲームやSNS等の活用頻度が増加しています。
一方で、過剰な電子機器の使用は依存に繋がるリスクもあります。
それでは、電子機器の有効な活用方法にはどのような内容があるのでしょうか?
また、電子機器のやりすぎを防止するためには、どのようなルールが必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害児のタブレットの有効な活用方法とルール設定について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「加藤博之(2023)がんばりすぎない!発達障害の子ども支援.青弓社.」です。
タブレットの有効な活用方法について
著者の療育現場では、タブレットを活用することがあります。
台数は2~3台であるため、時間で区切るなどして利用者10名程度の子どもたちの要望を聞きながら貸し借りをするように調整しています。
子どもたちがタブレットを使っていく中で有効だと感じる活用方法も見られます(以下、代表的なものとして3つ紹介します)。
①制作活動をする時の参考に活用する
段ボール工作や折り紙など子どもたちは様々な遊びをします。
そして、こうした制作遊びをする際に、動画を見本として作業を進めることで、子どもたちの理解の補助の役割を果たしてくれることが多いにあります。
子どもたちの中には、大人の手を借りずに、自分で動画検索をして自分が作りたいものを作れるようになったケースもあります。
②他者とのコミュニケーションツールとして活用する
子どもたちの多くは、自分の興味関心のある動画に熱中します。
そして、ある時期を境に他者と興味関心のポイントが重なると、その後、他者とタブレットを通して会話のやり取りが増えていく様子が見られることがあります。
普段なかなかうまく話せない子どもでも、タブレットを通して会話が盛り上がる場合もあります。
③イラストを繋ぎストーリーを作る媒体として活用する
子どもたちの中には、イラストを作成して完成した画像を繋ぎ合わせて、ストーリーを作成するケースもあります。
画像編集とも言えるこの作業により、子どもたちは個々で作成した作品を他児と情報交換するなど、他者と完成した作品を一緒に楽しむ様子も多く見られます。
タブレットのルール設定について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
ゲームやネットをやみくもに禁止することは現実的ではありません。電子メディアとどう付き合っていくかを考えることのほうが重要になってきます。
要因の一つであるストレスを、家庭や学校でできるだけ軽減させることが必要です。
そのうえで、電子メディアと関わるルールを設定していきます。
切り替えが苦手な発達障害の子どもにとっては、「中途半端」でやることは困難を極めます。そもため、時間で区切るよりも「きりがいいところで終わる」というほうが、子どもにとっては受け入れやすいと思われます。
タブレットなど電子機器の活用のルールについて以上の引用から次のことが言えるかと思います。
①禁止事項を設けることより、付き合い方を考えていく
禁止事項が増えると子どもたちはさらに反発心が増加します。
禁止事項以上に、子どもたちが納得できるタブレットとの付き合い方について、提案をベースとして考え実行していくことが有効だと思います。
②他の活動で過度なストレスがないかを確認しながらルールを設けていく
過度なストレスがタブレットへの長時間使用に影響している場合もあります。
そのため、ストレス要因の分析と軽減、そして、他の活動への誘い掛けが必要だと思います。
③単純に時間で区切るのではなく、〝きりがいいところで終える″を意識する
単純に時間で区切ることは関わる大人たちにとってはわかりやすいルール設定です。
一方で、時間への縛りを強くしてしまうと、子どもたちの〝きりよく活動を終える″に繋がらなくなってしまうことがあります。
こうなると心が満たされなくなるため、結果としてうまくいかない場合が多くでてくるように思います。
そのため、ルールは前提として設定するも、その子の〝きりの良さ″を意識した関わり方がさらに重要だと感じます。
以上、【発達障害児のタブレットの有効な活用方法とルール設定について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
タブレットをはじめ、電子機器の活用によるゲームや動画鑑賞など過度な集中や活動内容の縮小は療育現場において危惧すべきことです。
一方で、今回見てきたように能動的なメディアの活用方法や他者との共有・共感のツールとして活用することは、とても有効な活用の仕方だと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も発達障害児支援において、タブレットなどメディアの活用方法やルール設定について試行錯誤していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「療育現場でのタブレット活用の好ましい変化」