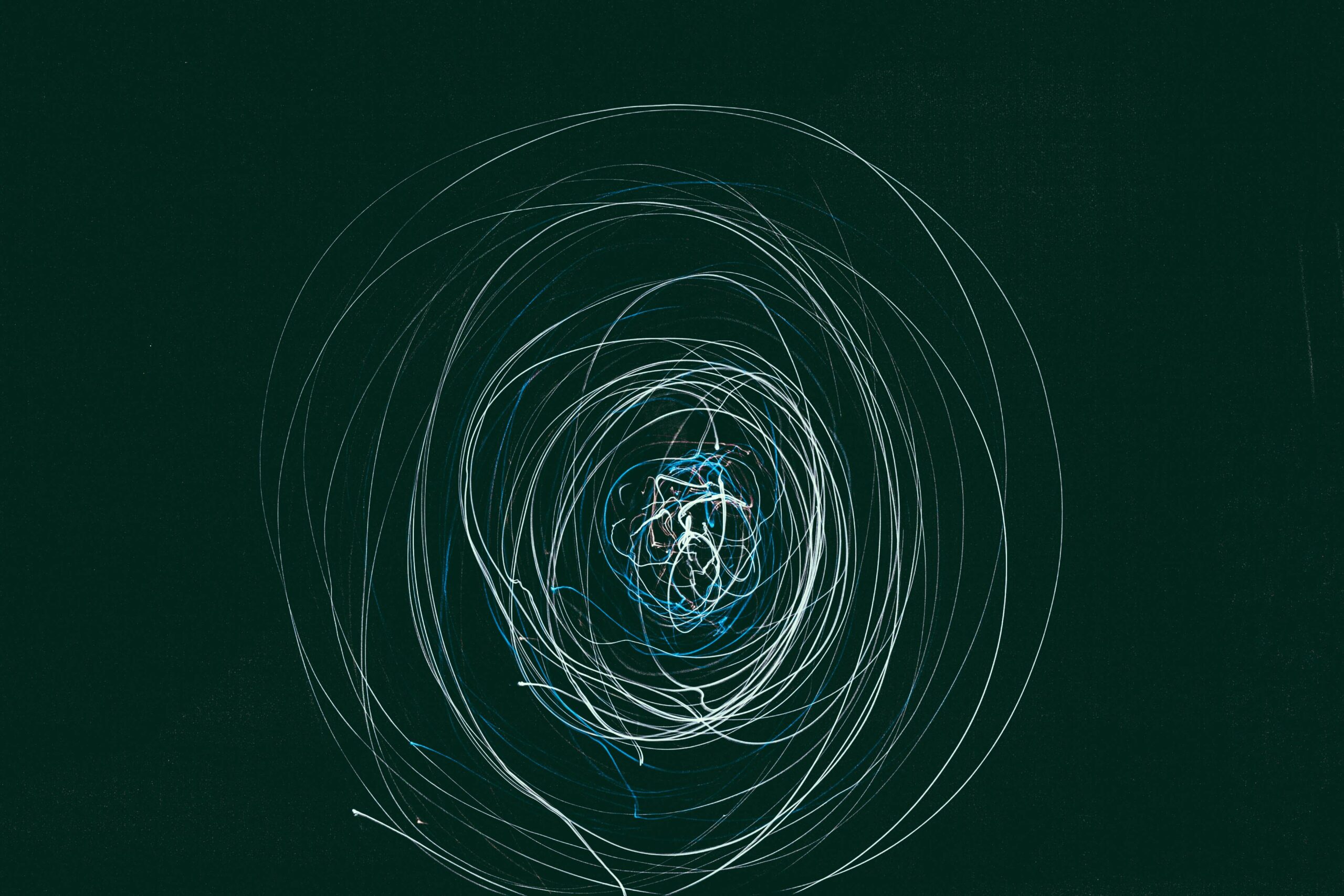
境界知能の人たちへの理解と支援で思い悩んだことはありませんか?
書籍やメディアなどを通して、ここ最近〝境界知能″が社会的に認知されるようになってきています。
一方で、具体的な状態像の理解や支援に関しては、まだまだこれからといった状況にあると言えます。
著者の周りにもおそらく境界知能だと想定される人たちがおり、実際に困り感が様々な生活・仕事場面で見受けられます。
かつての著者は、境界知能とは何か?どのような特徴があるのか?どのような支援が必要なのか?ほとんど分からない状態でした。
しかし、当事者感を持ちながら、様々な書籍等を読み進めて行く中で、まだまだ理解や支援が行き届いていない人たちだということが分かってきました。
今回は、実体験+理論+書籍の視点から、境界知能に関する理解と支援のヒントについてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
目次
1.境界知能の当事者のエピソード
2.境界知能を理解する理論・書籍
3.境界知能に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
4.まとめ
1.境界知能の当事者のエピソード
境界知能の成人男性Aさんの事例を取り上げて見ていきます。
Aさんは、知能検査の結果、境界知能の領域にいる人です。
一方で、当時は、境界知能といった言葉が無かったため、知的水準が少し低い程度といった理解に留まっていました。
そのため、学校教育や日常生活において、様々な困り感がありながらも、〝何とか″〝やれている″状態だったこともあり、周囲はそれほど問題として取り上げることはありませんでした。
この〝何とか″〝やれている″を少し具体的に見ていくと、〝何とか″→〝本人の精一杯の努力で″、〝やれている″→〝本人はそう感じていないが周囲はそう感じている″といった視点に置き換えることができます。
そのため、様々な所で、精一杯の努力を強いられることが増え、また、周囲もなんとかできているから大丈夫だという認識から、Aさんを徐々に苦しめる方向に理解が向いていたように思います。
その後、Aさんは、中学・高校へと進むにつれて、徐々に状態が悪化していきました。
うつ病も発症するなど二次障害の症状も発症していました。
幼い頃からAさんを見ていた著者は、Aさんが成人期を迎えた以降に〝境界知能″という言葉を聞いて、Aさんが〝境界知能″の特徴に非常に似ており、そこで初めてAさんに対して腑に落ちる状態の理解への突破口が見えてきました。
2.境界知能を理解する理論・書籍
それでは、境界知能の理解を深めていく上で、著者が非常に参考になった書籍を以下に紹介していきます。
書籍①「梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.」
書籍②「本田秀夫(2013)子どもから大人への発達精神医学:自閉症スペクトラム・ADHD・知的障害の基礎と実践.金剛出版.」
書籍③「宮口幸治(2023)境界知能の子どもたち 「IQ70以上85未満」の生きづらさ.SB新書.」
書籍②に関しては、改訂版が出版されています。
「新訂増補 子どもから大人への発達精神医学: 神経発達症の理解と支援」
以上の書籍を踏まえて、著者が非常に参考になったキーポイントとして、1.境界知能とは何か?、2.境界知能と知的障害・発達障害の違い、3.境界知能の特徴、4.境界知能の支援の難しさ、5.境界知能への支援です。
それでは、次に、以上の5つのキーポイントについて具体的に見ていきます。
1.境界知能とは何か?
以下、著書①を引用しながら境界知能の定義について見ていきます。
一般的には、知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態を境界知能と考えます。
境界知能には明確な定義がなく、文献によっては「IQ71以上」「IQ85以下」などと書かれていることもあります。
医学的な診断がつくこともありません。
著書の内容から、〝境界知能″とは、知的機能が平均以下であり、かつ、知的障害に該当しない人たち(文献によって違いあり→IQが70~84のゾーンorIQ71~85のゾーン)のことを指します。
一方で、明確な定義はなく、医学的な診断がつくこともありません。
このゾーンの人たちは、人口全体の14%に相当し、通常のクラスに約5人いる計算になります。
割合を考えると決して珍しい人たちではないと言えます。
行動特徴としては、学習面や運動面、社会性の面など、様々な所で遅れが見られることがあります。
著者が〝境界知能″を知るきっかけとなった書籍として、宮口幸治さんが書いた「ケーキの切れない非行少年たち」があります。
この本を読んでから、先に紹介したAさんの状態像と非常に重なる点が多くあることに気づかされました。
2.境界知能と知的障害・発達障害の違い
境界知能の理解を深めていく上で、そこに隣接する他の障害との違いを知ることはとても重要です。
それでは、次に、書籍①を参照しながら、境界知能と知的障害・発達障害との違いについて見ていきます。
【境界知能と知的障害の違い】
- 知的機能の差にある→境界知能:IQ70~84、知的障害:IQ70未満
- 適応機能が低い状態にあれば、境界知能のゾーンに該当している人でも知的障害と判断されることある(最近は適応機能がより重視されるようになっている)
【境界知能と発達障害の違い】
- 発達障害は特性(ASD・ADHD・SLDなどの発達特性)が軸になっているといった違いがある
- 近い用語として〝グレーゾーン″があり、グレーゾーンとは、発達障害傾向に加えて、適応障害が見られる人たちのことを指す
- 境界知能には、発達障害が併存することもある
以上、境界知能と知的障害・発達障害の違いについて簡単に見てきました。
境界知能で発達障害が併存していないケース、あるいは知的障害だと診断を受けたケースを除いて、境界知能単独のケースでは診断がつかないため支援の対象になることが難しいと言えます。
3.境界知能の特徴
著書には、〝境界知能″の状態は、〝軽度知的障害″に近いと想定することで、状態像が理解しやすくなると記載されています。
それでは、書籍①を引用しながら境界知能に見られる特徴について見ていきます。
先の見通しを立てられない
理解力・記憶力が弱い
勉強が全般的に苦手
生活面の困り事がある
感情のコントロールが難しい
援助要求がうまくできない
幼少期は無自覚で、思春期以降は隠そうとする
以上に、境界知能には、様々な面で学習・生活・仕事上での困り感が生じる可能性があります。
〝先の見通しを立てられない″とは、実行機能の弱さであり、計画を立てて物事を進める苦手さがあります。
〝理解力・記憶力が弱い″とは、ワーキングメモリの弱さであり、今ある情報を取り込みながら思考する苦手さがあります。
〝勉強が全般的に苦手″とは、国語・算数・理科・社会などの勉強面において、小学校2~3年生頃から勉強についていくことが難しくなると言われています。
〝生活面の困り事がある″とは、例えば、時間管理・金銭管理・身だしなみなどに問題が見られます。
〝感情のコントロールが難しい″とは、衝動性の問題に加えて、感情のコントロールがうまくできないことで自己肯定感が低下して二次障害へと繋がるリスクも考慮する必要があります。
〝援助要求がうまくできない″とは、具体的な相談方法がわからない(いつ・誰に)ことや、人を頼ってはいけないという誤った認識を持っていることもまたあります。
〝幼少期は無自覚で、思春期以降は隠そうとする″とは、年齢が上がるにつれて自分の周囲とのズレ・違和感を抱くようになり、その中で、できない自分を隠そうとする様子が出てきます。
このように、境界知能の人たちには、学習・生活・仕事など様々な所で困り感が生じることがあります。
著者の印象としても、境界知能の人たちは、特定の部分・領域だけではなく、非常に広い領域にわたって困り感が生じることが見受けられるため、〝軽度知的障害″の状態像と想定した理解がとても大切だと考えさせられます。
4.境界知能の支援の難しさ
以下に著書②を引用しながら見ていきます。
近年では、知的障害を伴わない発達障害を対象とした支援の施策が急速に進められつつある。今、こうした施策が最も手薄となっているのが、軽度精神遅滞および境界知能の人たちである。
軽度精神遅滞や境界知能の子どもたちは、家庭においても学校においても、他の子どもたちよりわずかずつ遅れを取りながら参加し続ける場面が圧倒的に多い。このため、自己評価が低い形で固定しやすい。
著書の内容から、現在、知的障害を伴わない発達障害への理解や支援が急速に進んでいく中で、支援の手が行き届きにくい人たちに〝境界知能″〝軽度知的障害″があると考えられています。
さらには、こうした人たちの多くは、周囲との少しのズレ・違和感・遅れを持ちながら集団参加をしているため、適応の難しさや失敗経験などによって自己評価が徐々に低下していくことも大きな懸念材料としてあります。
つまり、〝境界知能″の人たちは、まだまだ周囲から理解されていないといった背景に加えて、二次障害のリスクも高い点、さらには、先に見た医学的に診断がつかないことで支援の対象とはなりにくいことが影響して、支援が難しくなっていると考えられます。
著者の実感としても、〝境界知能″の人たちは、できる・できない、できそう・できなさそうといったはざまにいることで、周囲が当事者の困り感に気づきにくいこと、さらには、当の本人も具体的に何に躓いているのか(躓きそうなのか)よく分からないといった状態にあるのだと思います。
社会の中で、〝明確な″〝顕著な″困り感・問題として現れないことが逆に状態像の理解を難しくさせ、さらには、支援の難しさが生じているように思います。
一方で、理解や支援を受けずに困り感が残存し続けることで、将来的に二次障害などリスクが高まることも事実だと感じます。
5.境界知能への支援
それでは、境界知能への支援としてどのようなことを大切にしていけば良いのでしょうか?
以下、著書①を引用しながら見ていきます。
基本的な考え方として言えることもあります。境界知能の場合、勉強面でも生活面でも平均に対して70~80%の目標設定を心がけるのがよいということです。
境界知能の子どもも能力がまったく伸びないわけではありません。本人のペースでじっくり学習していきます。そのための目安が70~80%なのです。
〝境界知能への支援″で大切なことは、様々な事柄に関して、目標設定を低め(70~80%)に設けることが重要だと言えます。
境界知能の人たちは、定型発達児・者と比べて、少し低い知的機能であるため、勉強面でも生活面でも、定型発達児・者よりも低い基準値が必要だと言えます。
著者の実感として境界知能たちは、周囲が想定している以上に様々な事柄を学習・適応する難しさを抱えています。
そのため、著書にあるように、能力を伸ばすことよりも、その人に合った目標設定、つまり、目標設定を低めにしていく方法を取ることが必要だと考えます。
一方で、境界知能の人たちの知能を伸ばすことができると考えている人もいます。
以下、著書③を引用しながら見ていきます。
環境の変化を含めて慎重に検証する必要がありますが、IQは周りの大人との関わり方次第で変わる可能性も少なからずあるはずです。
それと脳には「可塑性」があります。脳は外界からの刺激などによって常に機能的な変化、構造的な変化を起こしているとされます。神経組織や回路が変化する性質があるのです。成長期の子どもの脳ならなおさら、常に変化してその能力を伸ばせる可能性があるのではないでしょうか。
著書にあるように、脳には〝可塑性″があります。つまり、変化の可能性があるということです。そして、特に成長期の子どもにおいて、変化の可能性が高いと言えます。
もちろん、IQを伸ばすことを目的とするのではなく、本人にとって着実に積み重なる学習をしていくこと、本人が楽しいと思えること、意味や達成感を感じることなどの視点を大切に学びの環境を整えていくことが大切だと言えます。
その結果として、脳の成長・発達が見られるようになるという認識が必要です。
書籍③の執筆者である宮口幸治さんは、〝コグトレ″と言われる〝認知機能の苦手さを持つ子どもや大人を対象とした認知機能強化トレーニング″を考案しています。
それに関する文献等をいくつか以下に紹介します。
3.境界知能に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
著者は、これまで見てきた境界知能に関する視点に加えて、境界知能に近い状態像として〝軽度知的障害″に関する情報も含めて理解や支援の手がかりを得ていきました。
併せて、著者はAさんに低い目標設定を設けることの重要性・本人に合った課題設定の必要性などを伝えていきました。
その結果、大きな変化として、Aさんは、これまで自分がなぜ周囲よりもうまくできなかったのか?周囲からの理解が得られにくかったのか?といった背景を深く知ることに繋がっていきました。
それは、Aさんが、境界知能の人たちの状態像とこれまでの自分とを照らし合わせることで、非常にリンクする点を多く見つけることができたからだと思います。
そのこともあり、これまでモヤモヤしていた違和感や周囲とのズレ・遅れなどの正体が徐々のクリアになることで、理解した・されたという安心感を得る様子が見られていきました。
また、Aさんは、以前立てていたようなハードルが高い目標・課題設定をより低めに設定する習慣を身につけていきました。
もちろん、全ての事柄ではありませんが、ある内容によっては、本人に合った繰り返しの学習、そして、スモールステップなど、学習方法を工夫していくことで、成長の実感を得る機会も増えように感じます。
このように、境界知能といった理解されにくい人たちに対して、どのような理解をしていく必要があるのか?どのような支援が必要であるのか?を考えていくことはとても大切だと著者は実感しています。
4.まとめ
〝境界知能″とは、知的機能が平均以下であり、かつ、知的障害に該当しない人たち(文献によって違いあり→IQが70~84のゾーンorIQ71~85のゾーン)のことを指します。一方で、明確な定義はなく、医学的な診断がつくことはありません。
境界知能と知的障害の違いは、知的機能の差にあります(境界知能:IQ70~84、知的障害:IQ70未満)。
境界知能と発達障害の違いは、発達障害は特性(ASD・ADHD・SLDなどの発達特性)が軸になっているといった違いがあります。また、境界知能には、発達障害が併存することもあります。
境界知能″の状態は、〝軽度知的障害″に近く、例えば、先の見通しを立てられない、理解力・記憶力が弱い、勉強が全般的に苦手、生活面の困り事がある、感情のコントロールが難しい、援助要求がうまくできない、幼少期は無自覚で、思春期以降は隠そうとするなどの特徴があります。
境界知能(軽度知的障害も含めて)の人たちは、支援の手が行き届いていない現状にあります。
境界知能への支援で大切なことは、様々な事柄に関して、目標設定を低め(70~80%)に設けることです。
また、具体的なトレーニング方法として、宮口幸治さんが考案した〝コグトレ″が有名です。
書籍紹介
今回取り上げた書籍の紹介
- 梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.
- 本田秀夫(2013)子どもから大人への発達精神医学:自閉症スペクトラム・ADHD・知的障害の基礎と実践.金剛出版.
- 宮口幸治(2023)境界知能の子どもたち 「IQ70以上85未満」の生きづらさ.SB新書.
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
知的障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「知的障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」









