〝境界知能″とは、〝知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態″の人たちのことを指します。
IQ(知能指数)で言うと、70~84のゾーンに当たります(71~85と記載されている文献もあります)。
〝境界知能″の特徴として、他の障害と比べた際の分かりにくさがある一方で、生活の中で様々な困り感が生じる可能性があると考えられています。
それでは、境界知能の人には、どのような困難さがあると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、境界知能の人に見られる困難さとは何かについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、日常生活で起こる困り感を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「古荘純一(2024)境界知能 教室からも福祉からも見落とされる知的ボーダーの人たち.合同出版.」です。
【境界知能の人に見られる困難さとは何か?】日常生活で起こる困り感について考える
著書には、〝境界知能の人に見られる日常生活の困難さ″に関して、4つの項目が記載されています。
以下、著書を引用しながら見ていきます。
境界知能の特性によるもの
二次的に生じるもの
他者からの評価
医療機関受診例に見られる特徴
それでは、次に、以上の4つの項目について、具体的に見ていきます。
境界知能の特性によるもの
境界知能の人には、コミュニケーションの問題(複雑なやり取りの難しさ)、言語理解の問題(抽象的な理解の困難さ)、数的処理の問題(高度な作業の難しさ)、処理スピードの遅さ(作業の遅さ)など様々な躓きがあるとされています。
知的水準が境界域であるため、例えば、知的検査に代表される〝言語理解″〝知覚推理″〝ワーキングメモリ″〝処理速度″など、様々な能力に遅れが見られます。
このような特性があることで、学習や仕事における理解力や実行力、他者とのコミュニケーション能力において、生活上様々な問題が生じると言えます。
著者は境界知能の人との関わりを通して、上記に記載した様々な領域において問題が見られると感じることが多くあります。
一方で、知能が境界域であるため、周囲から見て努力不足であると思われたり、一見するとできる・分かっているようにも見えてしまうことがあるため、本人の本質的な特性への理解を深めていくことが支援上とても大切だと感じています。
二次的に生じるもの
境界知能の人の困り感への支援が不足した状態が続くと、二次障害が発症するリスクが高まってきます。
そして、二次的に生じる状態像として、主体性の欠如、自己肯定感の低下、学習に対する習熟度の問題、支援を受けたくないといった思いなどがあるとされています。
著者が見てきた境界知能の人の中には、二次障害が発症しているケースもあり、こうしたケースにおいて、上記に記載した二次的に生じる状態像は非常に該当しているように思います。
そのため、できだけ早期から、境界知能の人への支援を継続して行っていくことが大切だと感じています。
他者からの評価
境界知能の人に対して、他者がどのように評価しているかと言えば、通常の生活を送る上での問題はない、能力について低いと感じないことがある、忍耐力や集中力に欠ける、本人が主体的に発信したり行動することが少ないなどがあるとされています。
著者が持つ境界知能の人への印象として、本人の自己評価と周囲からの評価のズレがあるといったことが本質的な課題だと感じています。
つまり、本人がうまくいかない・思うようにできないと思っていても、周囲の人たちはもっと頑張ればできる・やり方を工夫すればうまくいくといったように思えてしまうといった認識の違いがあるのだと思います。
そのため、評価がなぜ低くなってしまうのかの背景にしっかりと目を向けていくことが支援上とても大切なことだと感じています。
医療機関受診例に見られる特徴
境界知能の人たちの医療機関の受診例には、いじめ・不登校・ひきこもり・ゲーム依存・心身の不調など様々な特徴があるとされています。
つまり、境界知能といった一次的な障害があることで、学校への不適応状態、外界に向かう意欲の低下、漠然とした無力感など様々な要因が影響して医療機関にかかることが境界知能のケースにおいては少なからずあると言えます。
著者がこれまで見てきた境界知能の人の中には、医療機関を受診しているケースもありました。
そのケースの実態として、そもそも支援に繋がっていなかったケース(支援が遅れたケース)、本人に合っていない支援を受け続けたケースなどがあったように感じます。
境界知能への理解と支援はまだまだ途上であるため、今後、ますます本人のニーズに応じた支援の必要性が高まっていくと感じています。
以上、【境界知能の人に見られる困難さとは何か?】日常生活で起こる困り感について考えるについて見てきました。
今回は、参考書をもとに、境界知能の人に見られる日常生活の困難さについて、4つの項目から見てきました。
以上の内容を踏まえると、境界知能の人たちには、非常に広範囲における困り感が生じることがあるのだと言えます。
そのため、様々な困り感に対して、できるだけ早期の理解と支援が必要だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も境界知能の人への理解を深めていきながら、生活における困り感を解消していく様々な手立てについて学びを継続していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【境界知能の二次障害の予防の重要性】発達障害児・者支援の経験を通して考える」
関連記事:「【境界知能と思ったら取るべき対応】悩みの相談先について考える」
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
古荘純一(2024)境界知能 教室からも福祉からも見落とされる知的ボーダーの人たち.合同出版.


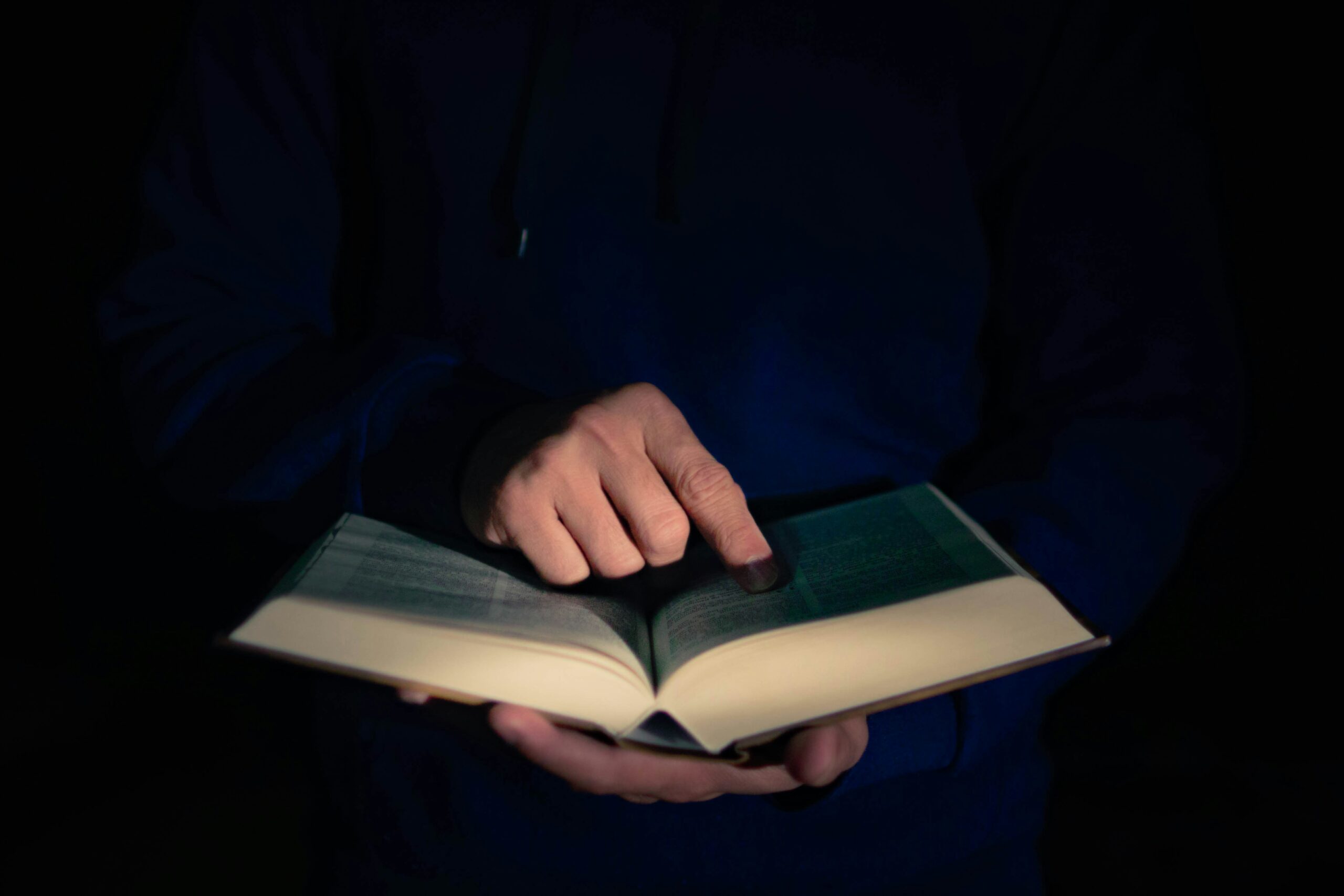
コメント