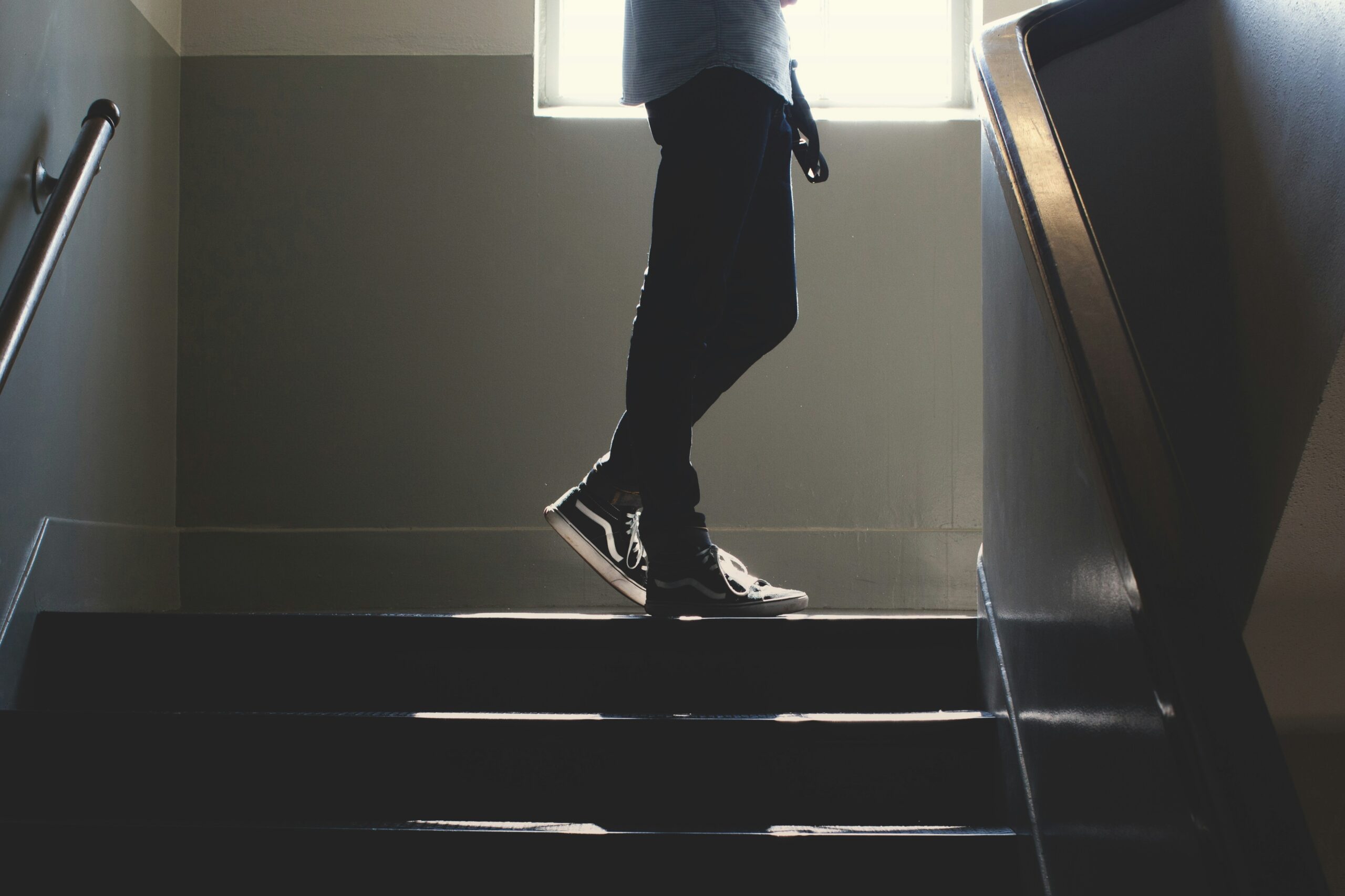
子どもが急に〝学校に行きたくない″と言えば当然親は戸惑います。
子どもが学校に行き渋ることは急に起こることもあるかもしれませんが、子ども自身が悩み抜いた末に出すSOSだとも考えられます。
それでは、子どもが学校に行きたくないと言い始めた際にどのような対応が重要となるのでしょうか?
そこで、今回は、不登校の子どもへの初期対応について、〝子どもが学校に行きたくない″といった場合の対応について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「下島かほる(2019)健康ライブラリーイラスト版 登校しぶり・不登校の子に親ができること.講談社.」です。
不登校への初期対応について
著書には不登校への初期対応の基本として大切な点をいくつか取り上げています(以下、著書引用)。
子どもが話しやすい状況をつくる
「行きたくない理由」への対応
身体症状が強いとき
ゆっくり休ませる
以上の4点について具体的に見ていきます。
1.子どもが話しやすい状況をつくる
以下、著書を引用しながら見ていきます。
子どもが「行きたくない理由」を話さない場合には、無理に問いつめるより、話しやすい状況をつくることを心がけましょう。
子どもが学校になぜ行きたくないのかは親なら当然気になります。
行きたくない理由を聞き取ることで解決方法が見えてくることもありますが、子どもによっては〝うまく言葉にできない″〝話しにくい理由がある″〝話したくない″など様々な思いもあります。
そのため、著書にあるように、無理に問い詰めることはぜずに、一緒に過ごす時間を増やすなど話しやすい雰囲気を作ることが重要です。
2.「行きたくない理由」への対応
以下、著書を引用しながら見ていきます。
「休む」という形で回避するのではなく、カバーする方法がないか考えていきます。
子どもには学校に行きたくない理由があります。
もちろん、漠然とした不安感など言葉にならない(できない)という場合もあります。
どちらにせよ、著書にあるように、行きたくない理由に対しては、単純に〝休む″対応ではなく、行きたくない理由を〝カバー″する方法はないかを考えていく必要があります。
3.身体症状が強いとき
以下、著書を引用しながら見ていきます。
ストレスが身体症状として現れるのはよくあることです。決して仮病ではなく、実際に痛みが生じたり、胃腸の働きが低下したりします。医療機関を受診しておきましょう。
不登校の初期状態として、頭痛や腹痛など身体症状として現れることがあります。
周囲の人からすると、身体症状の訴えは、学校に行きたくない口実として言っているようにも見えるかもしれませんが、当の本人は本気で悩み苦しんでいます。
心理的なストレス要因が身体症状として生じている場合(その可能性がある場合)には、著書にあるように、医療機関の受診の検討が必要です。
4.ゆっくり休ませる
以下、著書を引用しながら見ていきます。
「休みたい」と言っている以上、これといった理由がわからない場合でも、「エネルギーが底をつきかけているのだ」ととらえてください。心身の回復のためには、休息が必要です。
冒頭で述べた通り、学校への行き渋りは、子どもが悩み抜いた末に出したSOSです。
周囲の大人からすると、学校への行き渋りは、初期状態と捉えてしまうかもしれませんが、それ以前に、子どもは様々なことを経験しその中で悩み自分なりに解決策を見出そうと必死にもがいた結果であると言えます。
そのため、次の行動意欲を引き出すためには、まずは、著書にあるように、〝休息″が必要です。
心身のエネルギーを充電する期間がある程度は必要だということを考えていく必要があります。
以上、【不登校の子どもへの初期対応】〝子どもが学校に行きたくない″といった場合の対応について見てきました。
不登校の子どもへの初期対応には今回見てきたような様々な方法があります。
すべての子どもに共通した万能な方法はないかもしれませんが、様々な引き出しを持って対応していく必要があると思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も不登校の子どもについて理解を深めていけるように、専門的な知見についても情報を集めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【不登校の子どもへの基本対応】まずは現状を肯定することから考える」
不登校に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「不登校に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
下島かほる(2019)健康ライブラリーイラスト版 登校しぶり・不登校の子に親ができること.講談社.









