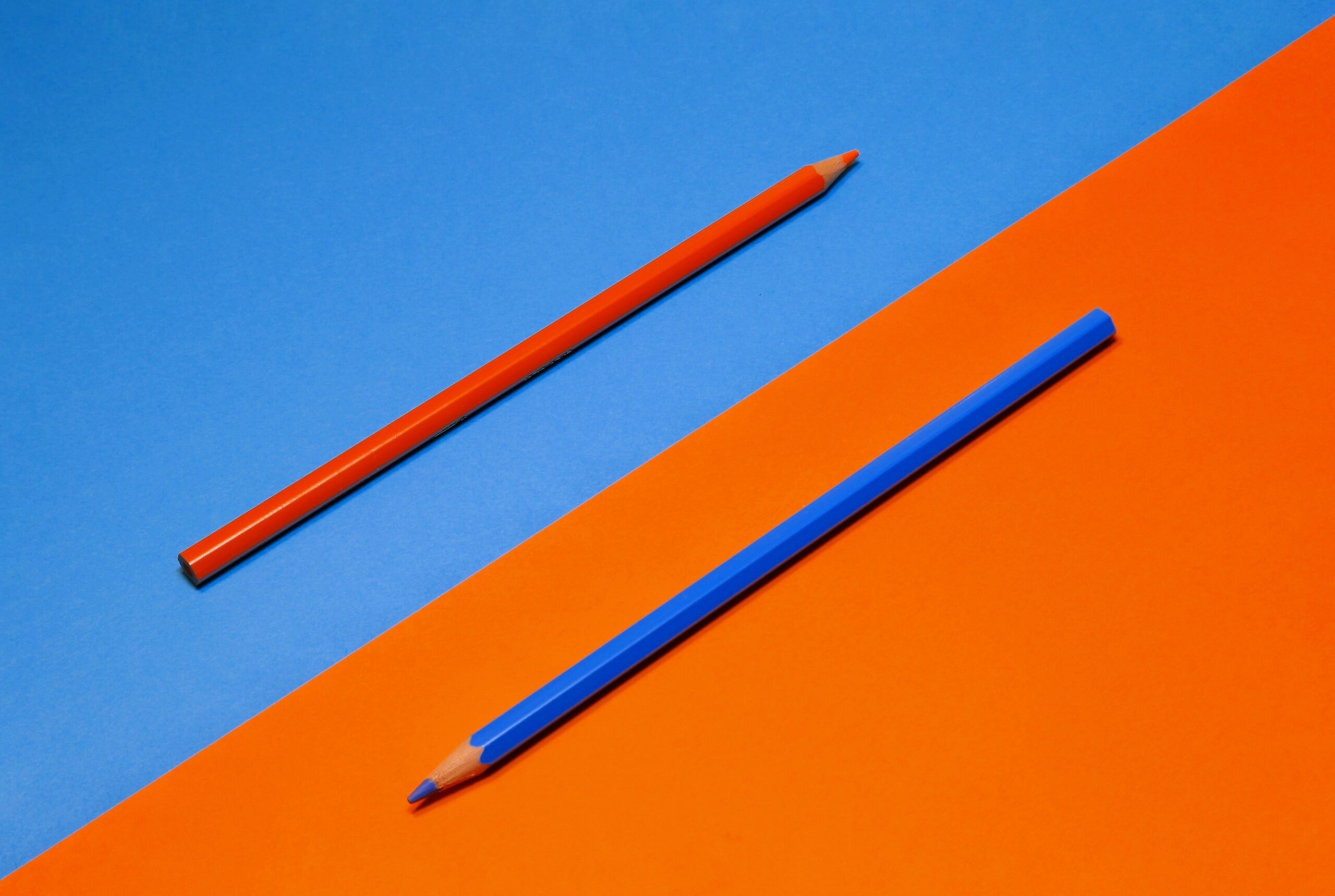
著者はこれまで児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどで療育に携わってきました。
長年療育をしていると、良い時期もありますし、悪い時期もあります。
こうした良い時期・悪い時期を振り返って見るとそれぞれの時期に質的に異なる学びがあると思います。
今回は、著者の療育経験を通して、良い時期・悪い時期のそれぞれから得られた学びについてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
良い時期からの学びについて
まず、良い時期とは何か?ということですが、これは人によって内容が異なるかと思いますので、ここでは著者の経験からお伝えします。
著者にとって良い時期とは、子どもたちのへの理解や支援がうまくいっている時期だと思います。
例えば、子どもたちが楽しく活動を持続していることや、ポジティブな変化(○○に興味を持った、○○ができるようになったなど)がみられるなどがあります。また、これまで取り組んできた支援がうまくいくようになったなどがあります。
療育の良さは、こうしたポジティブな変化をチームの仲間たちと共有する喜びに加え、関わり手の子どもと楽しさやできた喜びを共有したり、保護者ともまたそうした変化を共有するなど、人と喜びを共有できることです。
こうした良い時期が続くと、子どもたちそれぞれが何を欲しているのか?何に喜びを感じるのか?どのような経験を通して人への信頼や自信を獲得するようになったのかなどを考えるきっかけになります。
そして、こうしたポジティブな変化から、子どもたちの発達において何が必要であるのかを考えるヒントや習慣が身に付いていきます。
悪い時期からの学びについて
良い時期と同様に悪い時期もまた、人のよって内容が異なるかと思います。
悪い時期とは、苦労した時期、理解や支援がうまくいってない時期のことだと思います。
著者は思いのほか、悪い時期からの方が、学びが多かったように思います。
それは、苦労の末に人をより深く理解できると思っているからです。
関わり手が苦労するケースの多くは、生きづらさを抱えている人(子ども)です。
例えば、発達特性が配慮されずに育ってきた親子のケース、様々な発達特性が重複し理解が難しいケース、二次障害に発展しているケース、遊びにうまくハマれないケースなど様々あります。
こうした相手と関わることは、苦労を共にすることでもありまので、より深く相手のことを考えようと自ずとなっていきます。
著者も信頼関係をつくるのに年単位で時間を要したケースや二次障害へと発展してしまったことで状態像の理解が非常に複雑化したケースなど、関係づくりの面や障害特性の理解など本人の生きづらさを理解するのにとても時間を要しました。
しかし、そうした過程の中で迷走しながらも、身体と頭をフル稼働し、相手への理解が深まった実感することはこれまで多くありました。
もちろん、現在進行形で関わっている場合には、良き学びができているなど余裕をもった思考はできないことが多かったです。
正直、疲労困憊することも多々ありました。
あくまでも振り返ってみての話ですが、悪い時期(苦労した時期)が他者の痛み生きづらさへの共感や理解を深めることや、人間の発達の多様性を理解するにはとても大切だと思います。
以上、短いですが療育からの学びを、良い時期と悪い時期に分けてみてきました。
どちらの時期にもそれぞれの学びがあると思います。
逆に言えば、両方の時期をじっくりと経験することで、療育の大切さや深さを実感できるようになるのだと思います。
私自身、まだまだ未熟であり道半ばですが、これからも、様々な療育経験を通して、その中で深い意味を見出していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。









